No.00345�@Future Design |
 �W���G���[���w�A�[�g�x�ƕ]�����ׂ� �����I�ȕ��͋C���Y���A�[�e�B�X�e�B�b�N�ȑ��`�����͂̕ł��I�� |
 |
�wFuture Design�x ���̑��݁A���_���X�^�C���̃v���`�i���g�����ō����s�A�X�ł���� |
||
 |
|
||
���_���X�^�C�������܂ꂽ����̓C�M���X�M���̒������������A�p�g�����ƂȂ��㗬�K�����������Ă��܂����B���̌��ʁA���_���X�^�C���̃n�C�W���G���[�͋ɂ߂Đ������Ȃ��ł��B�ō����������S�[���h����v���`�i�Ɉڂ�ς��ߓn���ɂ��d�Ȃ��Ă���A�v���`�i���g�p�������̂Ɍ��肷�����ɐ��͏��Ȃ��ł��B �j��ł������]�����ꂽ����ɉ�����A�Ƃ艐���ɏ�̓V�R�^��B�����Ő�[�̃g�����W�V�����J�b�g�E�_�C�������h�̃N���A�Ŕ��������߂��B����܂łɌ������Ƃ̂Ȃ��A����Z�p����g�������_���X�^�C���炵���v���`�i�E�t�H�����B�v���`�i�E�t���b�g���C���̃C���p�N�g����P���B�ō����i�ł��邱�Ƃ������A�����̑�ꋉ�̐E�l�ɂ�錩���ȍ��B �܂��ɏ����Ȕ��p�i�I�����Č�肩���鏬���ȕł��� |
���̃̕|�C���g
 |
|
1. �M���炵���C�i�ɖ������ō��i���̓���p�W���G���[
 |
���̋C�i�ɖ������������́A�M��������p�̃W���G���[�Ƃ��ăI�[�_�[�����ƍl������㎿�ȃs�A�X�ł��B |
1-1. ������TPO������M���̃W���G���[
1-1-1. �����̓��{�l���^��"�W���G���["�̈Ⴂ��m��Ȃ��w�i
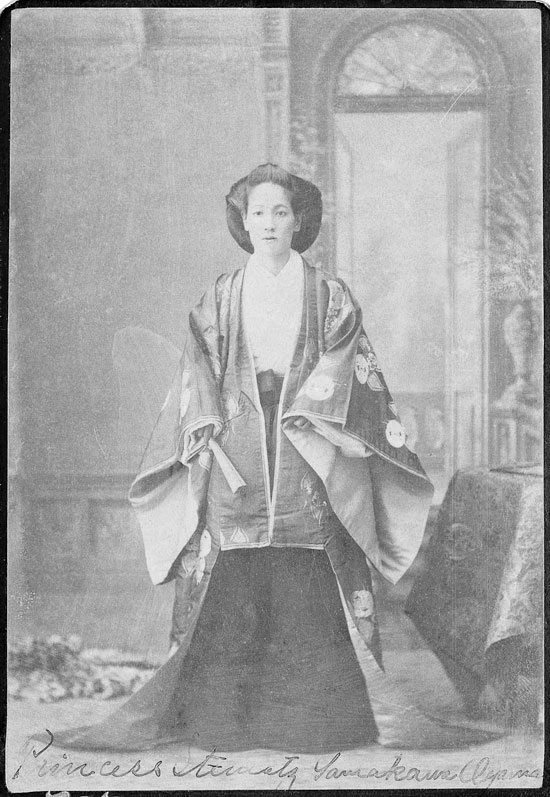 �A���ɎQ�������R��̏��i1860-1919�N�j1882�N�A22�� �A���ɎQ�������R��̏��i1860-1919�N�j1882�N�A22�� |
���������W�������{�̓W���G���[�������Ȃ��A���N�W���G���[�̗��j�����������A���E�I�ɋH�L�ȍ��ł��B |
| ����p�̃W���G���[�𒅗p����1880�N�㍠�̏㗬�K�� | |
| ���{�̏㗬�K�� | ���[���b�p�̏㗬�K�� |
 ���ݕv�l ��R�̏��i1860−1919�N�j1880�N��H ���ݕv�l ��R�̏��i1860−1919�N�j1880�N��H |
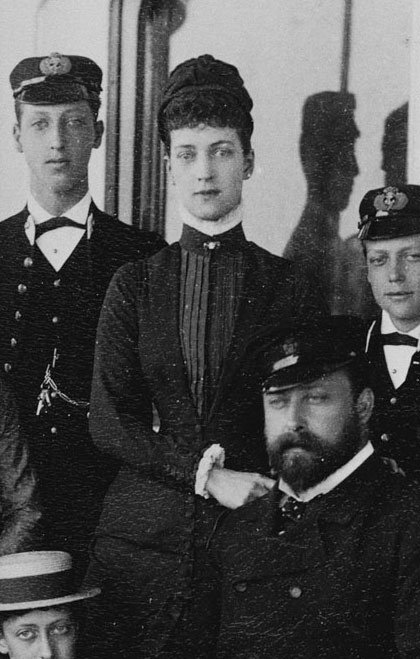 �C�M���X�����q�܃A���N�T���h���E�I�u�E�f���}�[�N�Ƃ��̉Ƒ��i1880�N�j �C�M���X�����q�܃A���N�T���h���E�I�u�E�f���}�[�N�Ƃ��̉Ƒ��i1880�N�j�y�o�T�zRoyal Collection Trust / The Prince and Princess of Wales with their shildren, 1880 [in Portraits of Royal Children Vol.26 1880] / © Her Majesty Queen Elizabeth II 2020 / Adapted |
���{�l���W���G���[�𒅗p����悤�ɂȂ����̂́A�J����Ƀ��[���b�p������������Ă���ł��B�A���A����͌���ꂽ�㗬�K���݂̂ł��B1947�N�ɋM�����p�~�����ȑO�͓��{�ɂ��g�����x������A�ؑ���m���Ȃǂ̏㗬�K�������݂��܂����B ��O�͋M���������A�����̎�ȒS����ł���A�����K���Ƃ��Č��͂�U�肩�����Ƃ������̓m�u���X�I�u���[�W���I�ɁA���ꂠ����̂̐Ӗ��Ƃ��Đ�s���郈�[���b�p�Ɋw�Ԃ悤�s�͂��Ă��܂����B���{�̏㗬�K�����w�ԑΏۂ̓��[���b�p�̏����ł͂Ȃ��A���R�Ȃ��瓯���g���ł��郈�[���b�p�̏㗬�K���ł��B �M���̏����̏ꍇ�́A�����悤�ɋM���̏����̃t�@�b�V������������Ă��܂����B����͓���̑����ŁA�W���G���[�⏬��������p�̂��̂ł��B�������s���Ă����A�̃o�[�E�u���[�`������ł��B���^�������ł��ˁB |
|
| �����p�̃W���G���[�𒅗p����1900�N�㍠�̏㗬�K�� | |
| ���{�̏㗬�K�� | ���[���b�p�̏㗬�K�� |
 ���ݕv�l ��R�̏��i1860−1919�N�j1919�N�ȑO ���ݕv�l ��R�̏��i1860−1919�N�j1919�N�ȑO |
 �m���E�F�[���܃��[�h�i1869-1938�N�j1906�N�A37���i�p�����G�h���[�h7���̎O���j �m���E�F�[���܃��[�h�i1869-1938�N�j1906�N�A37���i�p�����G�h���[�h7���̎O���j |
�����p�̃W���G���[�͂܂��ʂɂ���܂��B����́A�������s���Ă��������O�`�F�[��������̃R�[�f�B�l�[�g�ł��B ����̏����ƁA�Â̏㗬�K���ł̓R�[�f�B�l�[�g�̑g�ݗ��ĕ����S���قȂ�܂��B�Â̏㗬�K���̓W���G���[�ɉ����ăh���X�A������TPO�ɍ��킹�ĕς���K�v������A��������̃A�C�e�����K�v�ł����B |
|
| ���ʂ̋M���̂��߂̍ō����W���G���[ | |
 �C�M���X�̃��B�N�g���A�E�A���N�T���h�������i1868-1935�N�j1906�N�A38�A���B�N�g���A�����̑� �C�M���X�̃��B�N�g���A�E�A���N�T���h�������i1868-1935�N�j1906�N�A38�A���B�N�g���A�����̑� |
 �w�z���C�g�E���f�B�x �w�z���C�g�E���f�B�x�V�R�^�쁕�v���`�i�E�`�F�[�� �C�M���X�@1920�N�� SOLD |
���삳��Ă���100�N�ȏオ�o�߂����W���G���[�́A�����̂��߂̗ʎY�̈����܂Ŋ܂߂āw�A���e�B�[�N�W���G���[�x�ƌĂ�Ă��܂��Ă��錻��ɂ���܂����AHERITAGE�ł��Љ��W���G���[�́A��������㗬�K���̂��߂ɍ��ꂽ�M�d�ȍ����i�ł��B �����ɂȂ�Ƃ������肢��������ʂ�A1�_1�_���ޗ��A�f�U�C���A���ɂƂ�ł��Ȃ��������������Ă��鍂���Ȃ��̂ł��B |
|
| TPO�Ŏg��������㗬�K���̃W���G���[ | ||
| ��E���� | �����E���� | ����p |
 �w�����̏��_�x �w�����̏��_�x�K�[�����h�X�^�C�� �l�b�N���X �C�M���X or �t�����X�@1920�N�� ¥6,500,000-�i�ō�10%�j |
 �w�����n�Ԃ���鑾�z�_�A�|�����x �w�����n�Ԃ���鑾�z�_�A�|�����x�V�F���J���I�@�u���[�`���y���_���g ���[���b�p�@19���I��� ¥1,330,000-�i�ō�10%�j |
 �w�����̃��[�X���[�N�x �w�����̃��[�X���[�N�x���{���@�u���[�` �C�M���X�@1910�N�� SOLD |
��p�A�����p�A���ꂼ��ɐ����Ɠ���p�Ȃǂ�����A�܂��l�X�ȎЌ��V�[���Ŏg�����߂ɂ��ꂼ��̃W���G���[���K�v�ƂȂ�܂��B����ɐ�q�▼�h����ȂǁA�e�포���������Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B����̏����ɂ͑z�����ł��Ȃ��قǂ�����������܂��B ���ہA��ʂ̏����ɂ͑z���ł��܂���B����M���̎��オ�I�����}���A��O�̎���ƂȂ������ɍ��ꂽ�A����̕���ƊE���ݒ肵��������ɍl����l���唼�ł��B����̕���ƊE�ɓs�����ǂ��悤�ɐݒ肳�ꂽ���̂ɉ߂����A�W���G���[�̐^�̉��l�f���邽�߂̂��̂ł͂���܂���B�ނ���A���������ɓs���������Ȃ�̂ł���A���l������̂����l���Ⴂ�ƌ��悤�Ȃ��Ƃ����C�ł��܂��B�y���ċ��ׂ������㖽��ł���A�ւ�������ĉ��l������̂��Љ�A���q���܂Ɋ��ł��炢�����A���g���ǂ��d���������Ƃ������������Ƃ������z�͂���܂���B |
||
| �t�����X�̃N���E���E�W���G���[ | |
 �t�����X���܃}���[�E�A�����E�h�E�u���{�����V�V���i1782-1866�N�j1830�N�A48�� �t�����X���܃}���[�E�A�����E�h�E�u���{�����V�V���i1782-1866�N�j1830�N�A48�� |
 �t�����X���܃}���[�E�A�����̃T�t�@�C�A�̃p�����[���i���܂݈̍ʁF1830-1848�N�j �t�����X���܃}���[�E�A�����̃T�t�@�C�A�̃p�����[���i���܂݈̍ʁF1830-1848�N�j"Parure della regina maria amelia, parigi, 1800-15 poi 1850-75 ca" ©Sailko(16 June 2016, 16:34:00)/Adapted/CC BY 3.0 |
���̂悤�ȁA��O�ɂ���O�̂��߂̑�O�p�W���G���[�̔��f��Ƃ����m���I�Ȏ��ɉ����āA��O���ڂɂ��鑽���́A����M�������������p�ł��B�h�肳�������āA���̂悤�Ȏp�͈�ۂɋ����c��܂��B ���̌��ʁA�����̑�O���M���̏����͂����S�[�W���X�ȃh���X�ɋ���ȕ���t�����W���G���[�𒅂��Ă�����̂��Ɗ��Ⴂ����悤�ł��B�����āA���̂悤�ȕ��i�͒����ĊO�ɏo�������Ȃ��悤�ȃh�h��ȃW���G���[����������M���̃W���G���[�ł���Ǝv�����ނ̂ł��B |
|
 ���B�N�g���A�����i1819-1901�N�j1898�N�A79�� ���B�N�g���A�����i1819-1901�N�j1898�N�A79�� |
����Ȋ������A��O�ɂƂ��Ẳ���M���̏����̃C���[�W�ł��B ��݂����ȃi�C�t�͂�����ƈႢ�܂����E�E�i�j
����͕��h��ŁA�����Ɍ����Ă��s�U��蕪���邽�߂̃i�C�t�ł��B |
| �C�M���X�̃A���N�T���h�������q�܁i��̉��܁j�̃R�[�f�B�l�[�g | |
| ���o������ | ���� |
 1884�N�A40�� 1884�N�A40�� |
 1881�N�A36�� 1881�N�A36�� |
�����p�̃h�h��ȃW���G���[�͏d�����ł��B ��O�̎���ƂȂ������́A�M���������g�p���Ȃ��f�U�C�������̖͑��i���A������O�̂悤�Ɏs��Ɉ�ꂩ����܂����B�p�b�ƌ������A����ŃM�����č������Ɍ�����A�N�Z�T���[�ł��B�����͎��ƂƂĂ��y���ł��B�������Ȃ��玄�������ł������A�{���̃W���G���[�ɐG�ꂽ���Ƃ��Ȃ��ƁA�M�����ƕ�ō��ꂽ�W���G���[���ǂꂾ���d���̂��z�����ł��܂���B���͍��A�{���̍ō����W���G���[�Ɉ͂܂�Ďd�������閲�̂悤�ȏɂ���܂��B���܂ɃA�N�Z�T���[����ɂ���ƁA�u�y�����E�E�E�H�I�v�Ƌ����Ă��܂��܂��B���ꂭ�炢�Ⴂ�܂��B ���ł��e�B�A�����^�p���Ă���p�������̘b�Ƃ��āA�e�B�A���͏d�߂��Ē����Ԃ͒��p�ł��Ȃ��A�����͓����ɂ��Ȃ�Ȃǂ̃G�s�\�[�h���������ɂȂ������Ƃ������������������Ǝv���܂��B |
|
 �����q�܃A���N�T���h���i1844-1925�N�j1889�N�A44�� �����q�܃A���N�T���h���i1844-1925�N�j1889�N�A44�� |
�h��ȃW���G���[�𒅂���̂́A����M���ɂƂ��Ă�����ȃV�[���݂̂ł��B |
| �A���N�T���h�������q�܁i��̉p�����܁j��3�l�̉��� | |
| �������o�ȗp�̐��� | ���i�� |
 �W���[�W���q�̌������p�i1893�N�j �W���[�W���q�̌������p�i1893�N�j |
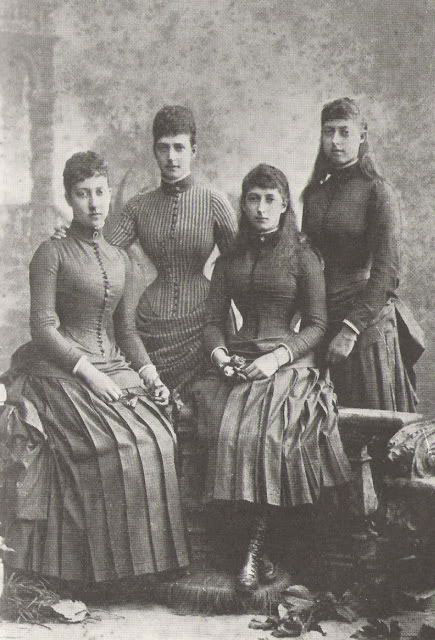 |
���������͂̋M���̃t�@�b�V�������[�_�[�ƂȂ�܂�����A�������Q�l�Ɍ��Ă݂�ƁA���i���͌���̎����������Ă���a�����Ȃ��قǃJ�W���A���Ȃ��Ƃ�������܂��B���i���Ƀh�h��ȕ�M���M���E�W���G���[�̓R�[�f�B�l�[�g���܂���B ���̌������ɎQ�����邽�߂̐���������ƁA�W���G���[�Ɍ�����TPO�����邱�Ƃ�������܂��B�e�B�A���𒅗p���Ă���̂�2�l�����ł��B����͔N�ゾ����A������W���G���[������Ȃ������Ȃǂ̕s���Ăȗ��R�ł͂Ȃ��A�����҂݂̂��e�B�A���𒅗p����Ƃ������[���ɂ̂��Ƃ������̂ł��B ����̓��{�̍c���̉^�p�@���A�Ȃ������N�ɂȂ�ƐU���ł͂Ȃ��e�B�A������邱�ƂɂȂ��Ă��邽�߁A�u���P�l���e�B�A���v�Ƃ�������𑽂��̓��{�l�ɗ^���Ă���悤�ł��B���̂悤�ȉ^�p���[���ɂȂ����w�i�͕����肩�˂܂����A�������ׂ����������̂��Ȃ��Ƒz�����Ă��܂��B���l���ł́A����������̍������U���𒅗p���܂��B�����̕����A��قǓ��{����������Ă���悤�ȏł��ˁB����ł��唼�̐l�̓����^���ߑ��ł��傤�B�e�B�A���ɂ�����\�Z�i���{�����̐ŋ��j��U���̃I�[�_�[����Ɍ�����A��قǓ��{�����̕ۑ���V���ɂ��𗧂Ǝv���܂��B�S���ł͂Ȃ��Ă��^�����ĐU�����I�[�_�[����l�������o�Ă���ł��傤���A�����E�ɐV�������s�ݏo���A���v�𑝂₷���Ƃ����҂ł��܂��B�t�@�b�V�������[�_�[�Ƃ��ĐV����������n��A�o�ς��č����S�̂̍K���ݏo�����Ƃ����Ăł���͂��Ȃ�ł����ǂˁB��������Ȃ��̂́A������ʐl���m��Ȃ����R�͂���̂�������܂���B |
|
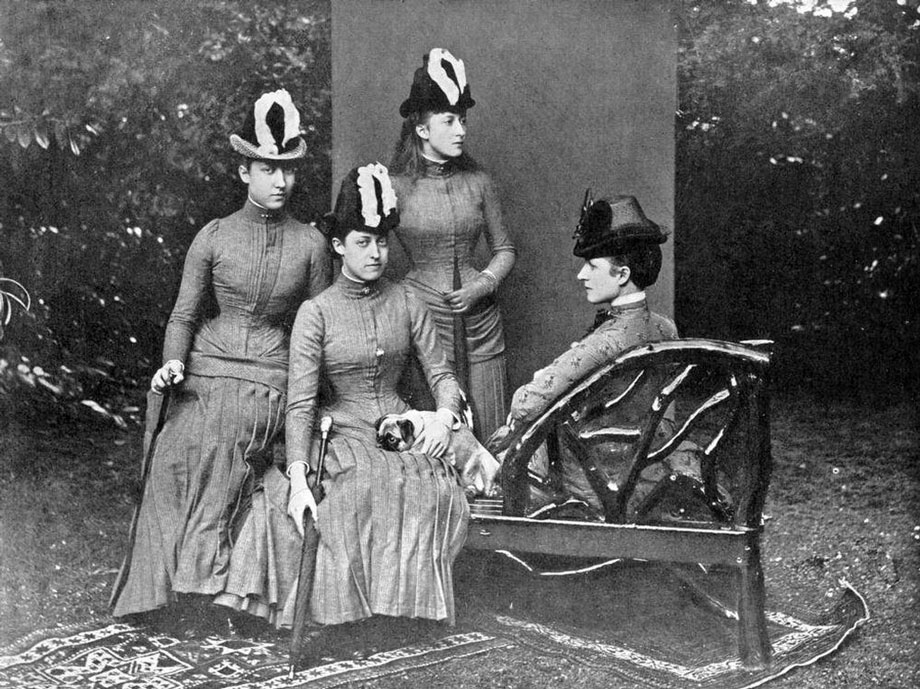 �A���N�T���h�������q�܂�3�l�̖����� �A���N�T���h�������q�܂�3�l�̖����� |
���āB�Ẩ���M���͕��i���ł��A�W���G���[�𒅂��Ȃ��Ƃ������Ƃ͂���܂���ł����B���i���p�̃W���G���[��������Ƒ��݂��܂����B�����p�̃h���X�ɕ��i���p�̃W���G���[�����킹�邱�Ƃ͂���܂��A���i���ɐ����p�̃W���G���[�������܂���B3�l�̉������A�������s���Ă����o�[�E�u���[�`�⏬�Ԃ�̃u���[�`���ɒ����Ă��܂��B |
| �Պ����̉p�����܂̐��� | �p�������N���X�Ƃ��Ȃ�A�W���G���[�͂Ƃ�ł��Ȃ��������L���Ă��܂��B ������A����ȃR�[�f�B�l�[�g���\�ł��B �u�����Ă���W���G���[�A�S���������������ł����H�i�j�v�Ƃ������炢�Z���X�̂Ȃ��R�[�f�B�l�[�g�ł����A����͎���w�i���l����Ƃ��傤���Ȃ��ł��B �鍑��`�ɂЂ����鎞��B�V�����͂̃A�����J���䓪���A���[���b�p�������Y�Ɗv�����o�Ă��̂������悤�ɂȂ�A���|�I�Ȑ��E�̒��S�Ƃ��Ă̑�p�鍑�̒n�ʂɗh�炬�������n�߂�����ł����B �e���̉������m�ł��ǂ��炪�ォ����������Ɉӎ����Ă���A�Ƃɂ����������ȃW���G���[�Ńh����K�v���������̂ł��B �Z���X���ǂ��A���{���[���ł͂Ȃ��A�Ƃɂ������l�ɕ�����₷���悤�x�ƌ��͂̐������h����Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���ł����B |
 �C�M���X���܃A���N�T���h���E�I�u�E�f���}�[�N�i1844−1925�N�j1902�N���A58�� �C�M���X���܃A���N�T���h���E�I�u�E�f���}�[�N�i1844−1925�N�j1902�N���A58��"1902 alexandra coronationhr" ©Franzy89(9 August 1902)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |
 �t�����X���܃}���[�E�A�����̃T�t�@�C�A�̃p�����[���i���܂݈̍ʁF1830-1848�N�j �t�����X���܃}���[�E�A�����̃T�t�@�C�A�̃p�����[���i���܂݈̍ʁF1830-1848�N�j"Parure della regina maria amelia, parigi, 1800-15 poi 1850-75 ca" ©Sailko(16 June 2016, 16:34:00)/Adapted/CC BY 3.0 |
��̋��傳�Ńh���邱�Ƃ́A����M���ł�����܂��B�����A���傳�ɂ���č����Ȃ��Ƃl�ɕ�����₷�������ނ̂��̂ł���A����̂ɁA�f�U�C���ɂ͌l�̃Z���X�̗ǂ������荞�ޗ]�n�����܂肠��܂���B �㗬�K���̂��߂̍����i�Ȃ̂ō��͔��Q�ɗǂ��̂ł����A������������̃f�U�C������őS���ʔ����Ȃ���ɁA�h���h���������͋C�������`����Ă��āA�G��Ă��ĐS�n�悢���̂ł͂Ȃ���ɁA���Ă��邾���ŐS�������ǂ��납�A�Ԃ��ăG�l���M�[���z������Ĕ��܂��i�j ���������W���G���[�͍������Ƃ͍����ł����A�㗬�K���ɂƂ��Ă͎d���p�̃W���G���[�ɉ߂����AHERITAGE������舵��������猩��Ύ��ɑ���Ȃ��i���ƒf���ł��܂��B�����ɂ̓s�b�^�����Ǝv���܂����A�����Ƃ͊ւ�肽���Ȃ��̂ł���舵�����܂���i�j |
| ���i���̃G�h���[�h7���̍ȃA���N�T���h���� | |
 |
 �y���p�zBritanica / Alexandra ©2021 Encyclopædia Britannica, Inc. �y���p�zBritanica / Alexandra ©2021 Encyclopædia Britannica, Inc. |
���[�������߂邱�Ƃ��ł��闧��̉����ł���A���������ۂɂ��������Ă���̂ł�����A�h���E�W���G���[���D���Ȃ�Ε��i���ɒ��p���邱�Ƃ͉\�ł��B�������Ȃ���A�����ł͂���܂���B�d���Ƃ��ăh����K�v���Ȃ����i�������A������̌������f���ꂽ�W���G���[���R�[�f�B�l�[�g���܂��B�d���p�ł͂Ȃ��A���̂悤�ȃW���G���[�����A�����ȕƂ��đ�Ɋ����Ă������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��ł��傤�B |
|
 �w�S�[���h�E�I�[�K���W�[�x �w�S�[���h�E�I�[�K���W�[�x�G�h���[�f�B�A�� �y���h�b�g���z���C�g�E�G�i���� �l�b�N���X �C�M���X�@1900�N�� ¥1,000,000-�i�ō�10%�j |
���̂悤�ȃW���G���[�́A�m���̂Ȃ������ɂ܂Ő������Ɍ�����K�v������܂���B �ڂɐG���̂́A���͂̏㗬�K���݂̂ł��B �������g�̐S�̖����ł�������A���{��m���A���I�Z���X�̂�����͂̏㗬�K���ɑf���炵���Ǝv���Ă��炦��Ηǂ��ł�����A����������̋��{��m���A�Z���X�����߂Đ��삳��܂��B �����珬�����̂Ɍ��ǂ��낪���ڂŁA���ꂼ��Ɍ��������āA���Ă��ĖO���邱�Ƃ�����܂���B |
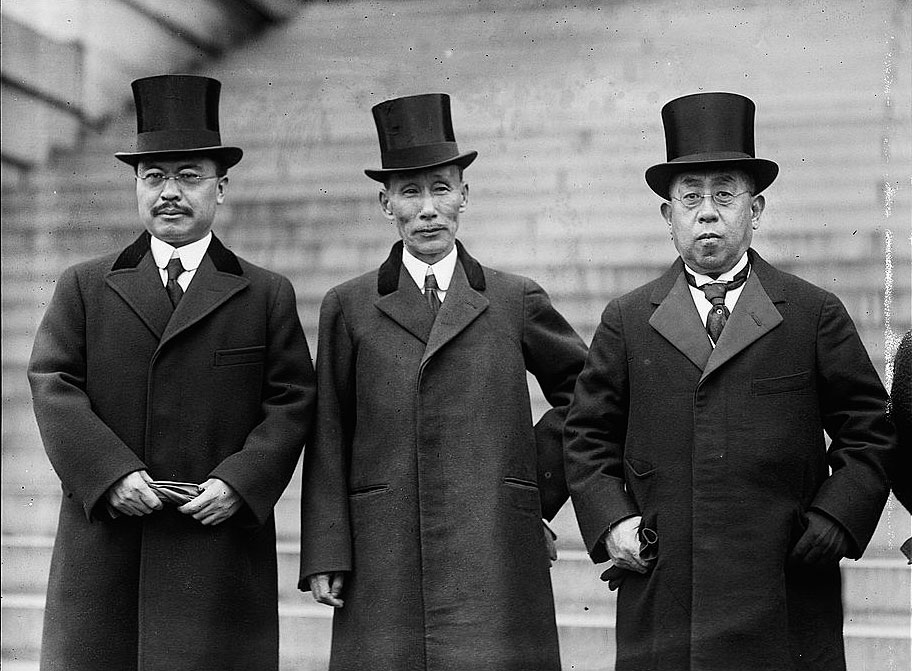 ���V���g���R�k��c�̑S����g�i1921�N11��3���j ���V���g���R�k��c�̑S����g�i1921�N11��3���j������d�Y �j�݁A�����F�O�Y �q�݁A����ƒB ���� |
����́A��̐��������Ŕ��f����l�������ł��B���{���͕̂K�v�ɉ����Ęa���ł��m���ł��g�Ȃ�𐮂���K��������܂������A����ł͍������X�g�������u�T���_����Z�p���͂��������������B�v�ȂǁA�h���X�R�[�h���w�肵�Ȃ���Ȃ�ʂق�TPO�ɍ��킹�����������镶�����p��Ă��܂��܂����B �t�@�b�V�����ɂ̓h����Ӗ������łȂ��A����ɗ��������i�Ƃ��Ă̖ʂ�����A���ł�����ł����t�ŃJ�W���A���ɂ���Ƃ����͈̂Ⴄ�͂��Ȃ�ł����ǂˁB���ǁA�t�@�b�V���������̐��ނƋ��ɁA���{�l�̗�V�̕����܂Ŏ����Ă������悤�Ɋ����܂��B |
 �w�V��̃I���S�[�������[�x �w�V��̃I���S�[�������[�x�A�[���f�R �V�R�^�쁕�T�t�@�C�A �l�b�N���X �C�M���X�@1920�N�� ¥1,230,000-(�ō�10��) |
���ł����R�̔@�������i�D�B����I�ԕK�v���Ȃ��A��������̎�ނ��K�v�Ƃ��܂���B
����̓W���G���[�����l�ł��B �����̏ꍇ�A�Ẩ���M���̂悤�ȗL��]��قǂ̍��͂������܂���A�n�C�W���G���[�������������Ǝ��̂��{���͕s�\�ł��B �A���e�B�[�N�W���G���[���m��ꂴ�鑶�݂ƂȂ�������́A���ꂽ�������炷����蓾�Ȃ����i�Ŏ�ɓ���܂��B���̂悤�ȕ��������ɂȂ��Ċy���߂�������݂���A�����ɂ���Ă͂���Ӗ��K�^�Ȏ��ゾ����������܂��B |
 �y�Q�l�z����̖��Ղ��������t�H�u�V�[�� �y�Q�l�z����̖��Ղ��������t�H�u�V�[�� |
���̂悤�ȗ�O�I�ȕ��͕ʂƂ��āA����̏�����1�̃W���G���[���g���ꍇ�����Ȃ�����܂���B ����͐̂̏��������l�ŁA�����p�ɍ��ꂽ�����قǃw�r�[���[�e�[�V�����ɂ�門�Ղ��������ł��B |
| �y�Q�l�z������Ղ������� | |
 |
 |
���̂��̂́A�g���̂��|�����炢���茸���Ă��܂��ˁB���p�̏Ƃ��čD�ޕ�������������Ǝv���܂����A�����ł��邪�̂ɓK�Ȉ��������Ă��炦�Ȃ������A��ɂ��Ă��炦�Ȃ������ƌ��邱�Ƃ��ł���ł��傤�B |
|
 �w�A���v�X�̗n���Ȃ��X�x �w�A���v�X�̗n���Ȃ��X�x�A���v�X�Y���b�N�N���X�^���@��]��3�ʃt�H�u�V�[�� �C�M���X�@18���I�㔼 ¥1,400,000-�i�ō�10%�j |
HERITAGE�ʼn���M���̂��߂ɍ��ꂽ�A���e�B�[�N�W���G���[�����߂Ă����ɂȂ�ƁA�܂�ō����ꂽ���̂悤�Ȕ������ɋ������������Ȃ�����܂���B ������͂����������Ă���̂Ńw�r�[���[�e�[�V�������Ȃ����ƁA�K�Ȉ����������Ă���A200�N�ȏ���R���f�B�V������ۂ��Ƃ��\�Ȃ��ƂȂǂ����R�ł��B ���Y�������Ƃ����̂́A�����g����ł�����܂��B |
| ����̃G�������h�I�ȃ����O | ||
| �u�����h�i�i�G�������h�̏ڍוs���j | ������ | �N���X�^���K���X |
 �G�������h�E�����O�i�J���e�B�G�@����j���i�͂��⍇�����������Ƃ̂����y���p�zCartier / SOLITARIO 1895 ©CARTIER �G�������h�E�����O�i�J���e�B�G�@����j���i�͂��⍇�����������Ƃ̂����y���p�zCartier / SOLITARIO 1895 ©CARTIER |
 �����G�������h�E �����O�i���Z���@����j �y���p�zodolly / �G�������h�����O�i�I�[�o��/2.29/�����_�C��4��/�c�C�X�g/K18�z���C�g�S�[���h/5���a���j ©���Z���W���G���[�ʔ̃V���b�vodolly-�I�[�h���[ �����G�������h�E �����O�i���Z���@����j �y���p�zodolly / �G�������h�����O�i�I�[�o��/2.29/�����_�C��4��/�c�C�X�g/K18�z���C�g�S�[���h/5���a���j ©���Z���W���G���[�ʔ̃V���b�vodolly-�I�[�h���[ |
 �O���[�����z���C�g�E�N���X�^���̃��W�E�����b�L�E�V���o�[�E�����O�i�X�����t�X�L�[�@����j�y���p�zSWAROVSKI / Attract Cocktail Ring Green, Rhodium plated ©Swarovski �O���[�����z���C�g�E�N���X�^���̃��W�E�����b�L�E�V���o�[�E�����O�i�X�����t�X�L�[�@����j�y���p�zSWAROVSKI / Attract Cocktail Ring Green, Rhodium plated ©Swarovski |
����W���G���[�ɍ��Y���������Ă�����́A�ǂꂭ�炢����������ł��傤���B�u�����h�����Ɣ����l�����݂��邽�߁A���Îs��ł����̒l�i���t���͂���悤�ł����A�W���G���[�Ƃ��Ă̐^�̉��l�͂���ł��傤���B ��͐l�H������������O�ƂȂ�A�����Z�p���m�����ꂽ���ƂŋH�����l���������A�Z�p�v�V�ɂ���Č����ڂ��Y��ȃC�~�e�[�V������������O�ɂȂ�܂����B �M���������g��Ȃ��w�A�N�Z�T���[�x�ł��A�����ڂ͏\���Ɍ���W���G���[�Ɠ����Ɍ����܂��B������f�U�C���ƍ�肪�����ł�����E�E�i�j �����ڂ������Ȃ�A���������ǂ��ƍl����l�������͓̂��R�ł��B�ȑf�ȃf�U�C���ƍ��ɂ��邱�Ƃɂ�萻���R�X�g��}���A�����W���G���[�Ƃ��č������邱�ƂŖ\�����ނ��ڂ�������W���G���[�ƊE�ł����A�A�N�Z�T���[�ƕς��Ȃ��Ȃ������ʁA���ł͔���Ȃ��Ȃ��Ă���悤�ł��B �W���G���[�Ȃ����Y��ł�������A���Y���������Ă��Ē���������Ȃǂ̃����b�g������A���z���o�����Ƃ���Ԃ����ł͂Ȃ��ł����A������o���Ӗ�������W���G���[�ɂ͂܂�Ŋ������Ȃ��ł�����ˁB ��ɂ��Ȃ��Ă����C�B�g���̂āB���̂悤�Ȋ��o����A����W���G���[�ɂ͕t���Ă��܂�����������܂���B1�̃W���G���[�C�Ńw�r�[���[�e�[�V�������A���茸��������Ă��C�ɂ��Ȃ��Ƃ����̂����ʂ̊��o�ɂȂ��Ă���l���A�c�O�Ȃ��炢��悤�ł��B |
||
1-1-2. ���ꂼ��̃W��������"�ō����i"�����݂���A���e�B�[�N�W���G���[
| �@�����͑S�čō����i�Ƃ��Đ��삳�ꂽ�A�Ẩ���M���̂��߂̃A���e�B�[�N�W���G���[�ł��B1�A���邢�͐����Ȃ��W���G���[���g���̂�������O�BTPO���B���B����Ȍ��㏎���̑����͂�������ׂČ����ꍇ�A�����w����̎��_�x�������ō����i�ŁA�����w����̎��_�x�قǍ����ł͂Ȃ��W���G���[�Ɣ��f���܂��B |
| TPO�Ŏg��������㗬�K���̃W���G���[ | ||
| ��E���� | �����E���� | ����p |
 �w����̎��_�x �w����̎��_�x��2ct�̃_�C�������h �u���[�` �t�����X�@1870�N�� SOLD |
 �w���a�̂��邵�x �w���a�̂��邵�x���[�}�����U�C�N �f�~�p�����[�� �C�^���A�@1860�N�� ��2,030,000-�i�ō�10%�j |
 �wMODERN STYLE�x �wMODERN STYLE�x�_�C�������h �u���[�` �C�M���X�@1890�N�� SOLD |
���̗��R�́A�w����̎��_�x�͑傫�ȃ_�C�������h���t���Ă���A�w���a�̂��邵�x�͕���g���Ă��炸�A�wMODERN STYLE�x���w����̎��_�x�Ɣ�ׂ�ƃ_�C�������h������������ł��B�����y�U�A���Ȃ킿�������f��ňꏏ�����ɔ��f�ł���Ǝv������ł��邩��ł��B�����܂ł����ɂȂ������́A����������ł���ˁB��̐����p�W���G���[�͂��̃W�������ł̍ō����i������A�����p�̐����ɂ͂��̃W�������ł̍ō����i������܂��B����p�W���G���[���R��ł��B |
||
1-1-3. �|�p���ŋ����f�C�E�W���G���[
| �W���[�W�A���̐����p�u���X���b�g | |
| �����p | ��p |
 �wDay & Night�x �wDay & Night�x�W���[�W�A�� �}���`���[�X �u���X���b�g �t�����X�@1820�N�� SOLD |
 |
| ��͋P���̔������_�C�������h�ȂǁA�������̃W���G���[���g�p���܂��B����A�����̓M���M����������t�������̂͒��p���܂���B | |
| �|�p���̍����ŋ��{/�m��/�Z���X�������f�C�E�W���G���[ | ||
 �w�����y���V���e�B���c�q�F���x �w�����y���V���e�B���c�q�F���x�S�[���h�E�A�[�g�@�u���[�` �C�M���X�@1870�N�� SOLD |
 �w�n�b�s�[�E�G���W�F���x �w�n�b�s�[�E�G���W�F���x�X�g�[���J���I���t�F�U�[�p�[���@�u���[�` �t�����X�H�@1870�`1880�N�� ¥1,200,000-�i�ō�10%�j |
 �w�K�N�x �w�K�N�x�s�G�g���h�����@�u���[�` �C�^���A�@1860�N�� SOLD |
�f�C�E�W���G���[�͕�ł͂Ȃ��A�|�p���̍����ŋ����܂��B����͂܂莝����̋��{�A�m���A�Z���X�������̃|�C���g�ƂȂ�Ƃ������Ƃł��B ���̂悤�ȕ𒅗p���Ă����Ẩ���M���́A���Ō����w�r���I�l�A�i���Y10���h�� / ��1370���~�j�̂悤�ȑ��݂ł��B�u���̃W���G���[�A1���~�������̂�I�h���A�@�@�I�I�v�A�u����A�����3����I��������A���قفI�I�v�Ƃ����悤�ȁA���������̐����̂悤�ȃh���荇���̓t�B�b�g���܂���B�����͕���قǎ����Ă���A���������o���Δ�����悤�Ȃ��̂́A��������|�C���g�ɂ͂Ȃ蓾�Ȃ��̂ł��B�����ŕK�R�I�ɏd�v�ɂȂ�̂��A�l�̔\�͂ł����B �f�C�E�W���G���[�͗D�������͋C�̓V�R�^��ł�������A���H��J���I�A���[�}�����U�C�N��s�G�g���f�����A�G�i�����Ȃǂ̌|�p�I�ȗv�f���������̂�����ɂ��č���܂��B�f�ނ����Ŕ��f���鐬���n�D�̐l�ɂ́A�����ł��܂���B�Ẩ���M���ł������ł���l�A�����łȂ��l�����݂��A���`�̐[���₻�̃Z���X�������|�C���g�ƂȂ�܂����B����Ӗ��A�i�C�g�E�W���G���[��艜�[���ʔ������E�ł���ˁB |
||
| �|�p���̍��������p�f�C�E�W���G���[ | |
 �s�G�g���h�����@�s�A�X �s�G�g���h�����@�s�A�X�C�^���A�@1830�`1840�N HERITAGE�R���N�V���� |
 �s�G�g���h�����@�o���O�� �s�G�g���h�����@�o���O���C�^���A�@1860�N�� HERITAGE�R���N�V���� |
�������̐��E�ɓ��邫�������ƂȂ����^���̃A���e�B�[�N�W���G���[���A�|�p���̍����ŋ����f�C�E�W���G���[�ł����B ����W���G���[���S���Y�킾�Ǝv�����A���������W���G���[��1�������Ă��܂���ł����BGen�H���A�܂��͂���Ȃ�̕���t���Ă�����̂������A�������Ă���悤�ɂȂ�ƁA���̂悤�Ȍ|�p�n�̃A���e�B�[�N�W���G���[�������ł���悤�ɂȂ�l�����邯��ǁA����ł����̂悤�Ȑl�͖ő��ɂ��Ȃ������ł��B ���ɂƂ��Ă͎�ɓ���`�����X�����邱�Ƃ���K�^�ł���A�����ē��R�Ƃ����F���ł����B�����̌|�p���A���ɒm��ꂸ�����Ă���B���ꂪ�f�C�E�W���G���[�ƌ����邩������܂���B�l�̐l�������ς���͂����B�{���ɖʔ������E�ł��ˁB |
|
| ����M���̐����p�W���G���[�̍ō����i | |
| �����p | ��p |
 �w�ߌ��̏����N���I�p�g���x �X�g�[���E�J���I�@�y���_���g �J���I�F�C�^���A or �t�����X�@19���I���� �t���[���F�C�M���X�@19���I���� SOLD |
 �wMIRACLE�x �G�h���[�f�B�A���@�u���b�N�I�p�[���@�y���_���g �C�M���X�@1905�`1915�N�� ¥10,000,000-�i�ō�10%�j |
����̊��o���Ɓu�ǂ����I�ԁH�v�A�u�ǂ��炪�D�݁H�v�Ƃ������o�ɂȂ肪���ł����A�ǂ�������K�v���������̂��Ẩ���M���ł��B���ꂼ��ڎw���ׂ���������Ă���A�����p�A��p�̑o���ɍō����i�����݂��܂��B�r���p�W���G���[�A�X�|�[�e�B���O�E�W���G���[�ȂǁATPO�ɍ��킹���e�X�̃W���G���[�ɂ��ō����i�����݂��܂��B�W�������Ⴂ�Ȃ̂ɁA�ǂꂪ���������c�_���邱�Ǝ��̂��i���Z���X�Ȃ̂ł��B |
|
1-2. ���{�l�ɂ����i�g�����₷���M���̓���p�W���G���[
�@����p�W���G���[�́A�f�C�E�W���G���[����ł��B�A�������p�قnj|�p���͋l�ߍ��܂��A�����܂ł�����g�����₷���f�U�C���ɂȂ��Ă��܂��B�i���ǂ����^�B���Ԃ�Ŏ咣�����������i���ɓ���݁A����ł��ď㗬�K���炵�����M���͎��킸�A���{��Z���X��������Ɠ`����Ă���f�U�C���ƂȂ�܂��B |
 ���[�h�����i14���j�A���C�[�Y�����i16���j�A���B�N�g���A�����i15���j�i1883�N�j ���[�h�����i14���j�A���C�[�Y�����i16���j�A���B�N�g���A�����i15���j�i1883�N�j |
���{�l�����ɂƂ��ẮA���̏㗬�K���̂��߂ɍ��ꂽ����p�W���G���[���ł�������₷���Ǝv���܂��B����20���I�̏㗬�K���̓���p�W���G���[�́A����̃t�@�b�V�����Ɉ�a���Ȃ�������₷���Ǝv���܂��B |
1-2-1. �A���e�B�[�N�̓���p�W���G���[
�@19���I�������20���I�����ɂ����ẮA���E�̒��S�ł����p�鍑�̃A���N�T���h���܂��A���E�̏㗬�K���̃t�@�b�V�������[�_�[�ł����B�A���N�T���h���܂͎��ᜂ̎�p��������A������J�o�[���邽�߂Ɏ̋l�܂������𒅗p���A���ꂪ����M���ɗ��s���Ă��܂����B |
| ����p�̃W���G���[�𒅗p����1880�N�㍠�̏㗬�K�� | |
| ���{�̏㗬�K�� | ���[���b�p�̏㗬�K�� |
 ���ݕv�l ��R�̏��i1860−1919�N�j1880�N��H ���ݕv�l ��R�̏��i1860−1919�N�j1880�N��H |
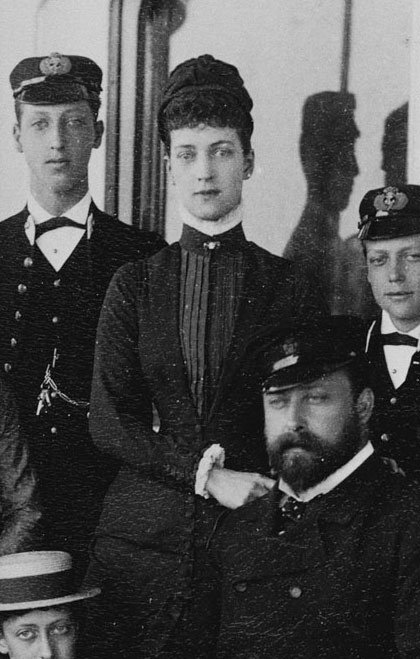 �C�M���X�����q�܃A���N�T���h���E�I�u�E�f���}�[�N�Ƃ��̉Ƒ��i1880�N�j �C�M���X�����q�܃A���N�T���h���E�I�u�E�f���}�[�N�Ƃ��̉Ƒ��i1880�N�j�y�o�T�zRoyal Collection Trust / The Prince and Princess of Wales with their shildren, 1880 [in Portraits of Royal Children Vol.26 1880] / © Her Majesty Queen Elizabeth II 2020 / Adapted |
���l�܂������ɉf����W���G���[�Ƃ��āA�ɒ��p���鏬�Ԃ�̃u���[�`��o�[�E�u���[�`�����s���܂����B���̎���͎Y�Ɗv���ɂ���đ䓪�������Y�K�����W���G���[�𒅂���悤�ɂȂ�������Ȃ̂ŁA�A���e�B�[�N�W���G���[�s��ɂ��㗬�K���p�̍����i�ƁA�����p�̈��������݂��Ă��܂��B���|�I�命���ł������A�����p�̈������唼�ł��BHERITAGE�ȊO�̂��X�ł����ɂȂ�ꍇ�́A���̂悤�ȏ����p�̃W���G���[���w�ǂȂ͂��ł��B �����p�̈����͑f�ނ������ǂ��Ȃ��ł����A�܂��f�U�C�����ʔ�������܂���B |
|
1-2-2. �����p�̗ʎY�̈����W���G���[�̓���
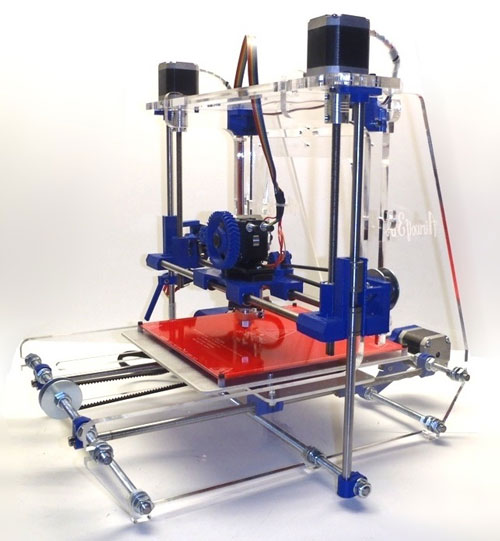 3D�v�����^�̈�� "Airwolf 3d Printer" ©Eva Wolf(28 May 2012)/Adapted/CC BY-SA 3.0 3D�v�����^�̈�� "Airwolf 3d Printer" ©Eva Wolf(28 May 2012)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |
�@�ȑO�A3D�v�����^���b��ɂȂ�܂����B�f�W�^���t�@�u���P�[�V�����ʼn��ł������D�݂̂��̂��f�U�C�����A���E��1�����̂��̂𐧍�ł���Ƃ�搂�����ł����B ���̌�A�Љ�ω��������ƌ����A�S�����̂悤�Ȉ�ۂ͂���܂���B |
"�����ōD���Ȃ��̂����R�Ƀf�U�C���ł���" ���ƂȂ��������͗ǂ��ł����A���ۂɂ������낤�Ƃ����ꍇ�A�ǂꂭ�炢�̐l��������肭����ł���ł��傤���B �o���̂Ȃ��f�l���A�f�U�C���̕��������ɂ����Ȃ�[������D��ăf�U�C���ݏo�����Ƃ��Ă��A���ʂ͂��܂������܂���B�����ł��B�v���̃f�U�C�i�[�ɂƂ��Ă�������ƂȂ̂ł�����B���s����قǂ̃q�b�g���i�����o���̂��A�����ɓ�����Ƃ���z������Ε����邱�Ƃł��B �I�[�_�[���C�h�ʼn��������ɂ��Ă��A�p�^�[���E�I�[�_�[�����������ł��B���ƂȂ�D�ꂽ�f�U�C�������݂��A�����ɂ�����ƃI���W�i���ŕύX����������A�z�F��ς�����x�������I�ł��B ���ǎ����ł�낤�Ƃ��Ă������ł�����̂͂ł����A�v�����f�U�C�����������i���������y���ėǂ��f�U�C���̕�����ɓ���A���������ǂ̓g�[�^���R�X�g�Ƃ��Ĉ��オ��ł���Ƃ������_�Ɏ���͂��ł��B�f�W�^���t�@�u���P�[�V���������s��ɒ�ԉ����Ȃ������̂́A���R�ƌ����Γ��R�Ȃ̂ł��B |
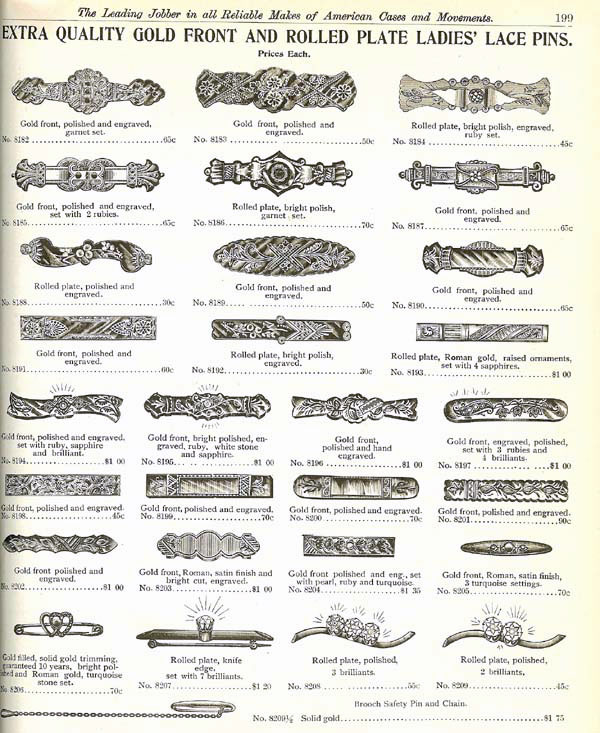 �����̃��[�J�[�̃J�^���O�i�A�����J�@19���I����j �����̃��[�J�[�̃J�^���O�i�A�����J�@19���I����j |
�̂̐l�������ł��B���������킯�ŁA�����͑�ʐ��Y�̊����i����I�Ԃ��ƂɂȂ�܂��B�̔����ׂ͖��邱�Ƃ���Ԃ̖ړI�ł��B���v�̍ő剻���l�����ꍇ�A���l�����̗D�ꂽ�f�U�C���ł͂Ȃ��A�Ȃ�ׂ������̐l�ɑi���ł���f�U�C����ڎw�����ƂɂȂ�܂��B���l��_�����A��������̂Ȃ��t�H�[�J�X�̃{�P���f�U�C���ƂȂ�܂��B�����͂ǂ�����Ă������悤�ɂ��������Ȃ��A������������̂��̂������̂͂��̂悤�ȗ��R�Ɉ˂�܂��B |
1-2-3. �㗬�K���̃W���G���[�̃f�U�C��
 �t�����X���܃}���[�E�A���g���l�b�g�i1755-1793�N�j �t�����X���܃}���[�E�A���g���l�b�g�i1755-1793�N�j |
�@�Ẩ���M�����A����̏����̊��o�őz�����Ă͂����܂���B �����l�ԂƂ͎v���Ȃ����炢�l�X�ȍ˔\�Ɍb�܂ꂽ�l����������A���̐l�������V�������s�ƁA����ɂ܂ő������Ղ̕�����n�����܂����B �H��̃Z���X�����Ƃ��ē��ɗL���������̂��A�t�����X���܃}���[�E�A���g���l�b�g�������ƌ�����ł��傤�B |
 ���܂̑��� "Vue aérienne du domaine de Versailles par ToucanWings - Creative Commons By Sa 3.0 - 037 " ©ToucanWings(19 August 2013, 19:25:10)/Adapted/CC BY-SA 3.0 ���܂̑��� "Vue aérienne du domaine de Versailles par ToucanWings - Creative Commons By Sa 3.0 - 037 " ©ToucanWings(19 August 2013, 19:25:10)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |
�}���[�E�A���g���l�b�g�͏��V�z���邱�Ƃ͂���܂���ł������A���ƂƂ̓��O�ȑł����킹���o�āA�����Ő�[�������C�M���X���뉀�������ꂽ"���z�̔_���W��"�A�w���܂̑����x���\�z�E������Ă��܂��B�����ł͎q�������ɁA���Ō����w�H��x���s���Ă��܂����B |
| �h���X | �W���G���[ |
 ���[�Y�E�x���^���i1747-1813�N�j ���[�Y�E�x���^���i1747-1813�N�j |
 �wREGARD�x �wREGARD�x�W���[�W�A�� REGARD ���P�b�g�E�y���_���g �C�M���X�@1820�N�� SOLD |
�h���X���Ɋւ��ẮA�w�t�@�b�V������b�x�ƌĂ��قǏd�p���ꂽ�����o�g�̎d�������[�Y�E�x���^�����L���ł��B�g�[�^���ŁA�D�ꂽ�Z���X�̃t�@�b�V�������Ăł��������ł��B���ʑO��1772�N�A�}���[�E�A���g���l�b�g��17�̎�����̒��ŁA8�ΔN�ゾ�����x���^���͗���邨�o����Ƃ���������������������܂���B 1774�N�Ƀ��C16�����t�����X���ɑ��ʂ���ƁA�Պ������ォ��x���^���͏T2��̃y�[�X�ōŐV�̍�i�������ɒ�Ă���悤�ɂȂ�܂����B�ו��Ɏ���܂ł̂Q�l�̏�M�͑����Ȃ��̂ŁA�ł����킹�ɂ͖����Ԃ���₵�������ł��B ����A�[�g�̂����Ŋ��Ⴂ����l�������ł����A�V�˂͒����ŏu�ԓI�ɗD�ꂽ�f�U�C����n��킯�ł͂���܂���B�V���̍˂����l���ł����Ă��A�����œ��]���t����]���A�O���ɗl�X�ȃC���X�s���[�V���������߁A�������肭�X�p�[�N�����ē������邱�ƂŐV�����D�ꂽ�f�U�C���ݏo���Ă��܂����B ����͂��̓��̐��Ƃ��Ȃ�������ɂ���X��������܂����A�˔\�Ɠw�͂����ꂾ���ɏW�����������Ƃɏ���Ƃ����l�����͘����ł��B�W���G���[�Ɋւ��Ă��A������ƐM���ł�����ƂƑł����킹�����āA�V�������̂�n���Ă��܂����B ��̓������Ŕ閧�̃��b�Z�[�W��`����A�N���X�e�B�b�N�E�W���G���[�́A����ł��l�C������܂��B������}���[�E�A���g���l�b�g�����˂ŁA�t�����X�̃W���G���[�E�f�U�C�i�[�A�W�������o�e�B�X�g�E�������I�i1765-1850�N�j�Ƌ��ɕ҂ݏo�����ƌ����Ă��܂��B |
|
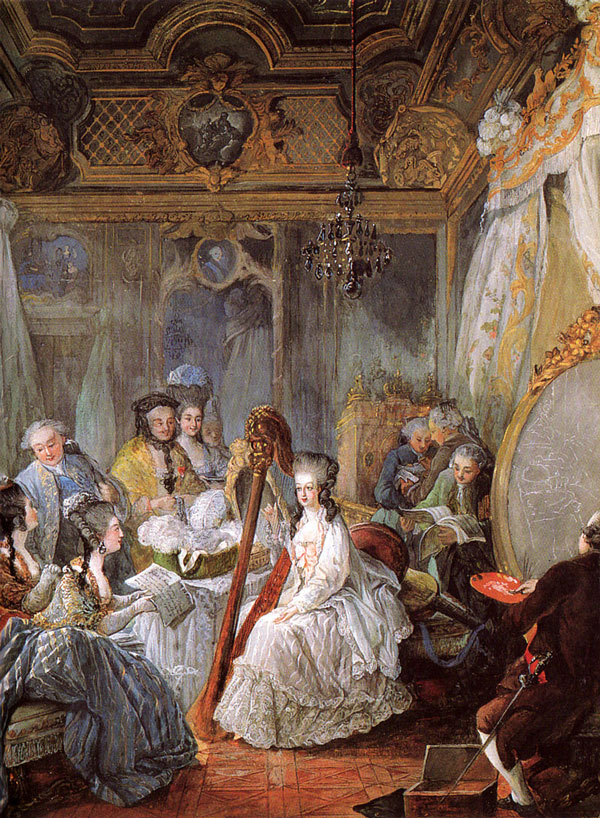 �n�[�v��t�ł鉤�܃}���[�E�A���g���l�b�g�i1777�N�A22���j �n�[�v��t�ł鉤�܃}���[�E�A���g���l�b�g�i1777�N�A22���j |
�}���[�E�A���g���l�b�g����藧�ĂėL���Ȃ̂́A�㗬�K���ł����Ă����ʂ͂����܂Ō��o�����Z���X�������Ă��Ȃ���������ł��傤�B �����̐l�́A������x�͐��Ƃɂ��C�����Ă����Ƒz�����܂��B �I���W�i���e�B������̂ł����Ă��A���ꂪ�D��Ă��Ȃ���Ώ^�̑Ώۂɂ͂Ȃ�܂���B �C���Ȃ��������̈���Ȃ��̂ł���ΒN���������������A�^�����܂���B�^�����Ȃ���Η��s�ɂ��Ȃ炸�A�l�m�ꂸ��������݂̂ł��B�V�����f�U�C���ݏo���͖̂{���ɑ�ςŁA�˔\���K�v�Ȃ��ƂȂ̂ł��B |
 �U�N�Z�����R�[�u���N���S�[�^���q�A���o�[�g�i1819-1861�N�j21���A1840�N�� �U�N�Z�����R�[�u���N���S�[�^���q�A���o�[�g�i1819-1861�N�j21���A1840�N�� |
���[�W�F���V�[�E�X�^�C���ŗL���ȃC�M���X���W���[�W4�����D��Ă��܂������A���B�N�g���A�����̕v�������A���o�[�g���z�����̋��{�̐[���͎Ќ��E�ł��m���Ă���A�ʑ��̉��z�f�U�C���ɉ����āA�W���G���[�E�f�U�C���܂łł���l���ł����B |
 |
 |
| �A���o�[�g���z�����B�N�g���A�����̂��߂Ƀf�U�C�������T�t�@�C�A�̃e�B�A���i1842�N�j V&A���p�� �y���p�zV&A museum © Victoria and Albert Museum, London/Adapted |
|
1840�N�Ƀ��B�N�g���A�����͌������Ă��܂����A�������ĊԂ��Ȃ�1842�N�ɃA���o�[�g���z�����̃e�B�A�����f�U�C�����Ă��܂��B�����ɂȂ��Ă���A�ʏ�̃e�B�A���Ƃ��Ă����łȂ��A�ւ����������ăR���l�b�g�̂悤�ɒ��p���邱�Ƃ��ł��܂��B���B�N�g���A�����̒��p�̎d�����A�Ȃ��Ȃ��ʔ����ł���ˁB |
|
 �I���W�i���̃I���G���^���E�T�[�N���b�g�E�e�B�A���𒅂������B�N�g���A�����i1853�N���j �I���W�i���̃I���G���^���E�T�[�N���b�g�E�e�B�A���𒅂������B�N�g���A�����i1853�N���j |
1853�N�ɂ̓I���G���^���E�T�[�N���b�g�E�e�B�A�����A�ȃ��B�N�g���A�����̂��߂Ƀf�U�C�����Ă��܂��B �ŏ��̖����A1851�N�̃����h������������ŃI���G���^���E�f�U�C���ɉe�����A��D���������I�p�[�����g���ăf�U�C���������̂ł��B |
|
 �I���G���^���E�T�[�N���b�g�E�e�B�A���i1853�N�j �I���G���^���E�T�[�N���b�g�E�e�B�A���i1853�N�j�y�o�T�zRoyal Collection Trust / The oriental tiara © Her Majesty Queen Elizabeth II 2021 |
�p�����A���N�T���h���܂ɂ���āA���̓I�p�[�����烋�r�[�ɕ���ς���Ă��܂��B1850�N����1870�N�ɂ����Ă͑�p�鍑�����E�̍H��Ƃ��čŐ������}���A�w�p�N�X�E�u���^�j�J�x��������������ł��B ��A�t���J�Ń_�C�������h�E���b�V�����n�܂�1869�N�ȑO�ɂ��ւ�炸�A�Ƃ�ł��Ȃ��S�[�W���X�ȃe�B�A���ł��B�ł��A��Η���ɂȂ�̂ł͂Ȃ��A�Ɠ��̃I���G���^���ȃf�U�C�����A���o�[�g���z�̃f�U�C���E�Z���X�����������܂��ˁB �W���G���[�̏ꍇ�A�f�ނ��n�m���ċ��x�Ȃǂ̍\���v�Z���ł��Ȃ��ƁA��\�ȃf�U�C�����ł��܂���B �D�ꂽ�f�U�C���̃W���G���[��g�ɂ��Ă���B�m���⋳�{�A�Z���X���d�v������Ќ��E�ɉ����āA���ꂪ�����ɃX�e�[�^�X�ƂȂ邩�A�Ȃ�ƂȂ����z������������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B |
1-2-4. 19���I����̏㗬�K���̓���p�W���G���[
 �wLily of the valley�x �wLily of the valley�x�X�Y�����@�u���[�` �C�M���X�@1880�N�� SOLD |
 �w����͂��闃�x �w����͂��闃�x�E�C���O�@�u���[�` �C�M���X�@1880�N�� SOLD |
�@19���I����̏㗬�K���̓���p�̃W���G���[�́A�ǂ���������z���ł��邭�炢���ɖ����Ă��܂��B�������̂Ȃ�1���Ȃ��A�b����t����Ώۂł͂Ȃ��A�����Ƃ̑����̗ǂ���D�݂őI�ԂƂ��������ł��B |
|
 �w�P���g�̐��x �w�P���g�̐��x�P���e�B�b�N�E�X�^�C�� �A�[�c���N���t�c �u���[�` �C�M���X�@1880�N�� SOLD |
 �w���ł݂��ԁx �w���ł݂��ԁx�I�p�[���Z���g�E�G�i�����@�u���[�` �A�����J�@1900�N�� SOLD |
����p�W���G���[�Ƃ͌����Ă��A�㗬�K���̓���p�W���G���[�͑Đ��Œ�������̂ł͂���܂���B���̐g���ɑ��������҂Ƃ��āA���킷����C�i�ɖ������Ȃ܂��ƍs���ɓw�߂܂��B ����̎������ɂƂ��Ă͓K���ȕ��i���ɒ�����Ƃ������A������Ɠ��ʂȎ��ɃR�[�f�B�l�[�g�ł��邭�炢�₩�őf�G�ł���ˁ� ���Ă��邾���łɂ�����L���ȋC�����ɂȂ��A�����ȕł���� |
|
1-2-5. 20���I�����̏㗬�K���̓���p�W���G���[
| �l�O���W�F�E�l�b�N���X�̎��ゲ�Ƃ̕ω� | |||
| ���C�g�E���B�N�g���A�� | �G�h���[�f�B�A�� | �A�[���f�R�O�� | |
 �wRainbow World�x �wRainbow World�x�C�M���X�@1890�N�� SOLD |
 �w�V���v���C�Y�x�X�g�x �w�V���v���C�Y�x�X�g�x�C�M���X�@1910�N�� SOLD |
 �O���[���z���C�g�V�R�^��@�l�b�N���X �O���[���z���C�g�V�R�^��@�l�b�N���X�C�M���X�@1910�N�� SOLD�@ |
 �_�C�������h �l�b�N���X �_�C�������h �l�b�N���X�I�[�X�g���A 1920�N�� SOLD |
�����܂ł��X���Ƃ��Ăł����A20���I�ɓ���A���オ�~��قnj���W���G���[�Ƀf�U�C�����߂Â��Ă������߁A���g�߂ɓ���Ŏg���₷����ۂƂȂ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �l�O���W�F�E�l�b�N���X�͂��̖��̒ʂ�A���풅�ɍ��킹�邽�߂̓���p�̃W���G���[�Ƃ��č���Ă��܂��B�u����Ȃɍ����ʼn₩�ȃW���G���[�����Őg�ɂ��Ă����́H�v�Ƌ����قǂł����A�Â̏㗬�K���͂��̂悤�Ȑl�����������Ƃ�������̐����ؐl�Ƃ������܂��ˁB�v�킸�������o�܂��B |
|||
| ����l�ɃR�[�f�B�l�[�g���₷��20���I�����̃n�C�W���G���[ | ||
| �G�h���[�f�B�A�� | �A�[���f�R�O�� | |
 �wShining White�x �wShining White�x�_�C�������h �l�b�N���X �C�M���X or �I�[�X�g���A�@1910�N�� SOLD |
 �wETERNITY�x �wETERNITY�x�_�C�������h �l�b�N���X �C�M���X�@1920�N�� SOLD |
 �w�V��̃I���S�[�������[�x �w�V��̃I���S�[�������[�x�V�R�^�쁕�T�t�@�C�A �l�b�N���X �C�M���X�@1920�N�� ¥1,230,000-(�ō�10��) |
���ʂɃI�[�_�[���č��ꂽ���̂Ȃ̂�1��1�ɖ��͓I�Ȍ��͂���܂����A���{���p�̉e������������Ă��邱�Ƃ������āA���{�l�ɂ���a���Ȃ����킹����f�U�C����20���I�����̃W���G���[�͑����ł��B ����M�������S�ɗ͂������Ă�����1930�N��A�A�[���f�R����ɂȂ�ƁA��̍����Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�܂��B�R�X�g�J�b�g�̂��߂̊ȑf���ɂ��A�n�C�W���G���[���Â����f�U�C���̂��̂��s�ꂩ��}���ɏ����Ă����܂��B���͏��������A����W���G���[�̂悤�Ȃ܂�Ȃ���ۂƂȂ��Ă����܂��B �G�h���[�f�B�A���ƃA�[���f�R�O���Ɋւ��Ă̓f�U�C���ɑ傫�ȈႢ�͂Ȃ��A�S�[���h�o�b�N���I�[���E�v���`�i�̍�肩�̈Ⴂ���x�ł��B |
||
 |
�㗬�K���̂��߂ɍ��ꂽ�W���G���[�����炱���A�f�ނ������㎿�B ����Ƀf�U�C�����Â��Ă��Ȃ���A���B�N�g���A���قNjX�����Ȃ�����g�������₷���B 20���I�����̉���M���̂��߂̓���p�W���G���[�́A�g���₷���ĂƂĂ��I�X�X���Ȃ�ł��I�� 19���I�㔼���牤��M�����}���ɗ͂������Ă������߁A�����ɂ߂Č��肳���̂���_�ł����E�E�B |
2. �M�����}���ɗ͂�����������̋M�d�ȍō����s�A�X
2-1. ���͑S���قȂ錻��ƌẪC�M���X�M��
2-1-1. ���{�l�ɂ̓C���[�W������̂́w�M���x
�@�M���B���t���̂́A����ł����ɂ��܂��B�������Ȃ����̓I�ɂǂ��������݂Ȃ̂��A��������Ɨ������Ă��鎩�g�͂���܂����H���̎d�����n�߂�ȑO�A���͉��ƂȂ��̃{�������C���[�W��������܂���ł����B ���{�ɂ������O�܂ł͋M�������݂��܂����B ���͏ے��Ƃ��Ă̓V�c�É��Ƌ��ɁA�c���݂̂����݂���`�ɂȂ��Ă��܂����A�@�\�I�ɂ͋M�������݂�������Ƃ͂܂�ňႢ�܂��B�{���A���̂悤�ȃ|�c���ƓƗ������`�ŌN��I�ȑ��݂��������邱�Ƃ͂���܂���B�N��̎��͂ɍ��ʂ̋M�������݂��A����ɂ��̎��͂ɋM�������݂��A�S�̂Ƃ��ď㗬�K�����`�����܂��B ���ꂠ����̂̐Ӗ��Ƃ��Đ�����O�����i������A�w�|�̐V����S�����肵�܂��B |
 ������(���v�N�s�ځF���a970-978�N�A1019�N�܂ł͑���) ������(���v�N�s�ځF���a970-978�N�A1019�N�܂ł͑���) |
���{�͗L���ȁw�����M���x���n�߁A���N�M�������݂��Ă��܂����B ���̂悤�Ȓ��ŁA���[���b�p�ɕ�����M�����x�ʼn^�p���ꂽ�ߑ�̓��{�M���w�ؑ��x�����[���b�p�M���ƃC���[�W�͋߂��ł��B |
 1889/����22�N�́w���@���z���x 1889/����22�N�́w���@���z���x |
�J�����Ė������{������������A1869�i����2�j�N����1947�i���a22�j�N�܂ł̖�78�N�ԑ��݂��܂����B ���̊��Ԃɑ��݂����M���̑�����1,011�ƂƁA�ɂ߂Č����Ă��܂����B ��p�鍑�����E�̒��S�Ƃ��ė͂����������ƁA1870�N�ɕ����푈�ōc��i�|���I��3�����ߗ��ƂȂ������ƂŔp�ʂ���A�t�����X�͋��a���Ɉڍs���ċM���K�����Ȃ��Ȃ������Ƃ�������z������������ʂ�A�ؑ��͌ẪC�M���X�M�����C���[�W����Ɨǂ��ł��B |
|||
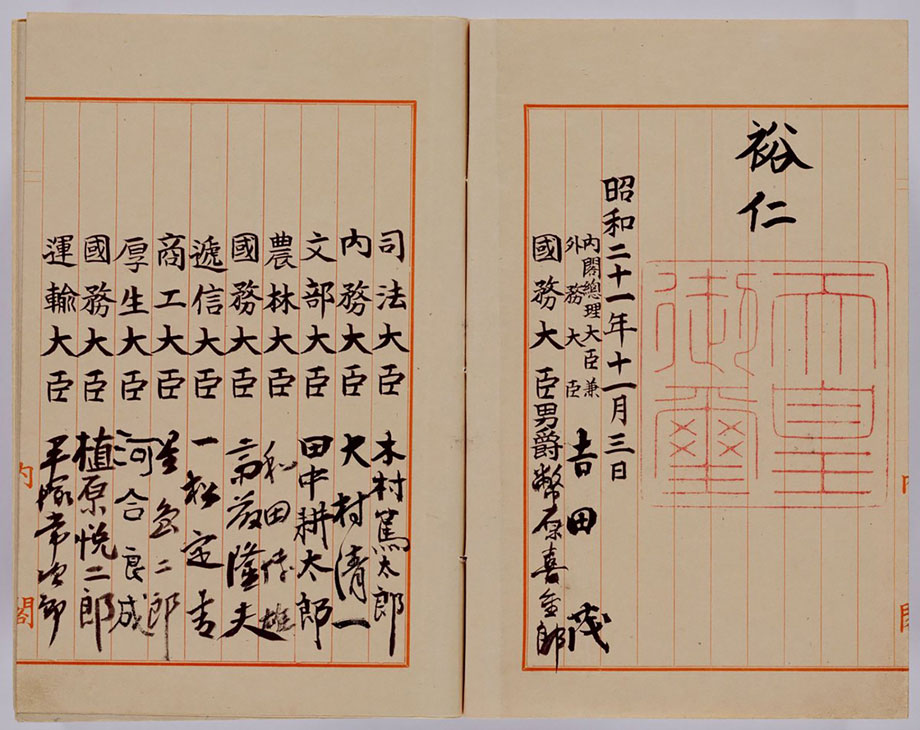 ���{�����@���{�u�䖼�䎣�Ƒ�b�̕����v�i2�Ŗځj�i1946/���a21�N11��3���j ���{�����@���{�u�䖼�䎣�Ƒ�b�̕����v�i2�Ŗځj�i1946/���a21�N11��3���j |
�s����1946�i���a21�j�N11��3���A�@�̉��̕����A�M�����x�̋֎~�A�h�T�ւ̓����t�^�ے���߂����{�����@�����z����܂����B��1947�i���a22�j�N5��3���Ɏ{�s����A�ؑ����x�͔p�~�ƂȂ�܂����B���ǂ��̓����a�����́AGen�����܂��2���O�̂��Ƃł��B |
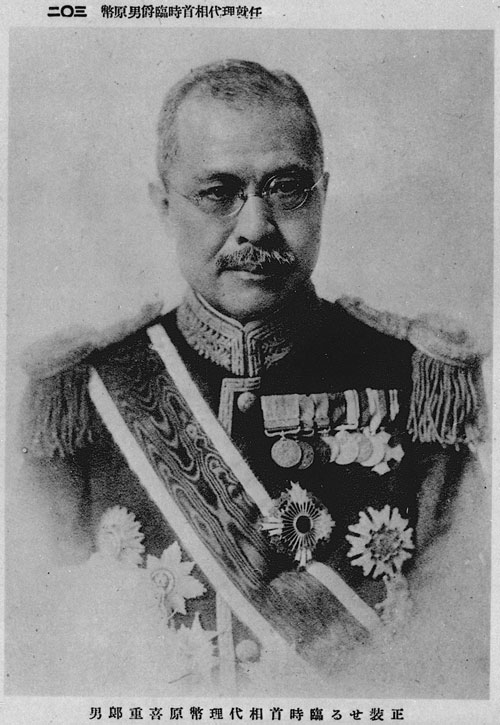 ��������Վ��㗝 ������d�Y �j�݁i1872-1951�N�j ��������Վ��㗝 ������d�Y �j�݁i1872-1951�N�j |
Gen�ł���A�M�������݂�������͖��o���ł��B ���炭�͌��M���i�ؑ��j�A���m���Ȃǂ̌��t���c��A�����������嗬���������܂ł͂�����x�A�M�ˌ������������Ă����ł��傤�B ���̗���Ƌ��ɋL������ۂ���������A����Ɏ���܂��B |
2-1-2. ���ɂ߂ĕ�����ɂ����C�M���X�M��
�@���@�ɂ���ċM�����p�~���ꂽ���{�ƈႢ�A�C�M���X�͌���܂ŋM�����������Ă��܂��B�����͐̂قǎ����Ă��Ȃ������Ƃ��Ă��A��X�����Ă��ċM���Ȃ�ł͂̋��{��}�i�[�A���_�Ȃǂ͂�����������p����Ă�����̂ƁA���ƂȂ��z������Ă������������������܂���B |
 �C�M���X�̋M���@�i2011�N�j �C�M���X�̋M���@�i2011�N�j"House of Lords 2011" ©UK government(9 Septenber 2011, 14:43:34)/OGL 3 |
�������Ȃ������͑S���Ⴂ�܂��B�C�M���X�̏͂ƂĂ�������ɂ����ł��B�ڂɌ�����`�ŋM�����p�~���ꂽ���{�ƈقȂ�A�����Ȃ��悤�Ȍ`�Œ����N���������ė͂��킪��Ă��������炱���ƌ����A����ɂ���Č�����Ă���l����������ƌ�����ł��傤�B |
2-1-3. ���G�ɗv�������ރC�M���X�M���̐���
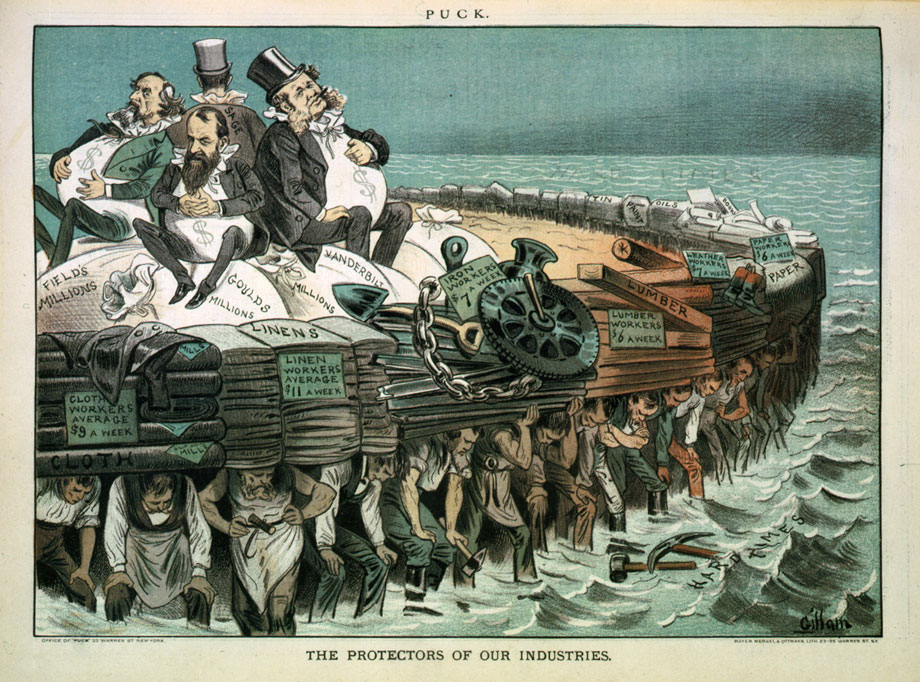 �S�����玑�{�Ƃ������^�ԘJ���ҁi�G���p�b�N�@1883.2.7���f�ڂ̕��h��j �S�����玑�{�Ƃ������^�ԘJ���ҁi�G���p�b�N�@1883.2.7���f�ڂ̕��h��j |
�@�C�M���X�M���̐��ނɂ́A�e��v�������G�ɗ���ł��܂��B�_�Ɗv����Y�Ɗv���ɔ������ω��A�A�����J�̐V���x�T�w�̑䓪�A��ꎟ���E���Ƒ���E���ɔ����݈ʌp���҂̎��S�ȂǁA�l�X�ł��B�S�Ă��ڍׂɂ���������ƂƂ�ł��Ȃ��c��ɂȂ邽�߁A����͋M���̐��Ɠ���ɒ��ڂ��Č��Ă����܂��傤�B |
2-1-4. �M���̐��ƕx�ƌ��͂̕��U
 �w�A���v�X�̗n���Ȃ��X�x �w�A���v�X�̗n���Ȃ��X�x�A���v�X�Y���b�N�N���X�^���@��]��3�ʃt�H�u�V�[�� �C�M���X�@18���I�㔼 ¥1,400,000-�i�ō�10%�j |
�@�嗤�M���ƈقȂ�A�C�M���X�M���͕ʊi������܂��B���̗��R�͋H�����ƁA����ɔ������|�I�ȍ��͂ł��B ����̓C�M���X�M�����O�����h�c�A�[�Ŕ����Ă����A���v�X�̃��b�N�N���X�^���ɁA�����Ō�����i���������Ƃ݂���X�y�V�����E�I�[�_�[�̉�]��3�ʃt�H�u�V�[���ł��B �O�����h�c�A�[�̓��e��A�������琶�܂ꂽ���̂悤�ȕ����邾���ł��A�C�M���X�M���̈��|�I�ȍ��͂��z���ł��܂��B ����ŁA�v���ɂ���Ėłт��t�����X�M����"�n�R�l�ɖт����������x"�̎҂������ƌ����܂��B |
|
18���I�����̃C�M���X�M���ƃt�����X�M���̐�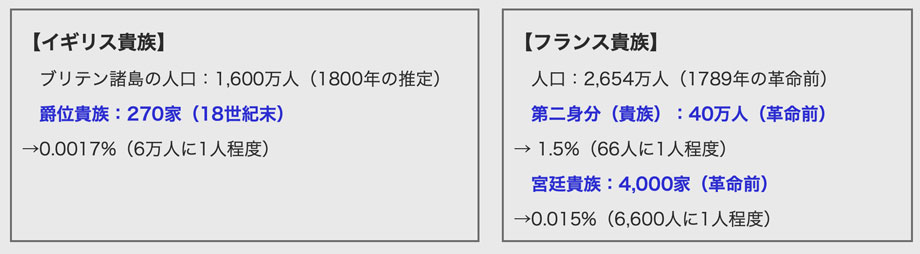 |
�ǂ��������Ƃ��ƌ����A���̐l���̈Ⴂ������ƕ������Ă��܂��B 1789�N�̃t�����X�v���������_�ŁA�t�����X�M����40���l�����܂����B�����̐l�����l������ƁA66�l��1�l�͋M�������܂����B���̐e������M���Ƃ��ĐU�镑���ƍl����A�N���X�ɍŒ�ł�1�l�͋M��������Ƃ��������ł��傤���B������Ă���Ȃ����݂ł͂Ȃ��A������ӂɕ��ʂɂ��鑶�݂ł��B ����A�C�M���X�M����270�Ƃ�������܂���ł����B�l��1,600���l�̒��ł̐��ł�����A�ɂ߂Č���ꂽ�����K���ƌ����܂��B�t�����X�M���̒��ŋ{��M���ɍi���Ă��܂�4,000�ƁA�C�M���X�M����15�{�߂������݂��܂��B �P���ɍ��ƑS�̂̍��Y�������ŁA�ϓ��Ɋ���U��ƍl�����ꍇ�A270�Ƃŕ�����̂ƁA4,000�Ƃŕ�����̂ł͂܂�ō��͂��قȂ�܂��B15�{�̍�������Ƃ����̂́A���Y150���~�̐l�Ǝ��Y10���~�̐l�Ƃ����Ⴂ�ɂȂ�܂��B15���~��1���~�̈Ⴂ�ƌ��Ă��ǂ��ł��B�t�����X�M���̏ꍇ�́A���̑���40���l����"�M��"�Ƃ����g���̐l�����܂����B���̉Ƃ͋M���������ƌ����Ă��A���܂����ʔ������Ƃ����҂ł��Ȃ��̂́A���̂悤�ȋH�����l�̖��������邩��ł��B |
 �A���V�������W�[���h�����G�i1789�N�j �A���V�������W�[���h�����G�i1789�N�j |
����ɂ��Ă������Ȑl���̈Ⴂ�ł���ˁB ���̈Ⴂ�����̐������̂��ƌ����A�����V�X�e���̈Ⴂ�ɂ���Ăł����B ���[���b�p�嗤�M���͌Z��S�����݈ʂ���Y�̌p���Ώۂ��������Ƃɑ��A�C�M���X�M���͒��j�E���q1�l�݂̂ł����B�{�q���s�Ƃ����O��Ԃ�ł��B �^�p����ĊԂ��Ȃ����͂��قǑ傫�ȈႢ�ɂ͂Ȃ�܂��A���オ�~�邲�Ƃɑ傫�ȍ��������Ă���V�X�e���ł��B ����́A�����̃V�X�e�����o�������ߑ���{�l�ɂ͊��o�I�ɑz�����₷����������܂���B |
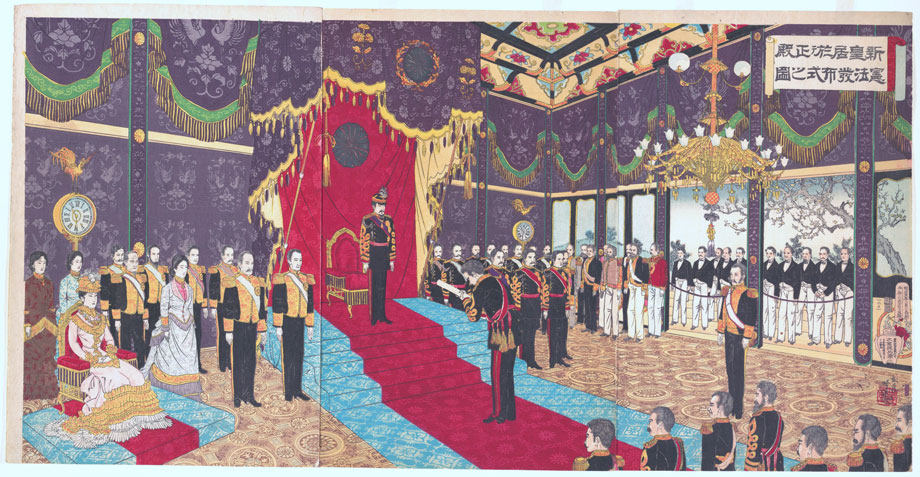 �V�c�����e���a���@���z���V�}�i���B����@1889/����22�N�j �V�c�����e���a���@���z���V�}�i���B����@1889/����22�N�j |
�ߑ�̓��{�ł͉Ɛ��x���^�p����A�Ɠ������s���Ă��܂����B1898�i����31�j�N�ɖ������@���̖��@�ŋK�肳��A1947�N5��2���܂ł̖�49�N�ԁA�ˎ�݂̂��S�Ă̍��Y�𑊑����Ă��܂����B������ƑO�܂ł́u���j�̉ł́`�v�A�Ȃ�Ęb���������肵�܂����ˁB�ˎ�ƂȂ钷�j�݂̂��y�n�Ȃǂ��S�đ������A���̌Z��o���ɂ͎�蕪�͂���܂���B ����͊�{�I�ɂ͔z��҂�1/2�A�q��������1/2���ϓ��ɕ�����Ƃ����`�ɂȂ��Ă��܂��B�����Ȃ��Ă��炨�悻76�N�i2023�N���݁j���o�߂��܂����B��̂ǂ��Ȃ����ł��傤���E�E�B ���j���S�Ă��p�����Ă�������́A�y�n�����̂܂܂̌`�Ŏp����Ă��܂����B76�N���o�߂���Ώ��Ȃ��Ă�2�A3��͑������s���Ă��܂��B�q���̐������Ȃ��Ȃ����Ƃ͌����A��l���q�őS�Ă𑊑�����Ƃ����̂͑命���ł͂Ȃ��ł��傤�B���������ɂ���ēy�n���蔄�肳�ꂽ�肵�čs���܂����B 2005�N�A�\���O�E�I�u�E���V�A�̍����獡�̎s���J�̃A�g���G�ɂ��܂��B���悻18�N�قǂł����A���������ꂾ���̊��Ԃł�Gen�H���A�傫�ȓy�n����������āA2���̉Ƃ��������Ă�ꂽ���������Ă��邻���ł��B�������Ĕ��ꂸ�A�P����}���邽�߂ɕ������Ĕ������P�[�X������Ƒz�����܂����A������ɂ���y�n���������A��������Y�����U�������ł��B �p�C�͌����Ă��܂��B�̂͋�������1�l�A���̑��̑吨�͕��Ȃ��B�����1�l1�l�������ȋK�͂̍��Y���ϓ��Ɏ����Ă���Ƃ��������ł��傤���B���͂��̏��Ȃ��p�C��D�������悤�Ȍ��ۂ��N���Ă��܂��B�w�����x��w�����x�Ȃ�Č��t�܂Ő��܂�Ă��܂��n���ł��ˁB �i���������������ǂ��̂��A�S�����������ׂČ��Ȃ������Ƃ��������ǂ��̂��A����͎��ɂ͕�����܂���B�����A�̂�"���Ă��"�ł���������������Ȃ��ē������ꍇ�A������Y�ƐV���̃L�[�p�[�\���Ƃ��ċ@�\�ł����Ƃ������Ƃ͌����܂��B |
| �C�M���X�̃}�E���g�m���X���݂̎d���p�t�H�u�V�[�� | |
 �w�A���Y���[�Ƃ̔��ݖ�́x �w�A���Y���[�Ƃ̔��ݖ�́x�W���[�W�A�� ���b�h�W���X�p�[ �t�H�u�V�[�� �C�M���X�@19���I���� ��1,230,000-(�ō�10%) |
 |
����ȕx�����L���A�����̐S�z���K�v�Ȃ������C�M���X�M�����������炱���A�d���p�̃t�H�u�V�[���ɂ��D���Ȃ������ӎ����s���n�点�邱�Ƃ��ł��܂��B �@�\��������ǂ�����ł͑z�����ł��Ȃ��قǂ́A�ґ�Ȃ����̂������ł��B |
|
 �A���C��i1960�N�Ɏ��j �y���p�zLOST HERITAGE / ARLEY CASTLE ©lost heritage �A���C��i1960�N�Ɏ��j �y���p�zLOST HERITAGE / ARLEY CASTLE ©lost heritage |
�w�A���Y���[�Ƃ̔��ݖ�́x�̎�����́A�����낱�̂悤�Ȃ���ɏZ��ł����قǂ̐l���ł�������ˁB���ꂾ���̂�����ێ����邾���ł��A���l���̐l�Ԃ₻�̑��ɂ������p���K�v�ƂȂ�܂��B1�x�̏o��ł͂Ȃ��A�����j���O�R�X�g�Ƃ��Ă����Ɣ�p�������葱����킯�ł����A������C�ɂ���K�v���Ȃ��قǍ��͂��������̂��C�M���X�M���ł����B �����A�����Ώۂ����j�E���q�݂̂Őe�����܂߂��{�q����؋����Ȃ��Ƃ����V�X�e���ɂ��A1844�N�ɃA���Y���[�Ƃ͒f�₵�Ă��܂��B�����炱���A�������Ĕ��݉ƗR���̕�����̓��{�ɑ��݂ł���킯�ł��B �������V�X�e���ɂ���āA�C�M���X�M���̋H�����ƍ��́E���͂����N�ێ��ł��Ă����Ƃ������܂��B |
2-1-5. �C�M���X�M���̐�
| �@�C�M���X�M���̐������Ă݂�ƁA19���I�ɓ����Ă����C�ɑ����Ă��܂��B�嗤�M���Ɣ�r����ƁA����قǏ��ω�����悤�ȑ������ɂ͌����Ȃ���������܂���B��������̌���ł��A����قǑ����Ƃ͊����Ȃ����ł��B�������Ȃ�����́A���g���傫���ϗe���Ă��܂��B |
| �N�� | ���P�M�� | �u���e�������̐l�� | |
| ����M���̎��� | �������`16���I | 50�� | �`625���l |
| 17���I�� | 170�� | 925���l | |
| 18���I�� | 270�� | 1,600���l | |
| 1830�N�� | 350�� | �`2,800���l | |
| 1870�N�� | 400�� | 3,400���l | |
| 1885�N | 450�� | �`4,200���l | |
| ��O�̎��� | 1999�N | 750�� | �p�� 5,868���l |
| 2020�N | 814�� | �p�� 6,708���l | |
| 2021�N | 809�� | �p�� 6,728���l | |
| 2023�N | 807�� | �p�� 6,812���l | |
���݂́A���ゲ�Ƃ̎v�f�����f����܂��B�Â�����́A���̌N�傪�n�ʂ�������肳���邱�Ƃ���ȖړI�ł����B�R�����グ���ҁA������O���ȂǂŎ�r�������҂Ȃǂ���ȑΏۂł����B 19���I�㔼�́A���Ȃ�l�q������Ă��܂��B |
|||
2-1-6. �V�����͂��䓪����19���I�㔼
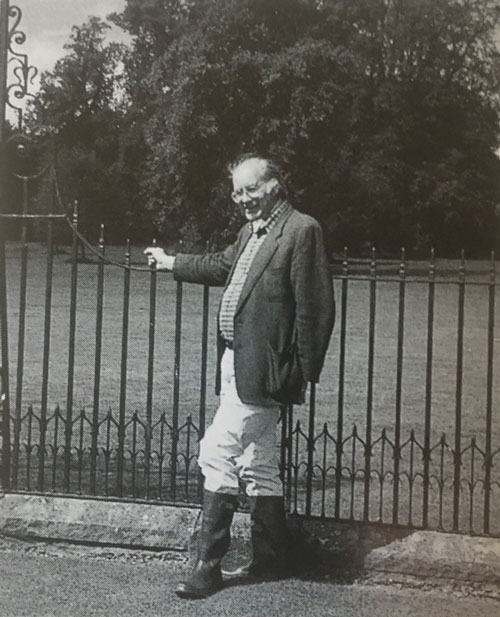 �ΐF�̃S�����C�𒅗p�����n�f�B���g������ �ΐF�̃S�����C�𒅗p�����n�f�B���g�������y���p�z�w�p���M���̕�炵�x�i�c�����O ���@2009�N�j�͏o���[�V�ЁAp.59 |
�@�Y�Ɗv�����O�̎���́A�H���ݏo���y�n�����L���邱�Ƃ����Y�ɂȂ���܂����B �`���I�ɁA�C�M���X�M���͑�n��ł����B ���͗ΐF�̃S�����C�𗚂����n�f�B���g�����݂ł��B���̖̂q���n��_�n�̎��@�Ȃǂ��M���ɂƂ��Ă͑�Ȏd���ŁA�����ɂ��`���I�ȃC�M���X�M���炵���Ȃ܂��ƌ����܂��B |
�������Ȃ���18���I�㔼������̎Y�Ɗv���ɂ��A���傫���ω����܂����B�l���ق��đ�ʐ��Y�E��ʔ̔��ɂ���đ�����҂��o���Y�Ǝ��{�Ƃ��A�����w���琶�܂�܂����B������"�䓪���钆�Y�K��"�ł���A�w�����x��w�V���x�T�w�x�ƌĂ�鑶�݂ł��B ���̏́A�A���e�B�[�N�W���G���[�s��ɂ��@���ɔ��f����Ă��܂��B |
 �w�Y��ȑ��x �w�Y��ȑ��x�u���[�E�M���b�V���G�i�����@�y���_���g �t�����X�H�@18���I����i1780�`1800�N���j SOLD |
�W���G���[��g�ɂ���̂��`���I�ȋM������������19���I�����̃W���[�W�A�����܂ł́A�A���e�B�[�N�W���G���[�s����M���炵�������i�����o�Ă��܂���i���l�C���������߁A���炩�ɂ��������W���[�W�A�����̈����ۂ��U���͑����o����Ă��܂��j�B ���{�ƒm����������Z���X�̗ǂ��f�U�C���A�����ȑf�ށA�O�ꂵ�����̗ǂ��Ȃǂ������ł��B |
 �w���̃����f�B�x
�w���̃����f�B�x�W���[�W�A���@�G�Ձ@�u���[�` �C�M���X�@1826�N SOLD |
�W���[�W�A���E�W���G���[�͖{���ɖ��͂������A�������Љ�����Ƃ���ł��B �ł��A�����͂������s��Ō��邱�Ƃ͂ł��܂���B �����������ʂ�x�ƌ��́A���{�ƒm����Ɛ肵�Ă����{���̋M���͋ɂ߂ď����ł��B �s��̑唼�́A���|�I�����ƂȂ鏎���p�ɍ��ꂽ��������W���G���[�ł��B ����炪�s��ɕ��𗘂����n�߂�̂��~�b�h�E���B�N�g���A���ȍ~�ł��B |
| �~�b�h�E���B�N�g���A���̓T�^�I�Ȑ����W���G���[ | |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
||
�Y�Ɗv���ɂ���đ䓪�������Y�K�������𐬂��A�ߐH�Z����������A�V�������Ƃ��ăW���G���[�Ɏ���o���n�߂��̂��~�b�h�E���B�N�g���A���ƌ����܂��B����܂ŃW���G���[�������Ă��Ȃ��������炱���́A���Ȍ����~�������`����Ă���W���G���[�ł��ˁB ���x�o�ϐ�������o�u�����ɂ����ẮA���{�̈ꕔ�̐����n�D�̏����ɂ̓t�B�b�g������������܂��AGen���������̂悤�ȃZ���X�����{���������Ȃ��n���{�e�I�ȃh���E�W���G���[�͍D���ł͂���܂��A�{���A���{�l�������D�ނ��̂ł��Ȃ��Ǝv���܂��B |
||
| ���C�g�E���B�N�g���A���̏����p�̈����W���G���[ | ||
 |
 |
 |
 |
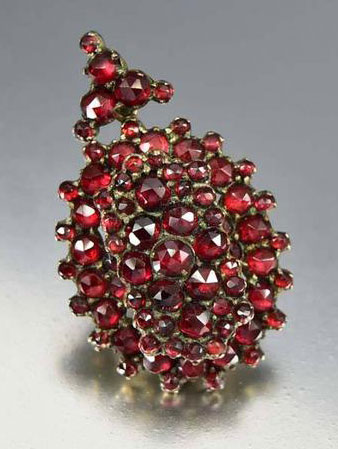 |
 |
���オ�~��ƁA�C�M���X�ł͂���ɏ������W���G���[���悤�ɂȂ�܂��B���ʂ̃A���e�B�[�N�W���G���[�E�V���b�v�Ŏ�舵���Ă���̂́A���̂悤�ȃ��C�g�E���B�N�g���A���̑�O�p�̗ʎY�W���G���[�ł��B������������̌��̂Ȃ��f�U�C���������ł��B����ł�Gen�⎄���猩��ƁA�u������I�I�H�v�Ɗ�����قǍ��l�Ŕ̔�����Ă����肵�܂��B�������獂���A��������㗬�K���̃W���G���[�Ƃ����킯�ł͂Ȃ����Ƃł��i�j |
||
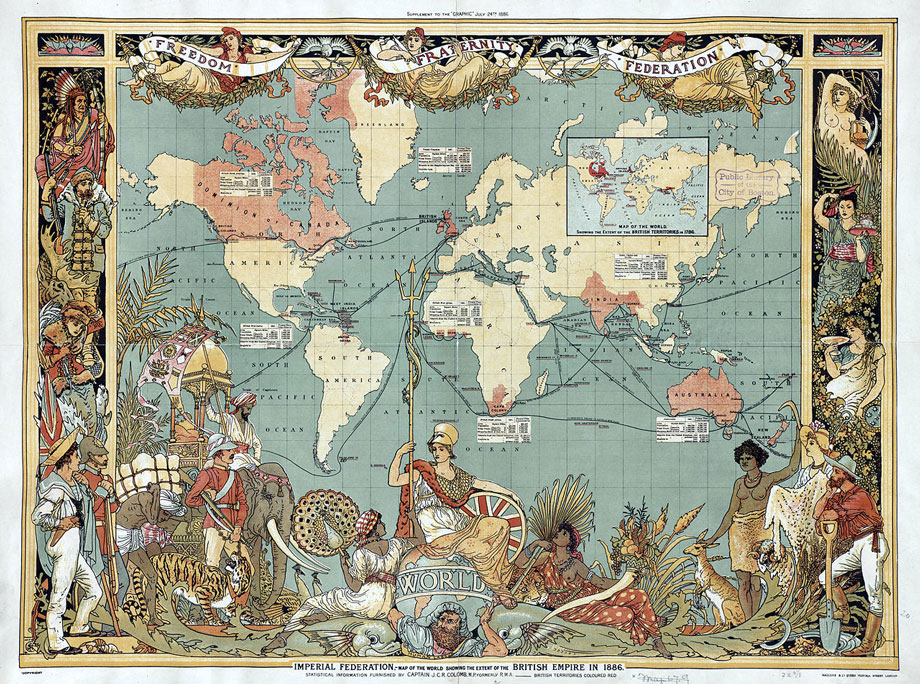 ��p�鍑�i1886�N�j ��p�鍑�i1886�N�j |
���̕ӂ�̃C�M���X�̌o�ϊ����̕ω��́A��p�鍑�����E�̍H��Ƃ��čŐ������}�����w�p�N�X�E�u���^�j�J�x�̎���ƘA�����Ă��z������������ł��傤�BPax Britannica�A�w�C�M���X�̕��a�x���Ӗ����郉�e����ł��B���[�}�鍑�̉������w�p�N�X�E���}�[�i�i���[�}�̕��a�j�x�ɕ�������̂ł��B ��p�鍑�̍Ő�����19���I��������20���I�����܂ł̊��Ԃł����A���Ɂw���E�̍H��x�ƌĂꂽ1850�N������1870�N�����w���ăp�N�X�E�u���^�j�J�ƌ������Ƃ������悤�ł��B�~�b�h�E���B�N�g���A���ɑ������܂��B�C�M���X�͓��ɂ��̎����A�Y�Ɗv���ɂ��씲�����o�ϗ͂ƌR���͂�w�i�ɁA���R�f�Ղ�A���n�����I�݂Ɏg�������Ĕe�����ƂƂ��ĉh���܂����B ���̌�A���C�g�E���B�N�g���A���ɂ����ď����܂ōL���x���s���n��킯�ł��ˁB |
2-1-7. �M���@�ŐV�����͂��䓪����19���I���
 �C�M���X���`���[���Y1���i1600-1649�N�j �C�M���X���`���[���Y1���i1600-1649�N�j |
�@�Â�����͕������グ���ҁA�D�ꂽ������O����r�������҂���ȏ��ݑΏۂł����B �ё��悩����`����Ă���ʂ�A�킢�̎���͒j�炵���������ƁA���ɑ傫�Ȕɉh�������炷���Ƃ��ł���҂��������`�ł����B |
| 19���I����ȍ~�Ɍ��т��グ�ď��݂����C�M���X�M�� | ||
| 1892�N -�Ȋw- |
1896�N -�|�p- |
1931�N -�Ȋw- |
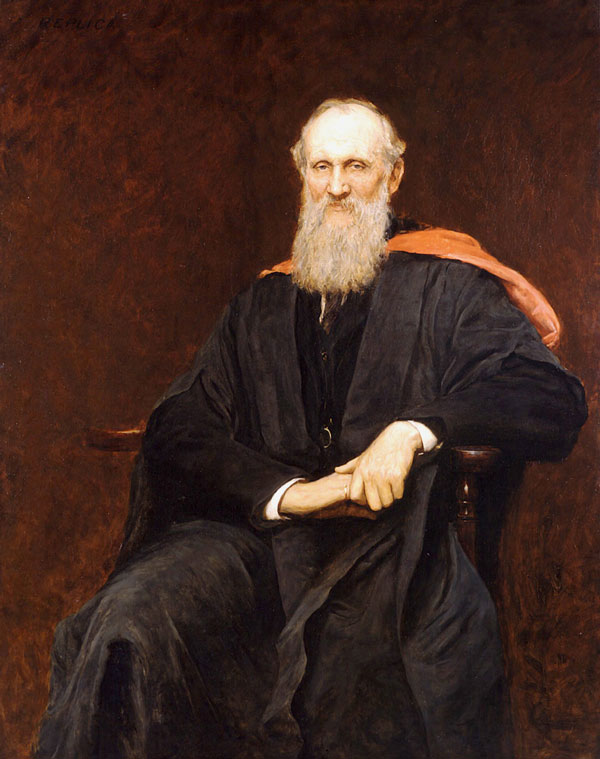 ����P�����B���j�݃E�B���A���E�g���\���i1824-1907�N�j ����P�����B���j�݃E�B���A���E�g���\���i1824-1907�N�j |
 ����X�g���b�g���̃��C�g���j�݃t���f���b�N�E���C�g���i1830-1896�N�j1880�N�̎��摜 ����X�g���b�g���̃��C�g���j�݃t���f���b�N�E���C�g���i1830-1896�N�j1880�N�̎��摜 |
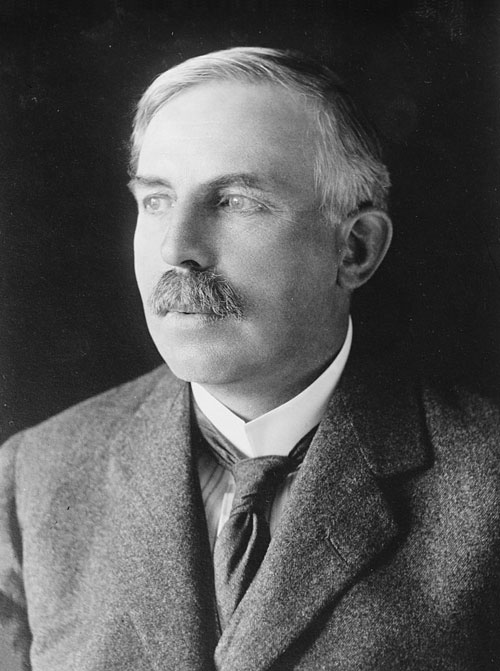 ����l���\���̃��U�t�H�[�h�j�݃A�[�l�X�g�E���U�t�H�[�h�i1871-1937�N�j ����l���\���̃��U�t�H�[�h�j�݃A�[�l�X�g�E���U�t�H�[�h�i1871-1937�N�j |
�ߑ�́A�̂Ƃ͑S���قȂ�^�C�v�̐l�X�����݂���悤�ɂȂ�܂����B�u�ǂ�������M���ɂȂ��̂��H�v�ł��Љ���ʂ�A19���I�㔼����20���I�O���ɂ����Ắw�Ȋw�̎���x�ƂȂ�܂����B���̂��߁A�P�����B���j�݂�l���\���̃��U�t�H�[�h�j�݂̂悤�ɉȊw�̌��тŏ��݂����l���������܂��B�M���ŒZ�L�^�����l���Ƃ��Ă��L���ȃX�g���b�g���̃��C�g���j�݂͌|�p�̌��тł��B ���̂悤�Ɋw�|�Ɋւ�����т̏ꍇ�́A���قǐ�������ׂ��Ɋւ��鋭����S�͊����܂��A19���I�㔼����䓪���n�߂��͎̂�ɋߑ�ɓ����Ėf�Ղ⏤�Ƃō��𐬂������������ł����B���E�̍H��Ƃ��đ�ʐ��Y���A�A���n��������܂����ݍ����ă{���ׂ������V�����͂ł��B�ނ炪�M���ɏ������A�M���@�ŕ��𗘂�����悤�ɂȂ��Ă����܂����B |
||
2-1-8. �M���@���x�z���n�߂��V������
2-1-8-1. ���Ԃ������Ȃ���C�M���X�ŗ͂𑝂������X�`���C���h��
| �}�C�A�[�E�A���V�F���E���[�g�V���g��5�l�̑��q���� | ||
| �� -�h�C�c�̋�s��- |
�O�j -�C�M���X�S��- |
�ܒj -�t�����X�S��- |
 �}�C�A�[�E�A���V�F���E���[�g�V���g�i1744-1812�N�j �}�C�A�[�E�A���V�F���E���[�g�V���g�i1744-1812�N�j |
 �l�C�T���E���C�A�[�E���X�`���C���h�i1777-1836�N�j �l�C�T���E���C�A�[�E���X�`���C���h�i1777-1836�N�j |
 �W���R�u�E�}�C�G�[���E�h�E���`���h�i1792-1868�N�j �W���R�u�E�}�C�G�[���E�h�E���`���h�i1792-1868�N�j |
������₷������Ƃ��ẮA���X�`���C���h�Ƃ�����܂��B�}�C�A�[�E�A���V�F���E���[�g�V���g��5�l�̑��q�����Œm���Ă��܂��B�t�����X�v���ɒ[���鍬��������i�|���I���푈�̎���܂ŁA���[���b�p�e���ɎU����5�l�̑��q�����̘A�g�ɂ���ċ����̍��𐬂��Ă��܂��B �O�j�̃l�C�T���E���C�A�[�E���X�`���C���h���C�M���X�S���ł����B�n�p��1798�N�A21�̎��ł����B�ڏZ��͑@�ۋƂ̒��S�n�}���`�F�X�^�[�ł��B���E�Ő悪���Ďn�܂����Y�Ɗv���ɂ���đ�ʐ��Y�����悤�ɂȂ����Ȑ��i��������ʂɎd����A�t�����X�v���ȗ����ʂ��������ĖȐ��i���������Ă����c���h�C�c�ɑ���A����ȗ��v���グ�܂����B���ԃ}�[�W���ߖ�̂��߁A�����i�̔����t���݂̂Ȃ炸�Ȏ�����F�Ƃɂ�����L���A�Ȏ��ƑS�̂������ɂȂ��Ă����܂����B �܂��ł����͋�s�ƂƂƂ���Ƃ̏o�g�ł�����A���ꂪ�ŏI�ڕW�ł͂���܂���ˁB�₪�ĖȎ��Ƃ̗��v������ɋ��Z�Ƃ���|����悤�ɂȂ�܂����B1804�N�ɂ̓����h���ɈڏZ���A1811�N��N�EM�E���X�`���C���h���T���Y�������A�ב֎�`�f�Ղ̋�s�Ƃɓ]���܂����B �i�|���I���푈�ɂ����Z�p�j�b�N�ɂ���ċ������������ۂ́A1810�N�ɉp���c��ɐݒu���ꂽ�n���ψ���ňӌ����q�ׂ�29�l�̐��Ƃ�1�l�Ƃ��đI��A�u���Ɍ����ȑ嗤�̏��l�v�ŐT�ݐ[���^���Ƃ��ĈÖ�������Ă��܂��B |
||
 ��p��s�Ƃ̃}�C�A�[�E�A���V�F���E���[�g�V���g�ɍ��Y��a����w�b�Z���I��� ��p��s�Ƃ̃}�C�A�[�E�A���V�F���E���[�g�V���g�ɍ��Y��a����w�b�Z���I��� |
5�l�Z��̕��}�C�A�[���������Ƃ����L���Ȍ��t�Ƃ��āA�uInfiltration instead of invasion�i�N���ł͂Ȃ��Z�����j.�v������܂��B ���̎�@�͈�ʐl�Ȃ�Αz�肵�Ȃ��悤�Ȏ��Ԃ͂�������̂́A�N������C�Â���ʂ܂ܕs�t���m���ɏh��𐬏A�ł���A���Ɍ����Ȃ����ł��B ��ʐl�Ȃ�Αz�肵�Ȃ��悤�Ȏ��ԂƂ����̂́A������Ă̑z�肪���C�ōs���邩��ł��B���ʂ͏�肭���������Ƃ������Ŋm�F�������̂ŁA�����������Ă���Ԃ�z�肵�܂��B�ނ�͎��̂悤�Ȗ}�l�Ƃ͈Ⴄ�悤�ł��i�j |
| �C�M���X�̃��X�`���C���h�� | ||
| �n�c -�p���ɈڏZ- |
�q -�����@�c��- |
�� -�����@→�M���@�c��- |
 �l�C�T���E���C�A�[�E���X�`���C���h�i1777-1836�N�j �l�C�T���E���C�A�[�E���X�`���C���h�i1777-1836�N�j |
 ���C�I�l���E�h�E���X�`���C���h�i1808-1879�N�j ���C�I�l���E�h�E���X�`���C���h�i1808-1879�N�j |
 ���ネ�X�`���C���h�j�݃i�T�j�G���E���X�`���C���h�i1840-1915�N�j ���ネ�X�`���C���h�j�݃i�T�j�G���E���X�`���C���h�i1840-1915�N�j |
�u�N���ł͂Ȃ��Z�����B�v 1836�N�Ƀl�C�T������������ƁA��s�Ƃ�27���������j���C�I�l�����p���܂����B�J���X�}�n�Ǝ҂������������o�c�̓X���Ђ́A�ʏ��2��ڂŎ������A3��ڂŒׂ��Ƃ�����ۂ�����܂��B�������Ȃ���A���C�I�l�����ɂ߂ėD�G�������悤�ł��B ���Ƃ��x�z���悤�Ƃ����ꍇ�A�K�v�Ȃ͔̂���ȍ��͂Ɛ����I�Ȍ��͂ł��B���͂͏����������Ă��܂��B�����I�Ȍ��͂͂�����������Δ��������\�ł����A��������ɂ��Ă�������x�̑�������͕K�v�ł��B���̎���́A�C�M���X���x�z����̂͋M���K���ł����B�܂��͋M���@�ւ̐Z����ڎw���܂����B ���l�C�T���͑���4�l�̌Z��Ƌ��ɁA1822�N�ɃI�[�X�g���A�鍑�̃n�v�X�u���N�Ƃ���j�݈ʂƖ�͂����^����Ă��܂����B������p���ł������߁A���C�I�l����1838�N�ɒj�݂̏̍���тт钺���܂����B�����A����͂����܂ł��I�[�X�g���A�̒j�݈ʂł���A�C�M���X�ł͂���܂���B �M���@��ڎw�����[�g�Ƃ��āA�܂����݂��ċM���@�̋c�Ȃ郋�[�g������܂��B�܂��A��ɏ����@�̋c�ȂāA���̌�Ɏ݈ʂċM���@�ɈƑւ����郋�[�g���l�����܂��B�����Ȃ菖�݂���͓̂���ł��B�܂������@��ڎw�����Ƃɂ��܂����B |
||
 �A�C�������h�̃W���K�C���Q�[�i1845-1849�N�j�̒Ǔ��� �A�C�������h�̃W���K�C���Q�[�i1845-1849�N�j�̒Ǔ��� |
�F�X�Ƒf�n������Ă������͂��ł����A�ڗ����̂Ƃ��Ă̓A�C�������h�̃W���K�C���Q�[�ł̋`�������B�ł��B1847�N��800���|���h�B���Ă��܂��B�����@�̋c�Ȃ邽�߂ɂ́A�I����������������̎x�����K�v�ł��B �W���K�C���Q�[�ł͖�100���l���쎀��a�����A�A�C�������h�̐l�X�̓A�����J��J�i�_�ւ̈ڏZ��]�V�Ȃ�����܂����B�A�C�������h�̐l���͏��Ȃ��Ƃ�20�`25%�������A10�`20�������O�ɈڏZ�����Ƃ���܂��B ���{�̐l��1��2,463���l�i2022�N�j�Ŋ��Z����ƁA2,500�`3,100���l�̐l�������ɑ������܂��B�����s�̐l����1,396���l�i2021�N�j�ŁA��s���̑��l����4,434���l�i2020�N�j�ł��B�����s�͊ۂ��Ɛl�����Ȃ��Ȃ�A��s���Ō��Ă����̔����ȏ�̐l�����Ȃ��Ȃ����̂Ɠ��������ł��B 40�l�w���Ȃ�A�N���X��8�`10�l�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂����̂Ɠ����ł��ˁB����قǐ[���Ȏ��Ԃ��ƁA�����Ă���l�ł��瑊������ȏɂ��������Ƃ͑z���ɓ����܂���B �W���K�C���Q�[�͓���1847�N�͏��ł��������������ŁA�w�Í���47�N�iBlack '47�j�x�Ƃ������Ă��܂��B������"���Ă��"���^�C�~���O�ǂ�����𓊓�����A�L���x����ꂽ���Ƃł��傤�B |
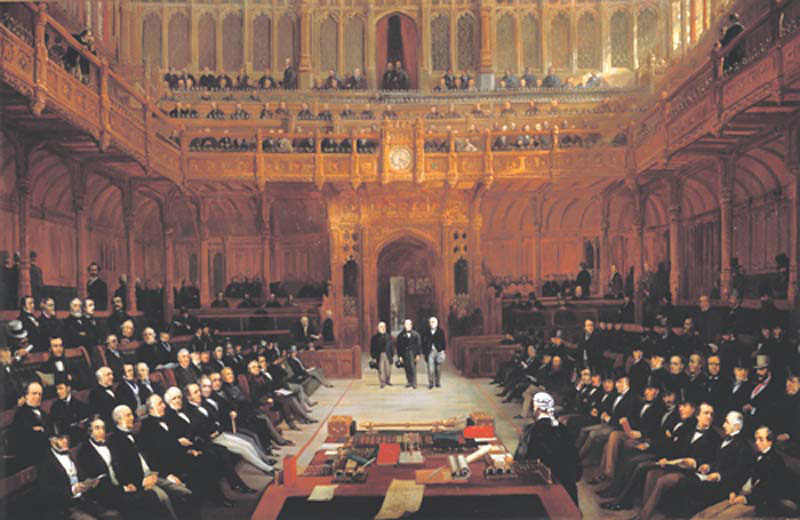 1858�N�ɏ����@�ɏ��o�@���郉�C�I�l���E�h�E���X�`���C���h 1858�N�ɏ����@�ɏ��o�@���郉�C�I�l���E�h�E���X�`���C���h |
���N�A���C�I�l���͋��Z�̒��S�n�V�e�B�E�I�u�E�����h���I���悩��o�n���A���I���ʂ����܂����B�����A���ꂾ���ł͋c���ɂ͂Ȃ�܂���B�L���X�g���k�Ƃ��Đ錾���s���K�v������܂����B���_���l�ł��郉�C�I�l���͂�������݁A�u���E���ōł��x�݁A�ł��d�v�ŁA�ł��m������I����̑�\�҂��c����肷�邱�Ƃ��A���t��̌`���𗝗R�ɋ��ۂ��邱�ƂȂǂł��Ȃ��Ɗm�M���Ă��܂��B�v�Ɖ������Ă��܂����B �����@�́A���_�������̐錾��F�߂ă��_���l�c����F�߂�ׂ��Ƃ��錈�c��ʂ��܂����B�������Ȃ���M���@���ی����A���C�I�l���͋c���ɂȂ邱�Ƃ��ł��܂���ł����B �������A���C�I�l���͊ȒP�ɒ��߂�悤�Ȑl���ł͂���܂���ł����B���ւ��i��ւ��A���Ԃ��������Ă��O�x�߂čs���ΒB���͉\�ł��B |
2-1-8-2. �p���c��ɉ����郆�_�����͂̑䓪
 ����r�[�R���Y�t�B�[���h���݃x���W���~���E�f�B�Y���[���i1804-1881�N�j ����r�[�R���Y�t�B�[���h���݃x���W���~���E�f�B�Y���[���i1804-1881�N�j |
���C�I�l���́A����r�[�R���Y�t�B�[���h���݃x���W���~���E�f�B�Y���[���Ɛe�����Ȃ�܂����B �f�B�Y���[���̓��_���l�ł����A12�ŃC���O�����h������ɉ��@���Ă���A4�x�̗��I���o��1837�N�ɏ����@�c���ƂȂ����l���ł��B �ێ�}���ŏ�w���ɏ��l�߁A�}��ƂȂ���2���ɓn��߂Ă��܂��i�ݔC�F1868�N�A1874-1880�N�j�B |
| ���_���l�̃f�B�Y���[���� | ||
| �c�� -�p���ɈڏZ- |
�� - |
�p���f�B�Y���[�� -�����@→�M���@�c��- |
 ���������l�x���W���~���E�f�B�Y���[���i1730-1816�N�j ���������l�x���W���~���E�f�B�Y���[���i1730-1816�N�j |
 ��ƁE�w�҃A�C�U�b�N�E�f�B�Y���[���i1808-1879�N�j ��ƁE�w�҃A�C�U�b�N�E�f�B�Y���[���i1808-1879�N�j |
 ����r�[�R���Y�t�B�[���h���݃x���W���~���E�f�B�Y���[���i1804-1881�N�j ����r�[�R���Y�t�B�[���h���݃x���W���~���E�f�B�Y���[���i1804-1881�N�j |
�f�B�Y���[���́A�c���̑�ŃC�M���X�ɂ���Ă��܂����B��c�̓X�y�C���̃��_���l�ŁA���F�l�c�B�A�ɈڏZ��ؐl�Ƃ��Đ������Ă��������ł��B�]�c���A�C�U�b�N�͋�s�ƂŁA���j�Ƀ��F�l�c�B�A�ł̋�s�Ƃ��p�����A1748�N�Ɏ��j�������c���x���W���~�����C�M���X�ɈڏZ�����܂����B�����őc���͊��������l�Ƃ��Đ������A���A�C�U�b�N�ɔ���Ȉ�Y���₵�܂����B ��}���A�����_���l�ŁA���ꋤ�ɗT���ł����B���A�C�U�b�N�͒����ȍ�ƂŁA�x���W���~���͗T���ȉƒ�ŕ��w�I���{��g�ɂ��Ȃ���M���q�I�Ɉ�����ƌ����Ă��܂��B ���a���ɋM���ł͂Ȃ��������ƁA���_���l�ł��邱��A�w�����Ȃ����ƂȂǂ�����A��������p���ɂ܂ŏ��l�߂��x���W���~���ɂ́w����オ��ҁx�̃C���[�W�������������ł��B�������Ȃ���A�{�l�͎���̌��Ɍւ�������Ă��܂����B���_���l�͉p���M���Ȃǂ��y���ɌÂ����j�����^�̋M���ł���A����Ɏ��g�̓��_���l�̒��ł��X�y�C���n��"�M��"�ł��邽�߁A�M���̒��̋M���ł���ƑI���ӎ��������Ă����悤�ł��B |
||
 ���B�N�g���A�����̈�Ԃ̒�����������r�[�R���Y�t�B�[���h���݃x���W���~���E�f�B�Y���[���i1877�N���j ���B�N�g���A�����̈�Ԃ̒�����������r�[�R���Y�t�B�[���h���݃x���W���~���E�f�B�Y���[���i1877�N���j |
�x���W���~���E�f�B�Y���[���́A���̒��ōł����B�N�g���A�������璞���������Ƃł��m���Ă��܂��B ����́A�f�B�Y���[���Ɍ������������Ă����v�A���o�[�g���z�̐�����̂��Ƃł��B |
2-1-8-3. �����E�O��ʂŋɂ߂ďd�v�l���������A���o�[�g���z
 �v�����^�W�l�b�g������̃��B�N�g���A�����ƃA���o�[�g���z�i1842�N�j �v�����^�W�l�b�g������̃��B�N�g���A�����ƃA���o�[�g���z�i1842�N�j |
�A���e�B�[�N�W���G���[�����D���ȕ��ɂ́A�₩�ɒ�������"�L���b�L�����ӂ�"�ȎЌ��ɂ݂̂������������������������ł��傤�B ����ǂ��납�A����M���͂��ł����т₩�ȃh���X�𒅂ė������Ƃ���l���Ă����Ƃ��犨�Ⴂ���Ă���������������邩������܂���B ������������HERITAGE��HP�ɂ͋������������A�����܂œǂނ��Ƃ��Ȃ��ł��傤�i�j ����Ȃ킯�ŁA����M���̃A���e�B�[�N�W���G���[�𗝉������łƂĂ���Ȑ����E�O���ɂ��Ă������������܂��B |
 ���B�N�g���A�����i1819-1901�N)19�A1838�N ���B�N�g���A�����i1819-1901�N)19�A1838�N |
�N��Ƃ������ʂȒn�ʂɂ��������B�N�g���A�����́A�����E�O������ɂ߂ďd�v�ȗ���ł����B �ނ��덑�ƂƂ��ẮA�L���b�L�����ӂӂȎЌ���肻����̎d���̕������|�I�ɏd�v�ł��B |
 �����q����̃C�M���X���G�h���[�h7���i1841-1910�N�j5�� �����q����̃C�M���X���G�h���[�h7���i1841-1910�N�j5�� |
����̓��{�͂����L���Ȃ����Ő����ƂɂȂꂽ�肷�邽�߁A�����\�͂�O��\�͂�N�ł��ł���ȒP�Ȃ��̂ƌy������l�����邩������܂���B �������Ȃ�����ۂ͑S�������ł͂���܂���B���Ƃ��˔\����҂ł����Ă��A�l���݈ȏ�̓w�͕͂K�v�s���ł��B ����̂ɁA�������ƂȂ邱�Ƃ��m���Ȏ҂͓O�ꂵ�Ē鉤�w���X�p���^���炳��܂��B ���B�N�g���A�����v�Ȃ̒��j�o�[�e�B�i�G�h���[�h7���j�ւ̋���́A���s�҂ƌ����Ă��ǂ��قǂ̓��e�������Ƃ���\�������قǂł��B |
 �I�[�X�g���A�c�違�n���K���[�����t�����c�E���[�[�t1���i1830-1916�N�j �I�[�X�g���A�c�違�n���K���[�����t�����c�E���[�[�t1���i1830-1916�N�j |
���l�ɁA�����N��Ƃ��đ��ʂ��邱�Ƃ��m�肵�Ă����t�����c�E���[�[�t���A�c��������n�v�X�u���N�Ƃ̓`���ɑ����Ē鉤���炪�{����܂����B �������Ɛ��܂����ł��B 6�ɂ͏T13���ԁA7�ɂ�32���ԁA12�ł�50���Ԃ̂���Ƃ������ނ̎��Ƃ��݂����܂����B 13�̎��ɂ͕��̂��߂��̃X�g���X�ŕa�C�ɂȂ�܂������A��͉Ȗڂ��lj�����A���Ƃ͒�6���Ɏn�܂���9���܂ő����������ł��B �悭�ߘJ�������A�Ђ˂�������Ȃ��������̂ł��B���ꂠ��҂̐ӔC���悭���o���Ă����̂ł��傤�B |
 �Z�A�_�����[�}�c�郈�[�[�t2���̌������ŏj���ŗx��9�̃}���[�E�A���g���l�b�g�i�E�j1765�N �Z�A�_�����[�}�c�郈�[�[�t2���̌������ŏj���ŗx��9�̃}���[�E�A���g���l�b�g�i�E�j1765�N |
�����ŏd�v�Ȃ̂��A�����M���ł��A�j���Ə����ł͖{���͖������قȂ��Ă������Ƃł��B �j���������E�O�����i�����ŁA�����͊w�|�̐U���ƕ����̔��W���d�v�Ȗ����ł����B ������}���[�E�A���g���l�b�g�̗������ƁA�����I�ȋ��{����ɏd�_�I�Ɏd���܂�Ă��܂��B �������N��ƂȂ�ꍇ�A�j���Ə����̗����̋��{���K�v�Ƃ����킯�ł����A�I�[�X�g���A�c�違�n���K���[�����t�����c�E���[�[�t�̗Ⴉ����z���ł���ʂ�A������Ɩ���������߂��܂��B �V�Ɉ�����A���o�����˔\�������Ă��������x�͊�p�ɂ��Ȃ����Ƃ��ł��邩������܂��A��l�ł͖����ł��B�w�͂łǂ��ɂ��Ȃ�̈���Ă��܂��B |
| ���B�N�g���A�����̋���� | |
| ���F8���������A��F�h�C�c�o�g | ����W�F�h�C�c�o�g |
 �ꃔ�B�N�g���A�ƃ��B�N�g���A�����i1824-1825�N��) �ꃔ�B�N�g���A�ƃ��B�N�g���A�����i1824-1825�N��) |
 ���C�[�[�E���[�c�F���i1784-1870�N�j58�� ���C�[�[�E���[�c�F���i1784-1870�N�j58�� |
���Ƃ��˔\�Ɍb�܂ꂸ�Ƃ��A�����͖����ł��A������x�͓w�͂łǂ��ɂ��ł����͂��ł��B�������A���B�N�g���A�����͊��I�ɂ��b�܂�܂���ł����B�C�M���X�����炿�̕��A�P���g���G�h���[�h�E�I�[�K�X�^�X���q�̓��B�N�g���A����������8�����̎��A52�ŖS���Ȃ�܂����B �ꃔ�B�N�g���A�̓h�C�c�i�_�����[�}�鍑�U�N�Z�����R�[�u���N���U�[���t�F���g�����j�o�g�ŁA�p�ꂪ�b���Ȃ��܂܉ł��܂����B���B�N�g���A�����̋���W���C�[�[�E���[�c�F�����h�C�c�o�g�ł����B���R�A�h�C�c�ꂪ���C���̊��ƂȂ�܂��B�l�͂ǂꂾ�������ɊO�����b����悤�ɂȂ��Ă��A�v�l�͕ꍑ��ōs���Ƃ���܂��B��p�鍑�̌N��ɏA���҂Ƃ��āA��������������{�����Ƃ����C���܂�Ŋ������Ȃ����ł��B |
|
| �撣�������B�N�g���A���� | ���{�ɏG�ł��A���o�[�g���z |
 ���B�N�g���A�����i1819-1901�N)11���A1830�N ���B�N�g���A�����i1819-1901�N)11���A1830�N |
 �U�N�Z�����R�[�u���N���S�[�^���q�A���o�[�g�i1819-1861�N�j21���A1840�N�� �U�N�Z�����R�[�u���N���S�[�^���q�A���o�[�g�i1819-1861�N�j21���A1840�N�� |
�����{�l�͐����́w�^�ʖڂȗǂ��q�x�ŁA�����������E���Ĉꐶ�����Ɋ撣��܂����B�������A�˔\�̗L���͕�����܂��������߂��܂����B ���B�N�g���A�����̓h�C�c�o�g�̃A���o�[�g���q�ɍ��ꍞ�݃v���|�[�Y���A1840�N�Ɍ������܂����B�A���o�[�g���z�͌����ڂ̗ǂ������łȂ��A����M���̒��ł��ڂ�������قǂ̋��{�ƍ˔\�������Ă���A�܂��ɗ��z�̉��q�l�������悤�ł��B���̃A���o�[�g���z�͌�����A���g�̍������{�ɔ�ׁA�����̋��{�̂��܂�̐��ɋ������܂����B�N��́A���܂₽���̉����Ƃ͑S�����ꂪ�Ⴂ�܂��B�傢�ɖ�莋���܂����B �A���o�[�g���z�́A������1������W���C�[�[�E���[�c�F���Ƃ݂Ȃ��܂����B���[�c�F���͏�����5�̎�����ƒ닳�t�߁A�ꓯ�R�ɕ���Ă��܂����B�����̌�����͎����Ƃ��Ďd���A�鏑�����߁A�����̗\�Z�⏔�X�̐l�����������Ă��܂����B�A���o�[�g���z�͂��̎d���Ԃ�ɖ��������A���N�ɂ̓��[�c�F���̉�C���l����悤�ɂȂ�܂����B�����͖Ҕ����܂������A����1842�N�ɃA���o�[�g���z�����[�c�F�����{�삩��Ǖ����܂����B ���̕�����������ƁA�h�C�c�o�g�҂�̔e�������ɂ������܂��B���B�N�g���A�����̕������W���h�C�c�l�A�v�A���o�[�g���z���h�C�c�l�ł��B���ہA���B�N�g���A�������A���o�[�g���z�ƌ�������ۂɂ́A�u�h�C�c�l���p��������������Ƃ���ł́H�v�ƌ��O����l�����������悤�ł��B |
|
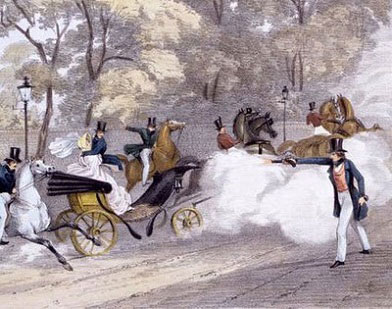 ���B�N�g���A�����ƃA���o�[�g���z��������n�Ԃւ̑_�������i1840�N�j ���B�N�g���A�����ƃA���o�[�g���z��������n�Ԃւ̑_�������i1840�N�j |
�������Ȃ���A���o�[�g���z�́A���B�N�g���A�����ɂƂ��Ė{���ɗ��z�I�ȉ��q�l�ł����B �V�����X�ɑ_�����ꂽ�ۂ́A�A���o�[�g���z���g������ă��B�N�g���A���������܂����B |
 �����o�[���q�݃E�B���A���E�����i1779-1848�N�j65�� �����o�[���q�݃E�B���A���E�����i1779-1848�N�j65�� |
�A���o�[�g���z�͖{���ɗD�G�������悤�ł��B ���B�N�g���A���������ʎ��A�̓����o�[���q�݃E�B���A���E�����ł����B���𑁂��ɖS�����A������O��ʂł̓K�ȑ��k�������Ȃ���������������ɂ����l���ł��B �����o�[���q�݂͑�������A���o�[�g���z�̔�}�ȍ˔\���������A�����ɑ��āu�A���o�[�g���͎��ɓ��̐�邨���ł��B�ǂ����A���o�[�g���̋邱�Ƃ��悭�������Ȃ����܂��悤�ɁB�v�Ɛi�����������ł��B |
 ���B�N�g���A�����̎O�j�A�[�T�[���q�ɑ��蕨������E�F�����g�����݁i1851�N�j ���B�N�g���A�����̎O�j�A�[�T�[���q�ɑ��蕨������E�F�����g�����݁i1851�N�j�w�����O���m�̗�q�x��͂����\�} |
�j���̒��ɂ́u�����I�����I�v�Ǝ��Ȍ����~���ۏo���Ŏ咣����l����萔���݂��܂����A�A���o�[�g���z�͂��������܂���ł����B���̔�}�Ȃ�˔\�����Ȍ����̂��߂ł͂Ȃ��A���B�N�g���A�����̂��߂Ɏg���܂����B���т��グ�Ă��咣���邱�ƂȂ��A���B�N�g���A�����̉��̉��̗͎����ɓO���܂����B���̊G��ł��A�Y�����݂����ȕ`�������������ے����Ă��܂��B |
 �w�C���O�����h�̈̑傳�̔錍�x�i�g�[�}�X�E�W���l�X�E�o�[�J�[�@1863�N���j �w�C���O�����h�̈̑傳�̔錍�x�i�g�[�}�X�E�W���l�X�E�o�[�J�[�@1863�N���j�C���O�����h�̈̑傳�̔錍�����A�t���J�̉��ɐ�������n�����B�N�g���A���� |
������u���A�A���o�[�g�̃I�o�P�H�I�v�ƈ�u���Ⴂ���Ă��܂������Ȃ��炢�A�ڗ������Ђ�����ƕ`����Ă��܂��B |
 ���B�N�g���A������Ɓi1846�N�j���C�����E�R���N�V���� ���B�N�g���A������Ɓi1846�N�j���C�����E�R���N�V���� |
�������Ȃ���A���̕����������ɂ���ă{���{�����������������𗧂Ē����A1850�`1870�N��ɂ����Ắw�p�N�X�E�u���^�j�J�x�Ƃ��Ă��قǂ̑�p�鍑�Ő�����z���グ�A���E���̖���������ƂȂ�1851�N�̃����h��������听���ɓ������̂��A���o�[�g���z�̉e�̊����Ă����ł����B ���B�N�g���A���͍L�����Ƃ��ă��B�N�g���A�������ڗ����܂����A������O���͍˔\�����Ă�����100%�M���ł���v�ɑS�ĔC���A���B�N�g���A�����͓�������w�̎q��Ɍb�܂�A�K���ȉƒ�����\���A���E�̒��S�����p�鍑�̌N��Ƃ��ĈЌ������邱�Ƃ��ł����̂ł��B |
 �A���o�[�g�L�O��̃A���o�[�g�������i1872�N�j �A���o�[�g�L�O��̃A���o�[�g�������i1872�N�j"Close-up of Albert Memorial" ©User:Geographer(10 November 2014)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |
��������B�N�g���A�������g���N�����������Ă��邩�炱���A���o�[�g���z�̎���A�u�v�̈̑傳��m���Ăق����I�v�Ɗ���Ă��̂悤�ȋ����b�L����������킯�ł��B ������ŃA���o�[�g�炵���Ȃ��A���ۂ��̑��̓C�M���X�l�̊��o�I�ɂ��s�]�̂悤�ł����A�����̐[�����Ɗ��ӂ̋C�����͓`����Ă��܂��B�����̓A���o�[�g����]����قNj��{���A�Z���X�ɂ��b�܂�Ȃ������悤�Ȃ̂ŁA�_�T���̂͂��傤���Ȃ��ł������E�E�B ���Ȃ݂ɂ��̑��́A�A���o�[�g���z�̂��A�ő傫�ȍ����ƂȂ��������h�������̗]����ō���������ł��B |
2-1-8-4. �A���o�[�g���z�̑����̐����I�e��
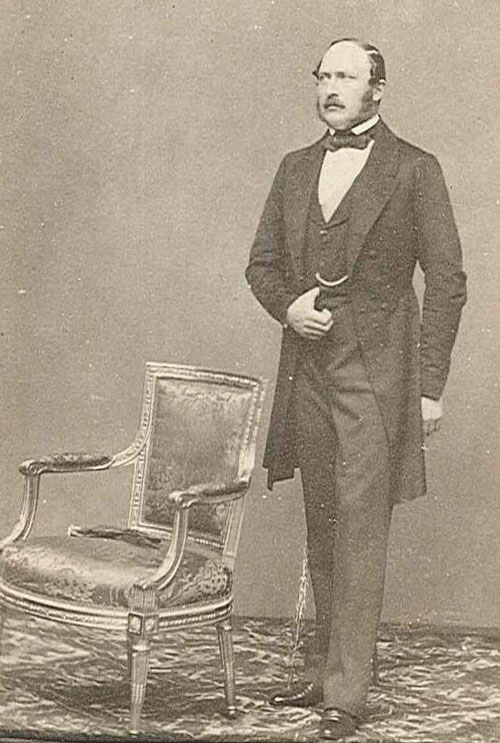 �A���o�[�g���z�i1819-1861�N�j41�� �A���o�[�g���z�i1819-1861�N�j41�� |
�A���o�[�g���z��42�ŋ}�����܂����B ��ɍ����G�h���[�h7���ƂȂ钷�j�o�[�e�B�͂܂�20�B������O���Ŋ���ɂ͌o���l���Ȃ���߂��܂����B �u�A���o�[�g�������ƒ��������Ă���A�C�M���X�̉����͂����ƒ��������Ă������낤�B�v ����������قǁA�C�M���X�ɂƂ��ăA���o�[�g���z�̑����̉e���͎��͑傫�����̂ł����B |
 �������B�b�L�[�ƃ��B�N�g���A�����v�ȁi�E�B���U�[��@1840-1843�N���j �������B�b�L�[�ƃ��B�N�g���A�����v�ȁi�E�B���U�[��@1840-1843�N���j |
�N��Ƃ���"�̂���"�ɂ��Ă������B�N�g���A�����ł����A���ۂ̃��B�N�g���A�����͂����������Ƃ��D��ł����킯�ł͂���܂���ł����B�����Ƃ��āA�撣���ċ��h���Ă��������ł��B �{���̃��B�N�g���A�����͂ƂĂ������炵���A�����Ƃ₩�ɂ��ĉ��q�l�ɗ����Đ����Ă������l�������悤�ł��B�X�|�[�c���\�ŃA�N�e�B�u�A�n���e�B���O�ɂ��o�����Ă������j�̉ŃA���N�T���h���܂ɑ��A�u�������n���e�B���O�Ȃɕt���čs�����̂ł͂���܂���I�v�ƌ����Ă��������ł��B���B�N�g���A�����͉Ƃő�l�����A���҂��Ă��銴���ł��ˁB |
 �����q�܃A���N�T���h���ƃo�X�P�b�g�ɓ�����2�l�̎q�������i1865-1867�N�j �����q�܃A���N�T���h���ƃo�X�P�b�g�ɓ�����2�l�̎q�������i1865-1867�N�j�y�o�T�zRoyal Collection Trust / Queen Alexandra when Princess of Wales (1844-1925) with two children in basket saddles © Her Majesty Queen Elizabeth II 2022 |
�A�N�e�B�u�Ŗ��邢���i�������A���N�T���h���܂́A�Ќ��E�̉ԂƂ��đ�l�C�����������ł��B���{��Z���X���d�v������㗬�K���ɂ̓A���N�T���h���܂̂悤�ȏ����̕����D�܂ꂽ�悤�ł����AGen�����̂悤�ȃA�N�e�B�u�ȏ������D�݂������ł����A�l�ɂ͌����s����������܂����ˁB |
 �I�p�[���̃e�B�A���𒅂������B�N�g���A�����i1819-1901�N�j �I�p�[���̃e�B�A���𒅂������B�N�g���A�����i1819-1901�N�j |
���B�N�g���A�����͉��������A���o�[�g���z�ɗ��肫��ł����B �t�@�b�V�����Ɋւ��Ă������������悤�ł��B�u���͂��ꂪ�D���I�v�ƌ����悤�ȁA�m�ł����Ί��o����I�Z���X�͎����Ă��Ȃ������悤�ł��B �A���o�[�g���z�̓I�p�[�����D���ł����B ���̂��߁A���B�N�g���A�������D��ŕp�ɂɃI�p�[���̃W���G���[��g�ɒ����Ă��܂����B |
|
 |
���B�N�g���A�����̓I�p�[�����D���������Ƃ���܂����A���ۂ̂Ƃ���́u�A���o�[�g���z���D���Ȃ��̂��D���I�v�ƌ����̂����B�N�g���A�����������悤�ł��B |
|
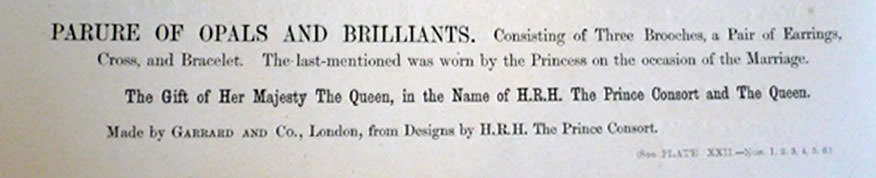 ���B�N�g���A��������A���N�T���h���܂ւ̃E�F�f�B���O�E�M�t�g�i1863�N�j ���B�N�g���A��������A���N�T���h���܂ւ̃E�F�f�B���O�E�M�t�g�i1863�N�j |
||
 �I�p�[�����Z�b�g���ꂽ�I���W�i���̃I���G���^���E�T�[�N���b�g�E�e�B�A���𒅂������B�N�g���A�����i�A���o�[�g���z�ɂ��f�U�C���@1853�N�j �I�p�[�����Z�b�g���ꂽ�I���W�i���̃I���G���^���E�T�[�N���b�g�E�e�B�A���𒅂������B�N�g���A�����i�A���o�[�g���z�ɂ��f�U�C���@1853�N�j |
�u���Ȃ��F�ɐ��܂肽���B�v �A���o�[�g���z�������l��������A�ȒP�Ɉ��p���ꂻ���ł��ˁB���ۂ͂����ł͂Ȃ��A�C�M���X�̂��߂ɐs�����Ă��ꂽ�̂ō����h���܂����B �v�w����1819�N���܂�A�����N�ł����B�������܂��Ⴉ�������炱���A�܂���42�ŕv�������Ȃ�đz���������A�v�ɑS�Ă𗊂肫���Ă����ł��傤�B �o�����܂Ƃ��ɂȂ��A1�l�ł͉����ł����A�܂Ƃ��ɐ������Ă⌈��������Ȃ��̂͊m���ł��B�A���o�[�g���z�S����́A���ƂƂ��Ă̐�]�I�ȏ����z������������Ǝv���܂��B |
|
2-1-8-5. �A���o�[�g���z������̐��E�ɂ�����f�B�Y���[���̑䓪
 ���B�N�g���A�����̈�Ԃ̒�����������r�[�R���Y�t�B�[���h���݃x���W���~���E�f�B�Y���[���i1877�N���j ���B�N�g���A�����̈�Ԃ̒�����������r�[�R���Y�t�B�[���h���݃x���W���~���E�f�B�Y���[���i1877�N���j |
��ɂ��Љ���ʂ�A���̒��ōł����B�N�g���A�������璞�������̂����_���l�̃x���W���~���E�f�B�Y���[���ł����B �A���o�[�g���z������̂��Ƃł����A���͉��z�̓f�B�Y���[���Ɍ������������Ă��܂����B |
| �����I�� | |
| ���R�f�Վ�` | �ی�f�Վ�` |
 �A���o�[�g���z�i1819-1861�N�j �A���o�[�g���z�i1819-1861�N�j |
 ����r�[�R���Y�t�B�[���h���݃x���W���~���E�f�B�Y���[���i1804-1881�N�j1852�N�A47�� ����r�[�R���Y�t�B�[���h���݃x���W���~���E�f�B�Y���[���i1804-1881�N�j1852�N�A47�� |
�����I�Η������̗��R�ł��B�ڍׂ͂����ł͊������܂����A�A���o�[�g���z�����R�f�Վ�`���������Ƃɑ��A�f�B�Y���[�����ی�f�Վ�`���������Ƃ��w�i�ɂ���܂��B�ی�f�Քh���u�h�C�c�l�̉��������R�f�Քh�ƌ������āA�C�M���X�̔_�Ɨ������h�C�c�ɔ��������Ƃ��Ă���I�v�Ɖ����ᔻ���s���A�ی�f�Չ^���̐擪�ɗ����Ă����f�B�Y���[���ɃA���o�[�g���z�͌�����������Ă��܂����B �ی�f�Վ�`�����ɂȂ�������Ȃ��A���o�[�g���z�̓f�B�Y���[����s�M���A������������Ă��������ŁA���ɂ��F�X�ȗ��R����������������܂���B ���R�Ȃ���A���o�[�g���z���D���Ȃ��̂��D���A�A���o�[�g���z�������Ȏ҂������ȃ��B�N�g���A�������A�f�B�Y���[���ɂ͌�����������Ă��܂����B �������ӂ̂܂܂ɑ���̂̓`���������ł��ˁiT T�j �A���o�[�g���z�Ɏ��s���ċC�ɓ�����A��������C�ɓ�����̂Ɠ��`�ł��B�ǂ���ʂ��Ƃ����悤�Ƃ���y���������Ƃł��傤�B�����A�A���o�[�g���z�̓C�M���X�ɂƂ��Đ��������Ƃ����悤�Ƃ��钴�^�ʖڂȐl��������ɁA���Ȃ�̐�҂ł�����܂����B�ǂ���ʊ�݂͌�������Ă��܂����߁A��肢�邾���ł͛@�v�͏�肭�����Ȃ����ɂ������z�����܂��B |
|
 ��ʂ�~�����郔�B�N�g���A�����̕��h��i�p���`�@1876�N4��15�����j�C���h�l�̊i�D����������r�[�R���Y�t�B�[���h���݃x���W���~���E�f�B�Y���[�����C���h�銥�Ɖp���������������Ă���l�q ��ʂ�~�����郔�B�N�g���A�����̕��h��i�p���`�@1876�N4��15�����j�C���h�l�̊i�D����������r�[�R���Y�t�B�[���h���݃x���W���~���E�f�B�Y���[�����C���h�銥�Ɖp���������������Ă���l�q |
�A���o�[�g���z�������Ȃ��Ȃ�A���B�N�g���A�����͂�����ł����邱�Ƃ��ł���ł��傤�B �ň��Ƃ��������łȂ����������S�Ă𗊂���Ă����v���}������A���̎�����S�ɂ����ނ̂͗e�Ղł��B �f�B�Y���[���͐S��͂ނ̂����ӂ������悤�ŁA���ɏ�������͂�����K�w����l�C�������������ł��B �f�B�Y���[���͎��̂悤�ɋL�q���Ă��܂��B �u���݂͂ȋ��h�S�����B�j�̒��ɂ͋��h�S��S�������Ȃ��҂����邪�A���h�S���������j�̋��h�S�́A���̋��h�S�ł͋y�т����Ȃ��قnj������B�v ����Ȓj�̋��h�S�����f�B�Y���[���ɂƂ��āA���̏����ȋ��h�S�����Ďx�z���A�ӂ̂܂܂ɑ���̂͂��Ƃ��ȒP�Ȃ��Ƃ�������������܂���B |
 ���B�N�g���A���������ʂ̓��ɏ��߂ĊJ���������@��c�i1838�N�j ���B�N�g���A���������ʂ̓��ɏ��߂ĊJ���������@��c�i1838�N�j |
���B�N�g���A������18�ő��ʂ������A�P���W���g���{�a�ōŏ��̐����@��c���J����܂����B���̎��A�����ږ⊯�����h�n�[�X�g�j�݂̂����Ƃ��āA32�������f�B�Y���[�������s���܂����B ��c���I���������h�n�[�X�g�j�݂́A�f�B�Y���[���ɂ��̎��̌��i��b���܂����B��l�̏��������E�ҁA�����A�����Ƃ����̐^��I�R�ƕ����A�ʍ��ɍ�����i�B�C�M���X���ōł����Ђ���j�������A��l�̏����ɋR�m�̐������������i�B ���̌��i���v���`���ăf�B�Y���[���͓��������A���̓������g�������̑O���삢�Ă��̎�ɃL�X�����A�R�m�̒�������������Ɗ���������ł��B |
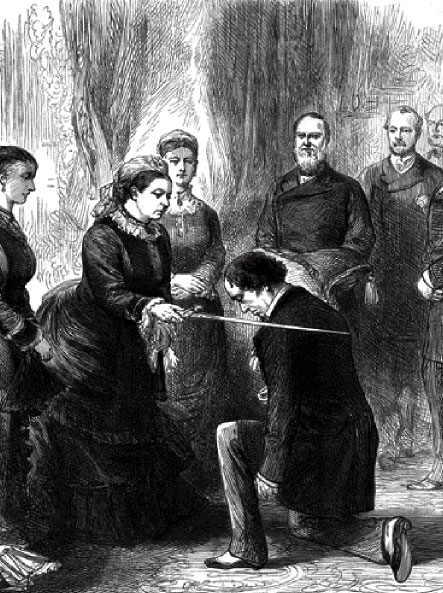 ���B�N�g���A��������K�[�^�[�M�͂����^����鏉��r�[�R���Y�t�B�[���h���݃x���W���~���E�f�B�Y���[���i1878�N�j ���B�N�g���A��������K�[�^�[�M�͂����^����鏉��r�[�R���Y�t�B�[���h���݃x���W���~���E�f�B�Y���[���i1878�N�j |
����͎������܂����B �����̒��������f�B�Y���[����1876�N��2�݈̎ʂ����݂��܂����B ������1878�N�ɂ��K�[�^�[�M�������^����܂����B �n�݂�1348�N�A�����������b���̌M�ݎm�͏펞24���܂łƐ��������A�C���O�����h�̍ō��M�͂ł��ˁB |
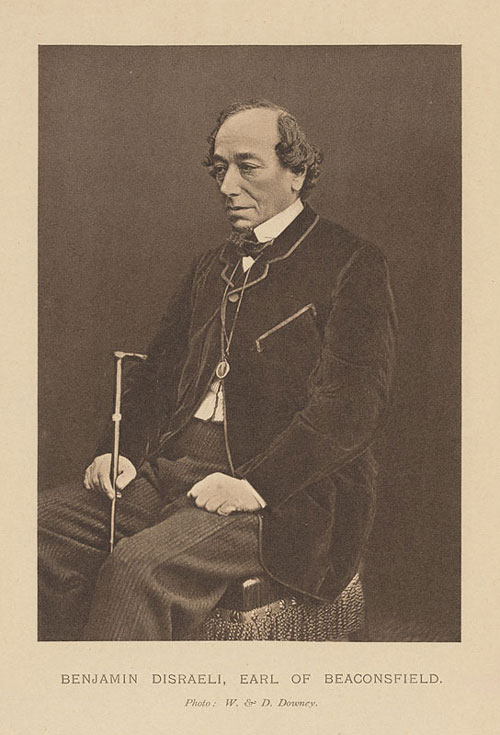 ����r�[�R���Y�t�B�[���h���݃x���W���~���E�f�B�Y���[���i1804-1881�N�j ����r�[�R���Y�t�B�[���h���݃x���W���~���E�f�B�Y���[���i1804-1881�N�j |
�f�B�Y���[���̓A���o�[�g���z���S���Ȃ�����A�A���o�[�g�����̐擪�ɗ����A�A���o�[�g���z�̐l�i��J�ߏ̂��鉉�����s���Ȃǂ��ă��B�N�g���A�����̐S��݂͂܂����B �{���̏��͕�����悤������܂��A��������S�Ƃƌ������A�ŏ����炻�̋C���X�ƌ�����ۂ��`����Ă��܂��ˁB �h�{��Ԃ��q����Ԃ��C�M���X�ōł��b�܂�Ă���͂��̉p�������ɉ����āA�A���o�[�g���z�̂��܂�ɂ��������鎀�́A�łȂǂɂ��ÎE�����������Ƌ^���Ă��܂��܂��B �A���o�[�g���z�̉e���������Ȃ������B�N�g���A�����́A����Ƀf�B�Y���[���ɍD�ӂ���悤�ɂȂ��Ă����܂����B |
 ����r�[�R���Y�t�B�[���h���݃x���W���~���E�f�B�Y���[���i1804-1881�N�j ����r�[�R���Y�t�B�[���h���݃x���W���~���E�f�B�Y���[���i1804-1881�N�j |
���������ӂłȂ��Ă��A�N��Ƃ�������ɂ��郔�B�N�g���A�����͐���������邱�Ƃ͂ł��܂���B�����ŒN���𗊂�ɂ���͕̂K�R�ł��B 1861�N�ɃA���o�[�g���z���S���Ȃ�܂������A1866�N�̑�O���_�[�r�[���ݓ��t�̍��ɂ́A���B�N�g���A�����͊��S�Ƀf�B�Y���[���ɍD������悤�ɂȂ��Ă��������ł��B �f�B�Y���[������C�̎ɂȂ��2�l�̐e�����͑����A1868�N�t�����烔�B�N�g���A�����͎��炪�E�ԑ����f�B�Y���[���ɑ���A�f�B�Y���[���͂��̂���Ɏ����̏����𑗂�Ƃ����ԕ��ɂȂ��Ă��܂����B |
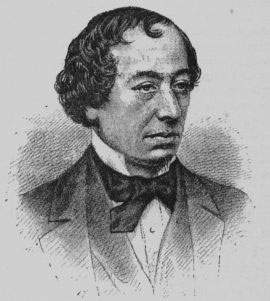 �x���W���~���E�f�B�Y���[���i1804-1881�N�j �x���W���~���E�f�B�Y���[���i1804-1881�N�j |
��S�Ƃ̃f�B�Y���[���͈Ⴄ��������܂��A���B�N�g���A�����̕��͊��S�ɗ��ɗ����Ă��銴���ł��ˁB �A���o�[�g���z���ň��̐l���������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��ł��傤����ǁA��{�I�ɂ͒j���ɗ��肽���A����Ȃ��Ɛ����Ă����Ȃ������������̂�������܂���B |
 �����@�v�[���̐��W���[�W�E�z�[���̃f�B�Y���[���� �����@�v�[���̐��W���[�W�E�z�[���̃f�B�Y���[����"Earl of Beaconsfield statue, Liverpool (1)" ©Reptonix free Creative Commons licensed photos(18 March 2012)/Adapted/CC BY 3.0 |
�f�B�Y���[����1881�N�A76�ŗ������܂����B ���B�N�g���A�����̔߂��݂͐[���A�]������ۂ̓V���b�N�̂��܂肵�炭���������Ȃ����������ł��B �������Ă��܂������A�f�B�Y���[���{�l�̈⌾�ɂ���ăq���[�G���f���̐��}�C�P���y�уI�[���E�G���W�F���Y����ő��V���s���܂����B ���B�N�g���A�����͑��V�ւ̎Q������]���܂������A�����͌N�傪�b���̑��V�ɎQ�邱�Ƃ͋֎~����Ă������߁A���Ԃ��Ԓf�O���܂����B ����ɕ�Q�����]���܂����B |
 ���B�N�g���A�����ɂ��f�B�Y���[���L�O��i1882�N�j ���B�N�g���A�����ɂ��f�B�Y���[���L�O��i1882�N�j"St Michael and All Angels 20080726-13" ©Hans A. Rosbach(26 February 2008)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |
���B�N�g���A�����̓q���[�G���f���ɒ����ƁA�f�B�Y���[�����q���[�G���f���ōŌ�ɕ�������������Ă��狳��Ɍ������������ł��B �@��Ԃ�������̊��̏�ɁA����̉ԗւ������܂����B �܂��A����Ɏ��g�̑z�������嗝�̋L�O���ݒu�����܂����B |
 �v�������[�Y "Prolecno cvece 3" ©Pokrajac(28 February 2007)/Adapted/CC BY-SA 3.0 �v�������[�Y "Prolecno cvece 3" ©Pokrajac(28 February 2007)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |
�f�B�Y���[���̓v�������[�Y���D�������������ŁA���B�N�g���A�����͑��V�̍ۂɃv�������[�Y�𑗂�܂����B����ɂ��A�����Ă��܂��B |
 �v�������[�Y�E�f�C�ŏ��������f�B�Y���[���L�O��i1886�N�j �v�������[�Y�E�f�C�ŏ��������f�B�Y���[���L�O��i1886�N�j |
�f�B�Y���[����2�x�ڂ̖����ƂȂ�1883�N4��19���A���{���ƎO����ł����A�f�B�Y���[�����̏��������s���܂����B ��������������ɁA���N4��19���Ƀv�������[�Y���������蒅�p�����肷��w�v�������[�Y�E�f�C�x�̏K�����C�M���X�ɍL�܂�܂����B |
 �v�������[�Y�E�f�C�i�t�����N�E�u�������[�@1885�N�j �v�������[�Y�E�f�C�i�t�����N�E�u�������[�@1885�N�j |
��ꎟ���E��풆�Ƀf�B�Y���[�����ւ̃v�������[�Y�̏���t�����ꎞ���~���ꂽ���ƂŁA���̏K���͐��ނ��Ă��܂��܂������A����܂ł͍����I�ȃC�x���g�����������ł��B |
| ���B�N�g���A�����̒��������j���̑� | |
 �A���o�[�g�L�O��̃A���o�[�g�������i1872�N�j �A���o�[�g�L�O��̃A���o�[�g�������i1872�N�j"Close-up of Albert Memorial" ©User:Geographer(10 November 2014)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |
 �����h���E�p�[�������g�̃f�B�Y���[�����i1883�N�j �����h���E�p�[�������g�̃f�B�Y���[�����i1883�N�j"Benjamin Disraeli monument" ©Tbmurray(24 February 2012)/Adapted/CC BY 3.0 |
���N����ȃC�x���g���Â��悤�ɂȂ������ƂŃf�B�Y���[���͎���A�}�h���������I�p�Y�ɏ����������ł��B���X�Ƃ��Љ�܂������A���lj����������������̂��ƌ����ƁA����قǃ��B�N�g���A�����̒������������Ƃ������Ƃ������Ƃł��B �ǂ��ł��ǂ��ł����A����ς葜�ɂ͋����b�L�͂��Ȃ������ǂ��ƌl�I�ɂ͊����܂����i�j ���Ȃ݂Ƀf�B�Y���[���̐����ƂƂ��Ă̌��т͉����ƌ����ƁA�C�M���X�̒鍑��`�̖����J���������ƂƂ��ĕ]������Ă��܂��B |
|
2-1-8-6. ���C�I�l���E�h�E���X�`���C���h�̐��E�Q��
 ���C�I�l���E�h�E���X�`���C���h�i1808-1879�N�j ���C�I�l���E�h�E���X�`���C���h�i1808-1879�N�j |
���āA���C�I�l���E�h�E���X�`���C���h�ɘb��߂��܂��傤�B 1847�N�ɏ����@�̑I���ɓ��I�������̂́A���_�����ł̐鐾���F�߂��Ȃ��������ߋc���ɂ͂Ȃ�܂���ł����B �f�B�Y���[���̂悤�ɃL���X�g���ɉ��@����Ƃ�����i���l�����܂����A�c���ɂȂ邱�Ƃ��̂��̂����A���_�����̃��_���l�Ƃ��ċc���ɂȂ邱�Ƃ��d�v�������悤�ł��B ������������ׂ��A�s�͂��܂����B�Ƃ͌����Ă��A�����w�͂�������������K��������������Ƃ������̂ł͂���܂���B |
�咣���������āA�����U���ΒN���������Ă����A�N��������Ă����Ƃ��������͐�͂��ł��B �����������́A���Ԃ��������Ă��������ĊO�x�߂Ă����̂������Ȏ�i�ł��B���̂��߂̏���ȃJ�l�������Ă��܂��B |
| ���ӂ̒��ƂȂ������_���l | |
 ���C�I�l���E�h�E���X�`���C���h�i1808-1879�N�j ���C�I�l���E�h�E���X�`���C���h�i1808-1879�N�j |
 ����r�[�R���Y�t�B�[���h���݃x���W���~���E�f�B�Y���[���i1804-1881�N�j1852�N�A47�� ����r�[�R���Y�t�B�[���h���݃x���W���~���E�f�B�Y���[���i1804-1881�N�j1852�N�A47�� |
���ǂ̂悤�ɋ߂Â��Ă��������͒肩�ł͂���܂��A���C�I�l���͐����Ƃ̒��ł��������_���l�������f�B�Y���[���ƂƂ�킯�e�������܂����B�f�B�Y���[���͖��T�̂悤�ɁA�T���ɂ̓s�J�f���[�̃��C�I�l���@�Ńf�B�i�[�����ꏏ���Ă��������ł��B���ꂾ���̕p�x�ł���A����̏�L�⍡��̍���ȂǁA���Ȃ薧�ɘA�g�����������ł���ł��傤�B 1847�N�A���C�I�l�����c�Ȃ��Ȃ��������Ƃ��A�����@�Ƀ��_�����̐鐾���F�߂���悤�C������Ă��A�z�C�b�O�}�̎w���҃W�����E���b�Z���������o����܂����B�f�B�Y���[���͂���Ɏ^�����A�L���X�g����"���_�����̊����`"�ł���A�u�ނ�̃��_������M���Ȃ��̂ł���A���Ȃ��̃L���X�g���͂ǂ��ɂ���̂��H�v�Ɖ������܂����B�L���X�g���ɉ����鋌�������T�Ƃ���̂����_�����ł��B �����@�ňӌ��͕�����܂����B���b�Z�����͐����I�x����������ɕX��}���Ă���Ƙ��߂����ꂽ��������悤�ł��B�����Ƃւ̘d�G�͌Í������A���邠��b�ł͂���܂��ˁB���ǂ��̖@�Ă͔ی��ɏI���܂����B |
|
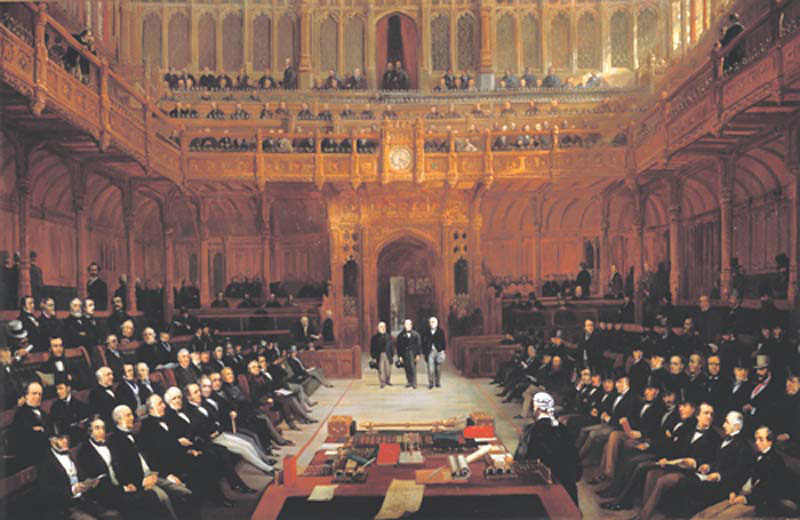 1858�N�ɏ����@�ɏ��o�@���郉�C�I�l���E�h�E���X�`���C���h 1858�N�ɏ����@�ɏ��o�@���郉�C�I�l���E�h�E���X�`���C���h |
�������Ȃ��烉�C�I�l���͒��߂邱�ƂȂ��I���̂��тɏo�n���A���I�𑱂��܂����B���̊Ԃ����𑱂����ł��傤�B���I�̂��сA���_�����鐾��F�߂�ׂ��Ƃ������c����o����܂������A�M���@�Ŕی����ꑱ���܂����B 1858�N�A�鐾�����͏����@�ƋM���@�ł��ꂼ��Ǝ��ɒ�߂�Ƃ����@�Ă�������A�����@�Ń��_�����̐鐾���F�߂���悤�ɂȂ�܂����B ��C�Ƀ_���Ȃ�Έꕔ����B��O��F�߂�������A�Ȃ������I�ɑS�Ă�F�߂�����B���̊�{�ł�����܂��ˁB ��������11�N�Ԃ̒��킪����A�����@�̋c�Ȋl���ɐ������܂����B���R�Ȃ��獑�⏎����̂��߂Ɏ����ɐ����Ƃ�������͖ѓ��Ȃ��A�o�@���邱�Ƃ͖w�ǂȂ��A�c��ʼn������s�����Ƃ���x���Ȃ����������ł��B����͑��|����ɉ߂����A����Ȃ��Ƃ�莟�͋M���@�ւ̐Z���ł��B�ŏI�I�ɂ͐��E�x�z���ڕW�ł�����A��p�鍑�̎x�z��ڎw���˂Ȃ�܂���B |
2-1-8-7. ���C�I�l���E�h�E���X�`���C���h�̋M���@�ւ̒���
���C�I�l���̋M���@��ڎw�������B 1847�N�ɏ����I�B |
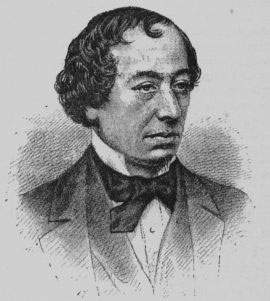 �x���W���~���E�f�B�Y���[���i1804-1881�N�j �x���W���~���E�f�B�Y���[���i1804-1881�N�j |
�f�B�Y���[����1868�N2��27���ɎƂȂ�܂����B ���̑�ꎟ�f�B�Y���[�����t�͑��I���Ŕs�k���A�Z���ɏI���܂����B ���N12��3���A9�����قǂŃf�B�Y���[���͎ޔC�ƂȂ�܂����B �ޔC�ɂ�����A���B�N�g���A�����̓f�B�Y���[���Ɏ݈ʂ�^���悤�Ƃ��������ł��B�����̃�����������`����Ă��܂��ˁB |
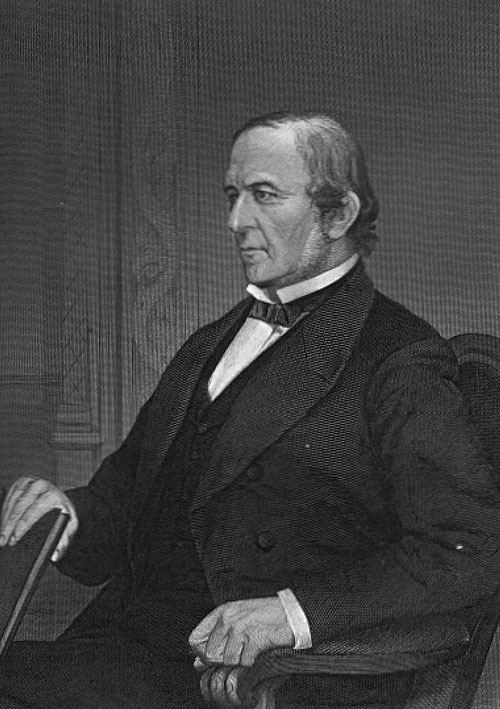 �E�B���A���E�O���b�h�X�g���i1809-1898�N�j1873�N�A63�� �E�B���A���E�O���b�h�X�g���i1809-1898�N�j1873�N�A63�� |
���̌�A�f�B�Y���[���̃��C�o���Ƃ����E�B���A���E�O���b�h�X�g����1868�N12��9���ɎɏA�C���܂����B 1869�N�Ƀ��C�I�l���̓O���b�h�X�g���ɁA���B�N�g���A�����֏��݂𐄋����Ă��炢�܂����B �������Ȃ��甽�����đނ����܂����B �C�M���X�M���̏����͒n��ł��邱�Ƃł����A���C�I�l���͊�ƉƁE���@�Ƃ̖ʂ������Ƃ����̂����̗��R�ł����B �����A����͕\�����ɗ��R�ł��B |
 ���B�N�g���A�����̈�Ԃ̒�����������r�[�R���Y�t�B�[���h���݃x���W���~���E�f�B�Y���[���i1877�N���j ���B�N�g���A�����̈�Ԃ̒�����������r�[�R���Y�t�B�[���h���݃x���W���~���E�f�B�Y���[���i1877�N���j |
�����鉳���͈Ӓ��̒j�������ڂɓ���܂���B�f�B�Y���[��������œ|�����O���b�h�X�g���͋C�ɓ���܂���ł����B ��Ă�f��͓̂��R�̗���ł���A�f�B�Y���[�����������Ă����烉�C�I�l���͏��݂ł��Ă������Ƃł��傤�B���C�I�l���͋M���ɂȂ�܂���ł����B �f�B�Y���[����1868�N�̏��݂͒f��܂������A1874�N����1880�N�ɍĂюƂȂ�A���̊Ԃ�1876�N�Ƀr�[�R���Y�t�B�[���h���݂����݂��Ă��܂��B |
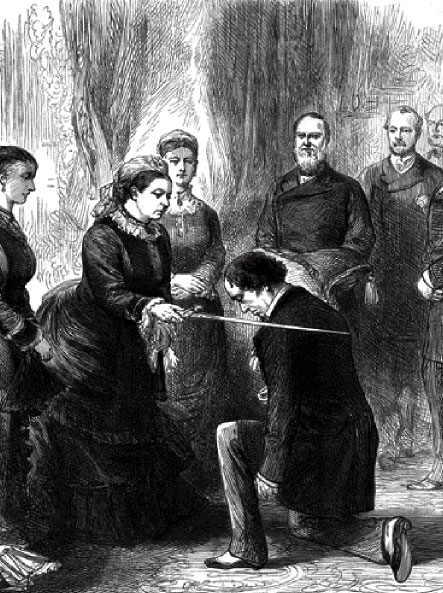 ���B�N�g���A��������K�[�^�[�M�͂����^����鏉��r�[�R���Y�t�B�[���h���݃x���W���~���E�f�B�Y���[���i1804-1881�N�j1878�N�A73�� ���B�N�g���A��������K�[�^�[�M�͂����^����鏉��r�[�R���Y�t�B�[���h���݃x���W���~���E�f�B�Y���[���i1804-1881�N�j1878�N�A73�� |
1878�N�ɂ́A�������M���̍ō��ʂł�������������悤�Ƃ��܂����B �����������Ղ肪�����������܂����A�����̐l�X�͂ǂ����Ă����ł��傤�ˁi�j �f�B�Y���[���͂����f��A���̑���ɃK�[�^�[�M�͂����^���Ă��炢�܂����B |
2-1-8-8. �n�Ղ������������C�I�l���E�h�E���X�`���C���h
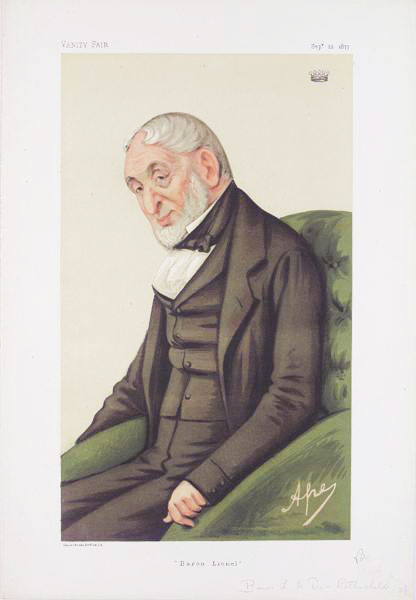 ���C�I�l���E�h�E���X�`���C���h�i1808-1879�N�j1877�N�A68�� ���C�I�l���E�h�E���X�`���C���h�i1808-1879�N�j1877�N�A68�� |
�^�C�~���O�Ɍb�܂�Ȃ��������Ƃ�����A���C�I�l���̑�ł̏��݂͊����܂���ł����B �������Ȃ��烍�X�`���C���h�Ƃ͐���z���ĕ�������Ղ��A�v������Ɍ����ē����܂��B ���C�I�l���͉p�����{�ɂ�����݂��܂���A���̑��z��4���|���h�ɒB���������ł��B ���q��t���ĕԂ��ė��܂�����A�߂��Ⴍ����������������ł��ˁB���������Ɏx�z�������邱�Ƃ��ł��܂��B ���̑��A�C�M���X�M���̃C���[�W�Ƃ��ďd�v�ȁw�n��x�̒n�ʂ��ł߂Ă��܂����B |
 ��2��o�b�L���K�����V�����h�X���݃��`���[�h�E�e���v�����j���[�W�F���g���u���b�W�X���V�����h�X���O�������B���i1797-1861�N�j1830�N�A33�� ��2��o�b�L���K�����V�����h�X���݃��`���[�h�E�e���v�����j���[�W�F���g���u���b�W�X���V�����h�X���O�������B���i1797-1861�N�j1830�N�A33�� |
1848�N�Ƀ_�b�V���E�b�h���j�݉ƁA1849�N�Ƀo�b�L���K�����V�����h�X���݂���L��ȗ̒n���A��n��ƂȂ��Ă��܂����B ���݂͉����ɕ��ԂقǍ����n�ʂŁA���ۂɃo�b�L���K�����V�����h�X���݂͐��a���_�ł��Ȃ�T�������������ł����A1847�N�A50����100���|���h�ȏ�̍�������Ĕj�Y�鍐���������ł��B 2018�N���_��8,976���|���h�A���{�~�Ɋ��Z�����135���~�قǂł��B�l�̕��Ƃ��ẮA�Ƃ�ł��Ȃ��z�ł��ˁB |
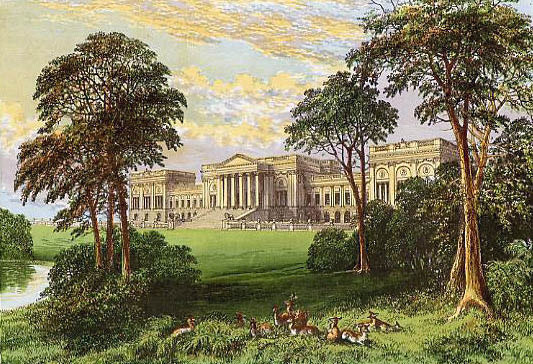 �o�b�L���K�����V�����h�X���݂̖{�@�������X�g�E�E�n�E�X�i1880�N�j �o�b�L���K�����V�����h�X���݂̖{�@�������X�g�E�E�n�E�X�i1880�N�j |
�������B�̂���1841�N�ɃT�}�Z�b�g�̃L�[���V�����̗̒n���A1847�N�ɃA���B���g���E�p�[�N�p���܂����B1848�N8������9���ɂ����āA���ɖ{�@�������X�g�E�E�n�E�X�������ɂ����܂����B19���I�̃C�M���X�̃J���g���[�n�E�X�����ɉ����āA�ő�K�͂ƂȂ��������ł��B �������Ē��X�ƒn�Ղ��ł߁A�M���ւ̒���͎��̑�Ƀo�g���^�b�`����܂����B |
2-1-8-9. �p�ӎ����ɐi�߂�ꂽ��3�㓖��i�T�j�G���E���X�`���C���h�̋M���@����
 ���B�N�g���A������Ɓi1846�N�j�Ԃ����̏��N��5���̉����q�o�[�e�B ���B�N�g���A������Ɓi1846�N�j�Ԃ����̏��N��5���̉����q�o�[�e�B |
���C�I�l�����p�����̂́A�����̒��j�i�T�j�G���ł����B�i�T�j�G���̓��B�N�g���A�����̒��j�ɂ��āA���������ƂȂ�o�[�e�B��1�ΈႢ�ł����B |
 �����q�o�[�e�B�i��̃C�M���X�����G�h���[�h7���j�i1841-1910�N�j5�� �����q�o�[�e�B�i��̃C�M���X�����G�h���[�h7���j�i1841-1910�N�j5�� |
�o�[�e�B��1859�N�A17�̍��ɃI�b�N�X�t�H�[�h��w�ɓ��w���܂����B�C�M���X�̗��̍����ł͏��߂Ă̑�w���w�ƂȂ�܂��B �u��[�A�����ǂ������̂ˁB���w���̉��q�l�Ȃ̂ˁB�v�Ƃ����̂́A����̏����̔��z��������܂���B �Â�����̓C�M���X�̑�w�͒��g�������������Ƃ�����A�㗬�K���͗D�G�ȉƒ닳�t���ق��ĉƒ�w�K��������A�C�[�g���E�R���b�W�𑲋ƌ�͑�w�ɂ͍s�����A�ƒ닳�t��ѓ����ăO�����h�c�A�[�ɏo������̂��ʏ�ł����B |
�����N��ƂȂ�̂́A�����̒��ł����肳�ꂽ�l�݂̂ł��B��p�鍑�̏ɑ������鉤�w���K�{�ł����A���̑��̐l�X�ɂ́A������w��ł����܂�Ӗ�������܂���B����̂ɂ����͂��������Ƃ��Ă��A���̉ƒ닳�t���ق��ăI�[�_�[���C�h�I�ɋ��炷��̂��ʏ킾�����̂ł��B �O�����h�c�A�[�́A�t�����X�v���Ƒ����i�|���I���푈�Ȃǂ̍����ɂ���ĉ��ƂȂ�܂����B����ɔ����A�C�M���X�����̑�w���炪���B���Ă������悤�ł��B |
| �P���u���b�W��w�Őe�F�ƂȂ�����l | |
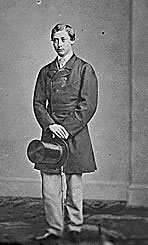 �I�b�N�X�t�H�[�h��w�݊w���̉����q�o�[�e�B�i��̍����G�h���[�h7���j�i1841-1910�N�j1860�N�A18�� �I�b�N�X�t�H�[�h��w�݊w���̉����q�o�[�e�B�i��̍����G�h���[�h7���j�i1841-1910�N�j1860�N�A18�� |
 ���ネ�X�`���C���h�j�݃i�T�j�G���E���X�`���C���h�i1840-1915�N�j ���ネ�X�`���C���h�j�݃i�T�j�G���E���X�`���C���h�i1840-1915�N�j |
1859�N10���ɃI�b�N�X�t�H�[�h��w�ɓ��w�����o�[�e�B�ł������A1861�N10���ɃP���u���b�W��w�ɓ]�Z���܂����B���̃P���u���b�W��w�Ńi�T�j�G���E���X�`���C���h�Əo��A�e�F�ƂȂ��������ł��B ���̃P���u���b�W��w�ł̌�w�F�����Ƒg��ŕs�Ǎs�ׂ��s���悤�ɂȂ�A���ꂪ�����Ă����܂����B�N���̒j�̎q�Ȃ�悭���邱�Ƃƌ����邩������܂��A�����뎟�������ƂȂ�l���ł��B�ꋓ�����ɒ��ڂ��W�܂�킯�ŁA���ʂ̐l�Ȃ�Ζ��ƂȂ�ʒ��x�̂��Ƃł���C�ɉ\���L�܂�A����ɂȂ蓾�܂��B ������뜜���A11���ɂ͕��A���o�[�g���z�������ɂ���Ă��܂����B |
|
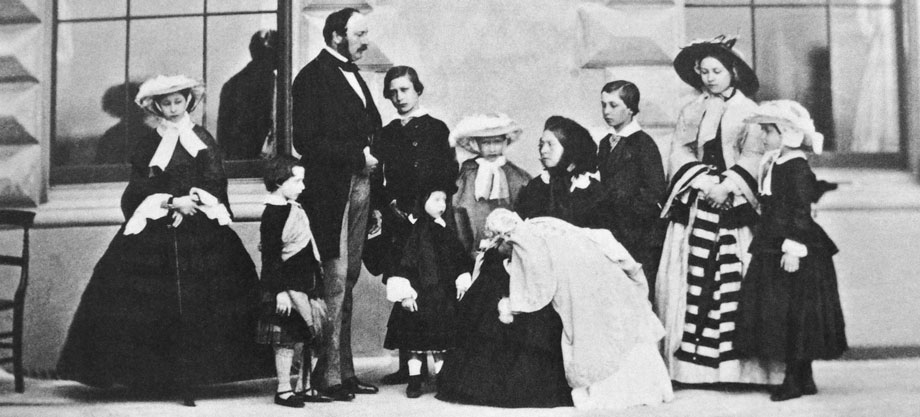 ���B�N�g���A�����v�Ȃ�9�l�̎q�������i1857�N�j ���B�N�g���A�����v�Ȃ�9�l�̎q�������i1857�N�j |
���C�����E�t�@�~���[�͑��Z�ł��B���ɃA���o�[�g���z�͎�����A�N���s�Ƃ��Ďd�������Ă������ߌ����ł����B�������ɑ̒�������Ă��܂������A�T���h�n�[�X�g�������R�m���w�Z�̐V�Z�ɏv�H���ɏo�Ȃ��Ă���o�[�e�B�̌��Ɍ������܂����B���J�̒��̏v�H�����������߁A����ɑ̒������������邱�ƂɂȂ����悤�ł��B �A���o�[�g���z�͑��q�o�[�e�B������A�o�[�e�B�͌����������Ɩ��ĕʂ�܂����B�߂����A���o�[�g���z�͑̒������������A��12���ɂ͊�ď�ԂɊׂ�܂����B |
| �^�ʖډ߂��������̐e�q | |
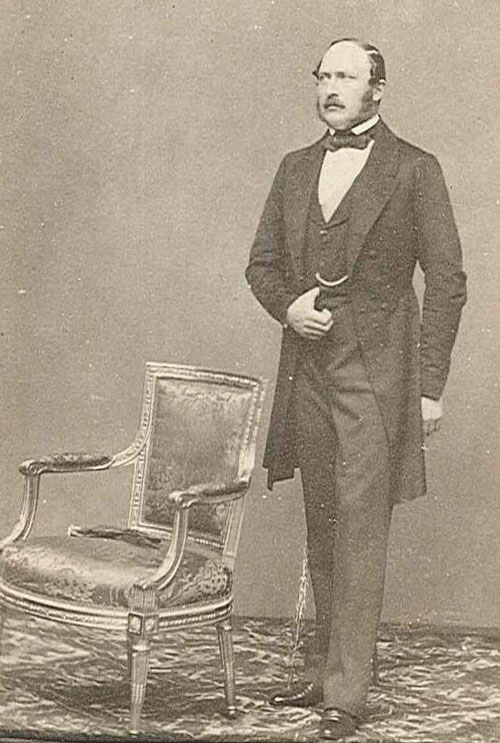 �A���o�[�g���z�i1819-1861�N�j41�� �A���o�[�g���z�i1819-1861�N�j41�� |
 �����q����̃C�M���X���G�h���[�h7���i1841-1910�N�j �����q����̃C�M���X���G�h���[�h7���i1841-1910�N�j |
���̊�Ă�m��A�o�[�e�B��12��14���̌ߑO3���ɃE�B���U�[��ɋ삯�t���܂����B�A���o�[�g���z�͕m���̏�Ԃł������A�o�[�e�B�̊������ƈ��S�����悤�ȕ\��ɂȂ�A�����̌ߌ�11���ɑ����������܂����B ����͎��̑z���ł����A���ɖڂɂ���ɗ��Ă͂���Ȃ��̂ł͎v���قǁA�A���o�[�g���z�̓o�[�e�B�ɑ��Ă������������Ă����̂�������܂���B����͐^�ʖډ߂��鐫�i�ƁA���������ƂȂ�o�[�e�B�̗�����v���Ă̂��Ƃł͂������͂��ł����A"�s��"�Ə̂����قǂ̌���������Œm���Ă��܂����ˁB ���ɖʂ������B �������A����Ȃ��Ƃ������Ă��{�C�ŐS�z���A�삯���ė��Ă��ꂽ���q�B�S�D�����o�[�e�B�̏����Ȋ፷�������āA���g�̕\����ׂ��̂��낤�Ƃ��z�����܂��B �����̐S�D�����Ɠ��̗ǂ�������A�o�[�e�B�͉����Ƃ��Ă̗��e�̗�����S�ł͗������Ă����̂ł��傤�B�o�[�e�B�̖{���̓A���o�[�g�E�G�h���[�h�ł��B�{���Ȃ�A�����Ƃ��Ă̖��̓A���o�[�g�ƂȂ�͂��ł����B |
|
| �^�ʖډ߂��������̐e�q | |
 �A���o�[�g���z�i1819-1861�N�j1848�N�A29�� �A���o�[�g���z�i1819-1861�N�j1848�N�A29�� |
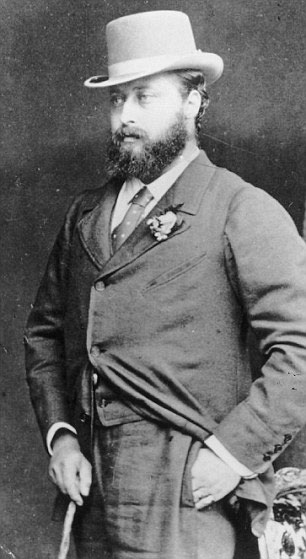 �����q����̃C�M���X���G�h���[�h7���i1841-1910�N�j �����q����̃C�M���X���G�h���[�h7���i1841-1910�N�j |
�������Ȃ���A�u�A���o�[�g�ƌ����ΒN���������v���o���悤�ɂ����������v�Ƃ������R�ŃG�h���[�h7���ɂ��������ł��B���ʂȗ���̂́A�Ȃ��b�ł��ˁB �A���o�[�g���z���g�͖{�C�Ńo�[�e�B���_���Ȑl�Ԃł���Ƃ͎v���Ă��Ȃ������͂��ł����A�����̍����Ƃ��Č�������Ă悤�Ƃ������̂ɁA�_�����A�o�����Ȃ��ł���Ȃǂ̕\�������Ă����悤�ł��B���B�N�g���A�����͂����������Ă��炸�A�A���o�[�g���z��������������ƂȂ��������܂����B �A���o�[�g���z���ǂ��ƌ��������̂͗ǂ��B�����ƌ��������͈̂����B����Ȕ��f�w�W�������B�N�g���A�����́A�o�[�e�B���o�����Ȃ��ł���Ǝv�������܂����B |
|
 1860�N��̉����q�o�[�e�B�i1841-1910�N�j 1860�N��̉����q�o�[�e�B�i1841-1910�N�j |
�Ⴂ�Ƃ͌����A20���߂�����l�ł��B ���������z���A�A���o�[�g���z�̐Ղ��p���ŌN��㗝�I�Ȏd���Ōo����ςޓ����������͂��ł��B �������Ȃ���Ƃ�ł��Ȃ��o�����Ȃ��Ƃ��āA���B�N�g���A�����̓o�[�e�B���������牓�����Ă��܂��܂����B �A���o�[�g���z���Ⴍ���ċ}�������̂̓o�[�e�B�̂����ł���ƍl�������Ƃ��A�����Ƃ���Ă��܂��B �A���o�[�g���z�����Ȃ��Ă��A�o�[�e�B�������Ɍg��邱�Ƃ��ł��Ă���A�����������ƒ��������Ă����\���͍l�����܂��B �N���������ɐ������A�Ӑ}���ĉ����𐭎�����r�����Ă������̂��B������Ƌ^�O���N�������ł�����܂��B |
| �����@�̋c�Ȃ��l���������X�`���C���h�̐e�q | |
| �y���z ���Z�̒��S�n �V�e�B�E�I�u�E�����h���I���� |
�y���q�z ��n��Ƃ��ĉe���͂����� �o�b�L���K���V���[�E�A���X�o�[���[�I���� |
 ���C�I�l���E�h�E���X�`���C���h�i1808-1879�N�j ���C�I�l���E�h�E���X�`���C���h�i1808-1879�N�j |
 ���ネ�X�`���C���h�j�݃i�T�j�G���E���X�`���C���h�i1840-1915�N�j ���ネ�X�`���C���h�j�݃i�T�j�G���E���X�`���C���h�i1840-1915�N�j |
����͂��Ă����A�P���u���b�W��w�Ŗ����̉p�����o�[�e�B�Ɛe�F�ɂȂ����i�T�j�G���E���X�`���C���h�́A1865�N�ɑI���ɏo�n���܂����B�����C�I�l���Ƃ͈قȂ�A�o�b�L���K���V���[�E�A���X�o�[���[�I���悩��ł��B���X�`���C���h�Ƃ���n��Ƃ��ĉe���͂����n��ł��B24�̃i�T�j�G���͌������I���A1885�N�ɋM���@�ɈڐЂ���܂ōđI���ꑱ���܂����B |
|
| ���X�`���C���h�Ƃ̋c�� | |
| �y���z���C�I�l�� ���Z�̒��S�n �V�e�B�E�I�u�E�����h���I���� |
�y���q�z�i�T�j�G�� ��n��Ƃ��ĉe���͂����� �o�b�L���K���V���[�E�A���X�o�[���[�I���� |
1847�N�@�����I�i38���j |
1865�N�@�����I�A�����@�̋c�Ȋl���i24�j 1876�N�@�f���̃C�M���X�̏y�j�݈ʂ��p���i35�j 1879�N�@���̃I�[�X�g���A���n���K���[�鍑�̒j�݈ʂ��p���i38�j 1885�N�@�����@→�j�݈ʂ����݂��M���@�Ɉڐ� 1915�N�@�����i74�Ζv�j |
���C�I�l���͋M���@�̋c�Ȃ��܂���ł������A�i�T�j�G���̑�Ŋm���ɋc�Ȃ���悤�A���X�Ə����͐i��ł��܂����B1876�N�ɁA�f���A���\�j�[����C�M���X�̏y�j�݈ʂ��p�����Ă��܂��B �u�H�H�H�v�Ǝv��ꂽ��������������ł��傤�B�C�M���X�̏ꍇ�A�݈ʂ��p���ł���̂͒��j�̒��q1�l�݂̂������͂��ł��B�o�q��{�q�Ȃǂ͔F�߂�ꂸ�A�Y���҂����Ȃ��ꍇ�͗e�͖����p��ƂȂ�̂��ʏ�ł����B |
|
| �C�M���X�̃��X�`���C���h�� | ||
| �n�c | ���j | ���j |
 �l�C�T���E���C�A�[�E���X�`���C���h�i1777-1836�N�j �l�C�T���E���C�A�[�E���X�`���C���h�i1777-1836�N�j |
 ���C�I�l���E�h�E���X�`���C���h�i1808-1879�N�j ���C�I�l���E�h�E���X�`���C���h�i1808-1879�N�j |
 ���ネ�X�`���C���h�y�j�݃A���\�j�[�E�h�E���X�`���C���h�i1810-1876�N�j ���ネ�X�`���C���h�y�j�݃A���\�j�[�E�h�E���X�`���C���h�i1810-1876�N�j |
�A���\�j�[�̓l�C�T���̎��j�ŁA���C�I�l���̒�ɂ�����܂��B��n�ɗD��A���P�Ƃł�����A���̌��тŃ��B�N�g���A��������i�C�g�̏̍���^�����Ă��܂����B�x���W���~���E�f�B�Y���[����E�B���A���E�O���b�h�X�g���ȂǁA���E�̏d���Ƃ��e�������Ă��������ł��B �A���\�j�[��2�l�̖����������̂́A���q�͂��܂���ł����B1847�N�A�A���\�j�[�͓���ŁA�Z���C�I�l���̑��q�����Ɍp���\�ȏy�j�݈ʂ����^����܂����B |
||
 ���ネ�X�`���C���h�j�݃i�T�j�G���E���X�`���C���h�i1840-1915�N�j ���ネ�X�`���C���h�j�݃i�T�j�G���E���X�`���C���h�i1840-1915�N�j |
����ɂ��A1876�N�̏f���A���\�j�[�̎����ɔ����ăi�T�j�G�����y�j�݈ʂ��̂ł��B 1870�N��̃G�W�v�g�́A�����I�ɕ��s���Ă���̂Ɠ����ɍ����j�]�̏�Ԃɂ���܂����B�G�W�v�g�����̓C�M���X�ƃt�����X�ɂ���ĊǗ�����Ă���ƂȂ��Ă���A�G�W�v�g�l�����͕s���������Ă��܂����B 1882�N�A���ɃE���r�v�����N���܂����B�������Ȃ���C�M���X�R�ɒ�������܂����B �苒�����ہA�i�T�j�G���̓G�W�v�g�̍����Č��̂��߂�850���|���h�̎؊�����܂����B���̉��܂Ƃ��āA1885�N�Ƀ��B�N�g���A��������j�݈ʂ��^�����܂����B |
| �C�M���X�̃��X�`���C���h�� | ||
| �n�c -�p���ɈڏZ- |
�q -�����@�c��- |
�� -�����@→�M���@�c��- |
 �l�C�T���E���C�A�[�E���X�`���C���h�i1777-1836�N�j �l�C�T���E���C�A�[�E���X�`���C���h�i1777-1836�N�j |
 ���C�I�l���E�h�E���X�`���C���h�i1808-1879�N�j ���C�I�l���E�h�E���X�`���C���h�i1808-1879�N�j |
 ���ネ�X�`���C���h�j�݃i�T�j�G���E���X�`���C���h�i1840-1915�N�j ���ネ�X�`���C���h�j�݃i�T�j�G���E���X�`���C���h�i1840-1915�N�j |
�������ă��X�`���C���h�Ƃ̓C�M���X�̋M���@������ʂ����܂����B�J�l�̗͂ɂ������܂����A������ׂ��悤�Ȓ����ɓn��v�����ł�������A�����ɂ��A�g�̐����ɂ͋����܂��B |
||
2-1-9. �����őz������`���I�ȃC�M���X�M��
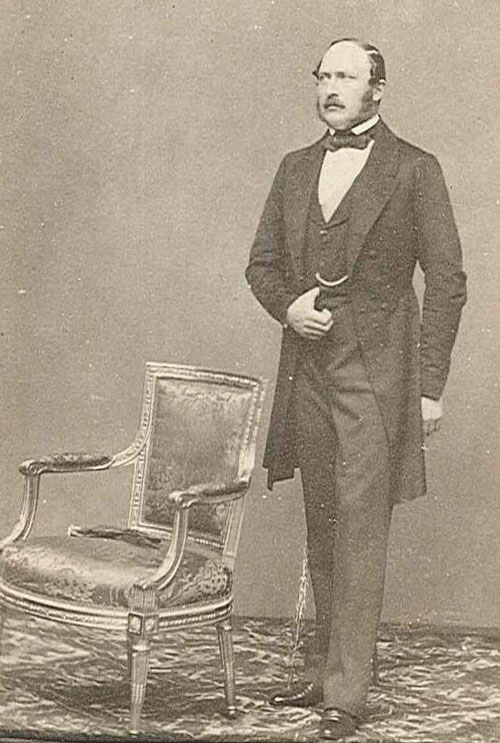 �A���o�[�g���z�i1819-1861�N�j41�� �A���o�[�g���z�i1819-1861�N�j41�� |
1861�N�ɃA���o�[�g���z���S���Ȃ�����A�}���Ȑ����ŋM���@�ɐV���������N�����Ă����܂����B 1830�N���350�Ƃ������݈ʋM���� ������ƈٗl�ł���ˁB 1870�N���400�ƂƂ����̂�1879�N�܂ł�400�ƂɂȂ��Ă����Ƃ������ƂŁA��������1885�N�ɂ�450�ƂƂ������Ƃ́A�͂�6�N�قǂ�50�Ƃ��M���������Ă���Ƃ������Ƃł��B |
 �A���V�������W�[���h�����G�i1789�N�j �A���V�������W�[���h�����G�i1789�N�j |
�������[���b�p�̋M���Ƃ�������ł��邪�̂ɁA�C�M���X�M���Ƃ��Ẵt�����X�M�����悤�Ȃ��̂ƌ��Ă��܂��l�����܂��B �������Ȃ���A���ۂ͂܂�ň�ۂ��Ⴂ�܂��B �t�����X�M���̏ꍇ�A���܂�ɂ��M���̐������߂��܂����B���̂��߁A���̋M�����T���ɂȂ邽�߂ɁA���������葽���������ł���悤�ꐶ�����ɍl����Ƃ������Ԃ��������₷���ɂ���܂����B |
�������Ȃ��琔���ɒ[�Ɍ����A"���܂�Ȃ���ɂ��Ĕ���ȕx������"�Ƃ��Đ��܂�Ă���̂��C�M���X�M���ł��B����͏����܂����A������͂��̂悤�ȏɂ��邽�߁A��̂́u�撣���Đ���オ��I�v�Ƃ����ӎ���o���͂���܂���B ����オ���S���Ȃ��A��J�����Ă��Ȃ��̂ɔ���ȕx�ƌ��͂����B���L������Y�◧��́A�����̍˔\��w�͂ɂ����̂ł͂Ȃ��A�_�ɂ��^����ꂽ�����ł���B |
 �w���a�̂��邵�x �w���a�̂��邵�x���[�}�����U�C�N�@�f�~�p�����[�� �C�^���A�@1860�N�� ��2,030,000-�i�ō�10%�j |
�N��̉����_�����Ɠ��l�ɁA�M���Ƃ����n�ʂ������͂���͂ɂ��Ă��A�_�ɂ��^����ꂽ�������ʂ������߂ɗ^����ꂽ�����ɉ߂����A���̖��߂��ʂ����Ȃ��̂͑ӑĂł���߁A�����Ď��~�̂��߂ɂ�����g���̂͂����Ă̂ق��Ƃ����l���ł����B |
 �f���H�����݂̃R���l�b�g �f���H�����݂̃R���l�b�g"Coronet EarlOfDevon PowderhamCastle" ©Lobsterthermidor(2014)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |
�܂��A��n��ł������C�M���X�M�������́A���̂����߂鏬���̉��̂悤�ȑ��݂ł�����܂����B |
 �可��������������Ƃ̎剮���ʁi�V���s�j"NiigataCityOpenData kyusasagawake02" ©�V���s(26 June 2016, 14:550:13)/Adapted/CC BY 2.1 jp �可��������������Ƃ̎剮���ʁi�V���s�j"NiigataCityOpenData kyusasagawake02" ©�V���s(26 June 2016, 14:550:13)/Adapted/CC BY 2.1 jp |
���{�l���w��n��x�ƕ����ƁA�ǂ����Ă����ۂ��V���{���z�����������Ǝv���܂��B �̂̒n��ƕ����ē��{�l���C���[�W����̂́A��ʂɂ́w�����x��w���_�x�Ȃǂ��Ǝv���܂��B�����̑����͕��m���o�ϓI�ɗT���ŁA�L�����~�ƍL��Ȕ_�n�����L���Ă��܂����B�����ł��K�͂͂��ꂼ��ł����A�可��������������Ƃ̎剮�͂���Ȋ����ł��B ���{�̏ꍇ�͒n�d������A��������吳�ɂ����Ă��n�吧���ł����W���������Ƃ���܂��B���̎����A50�����i125�G�[�J�[�j������w��n��x�ƌĂ�Ă��܂����B 50������495,867.5���āi��50�����āj�A�܂�0.4958675?�ŁA�����h�[������10.6���ł��B�ؐ��ɂ���ƁA150,000.68062503�i��15���j�ł��B����ŃC���[�W�ł����������������Ǝv���܂����A���͂܂������ς�C���[�W�ł��܂���i�j |
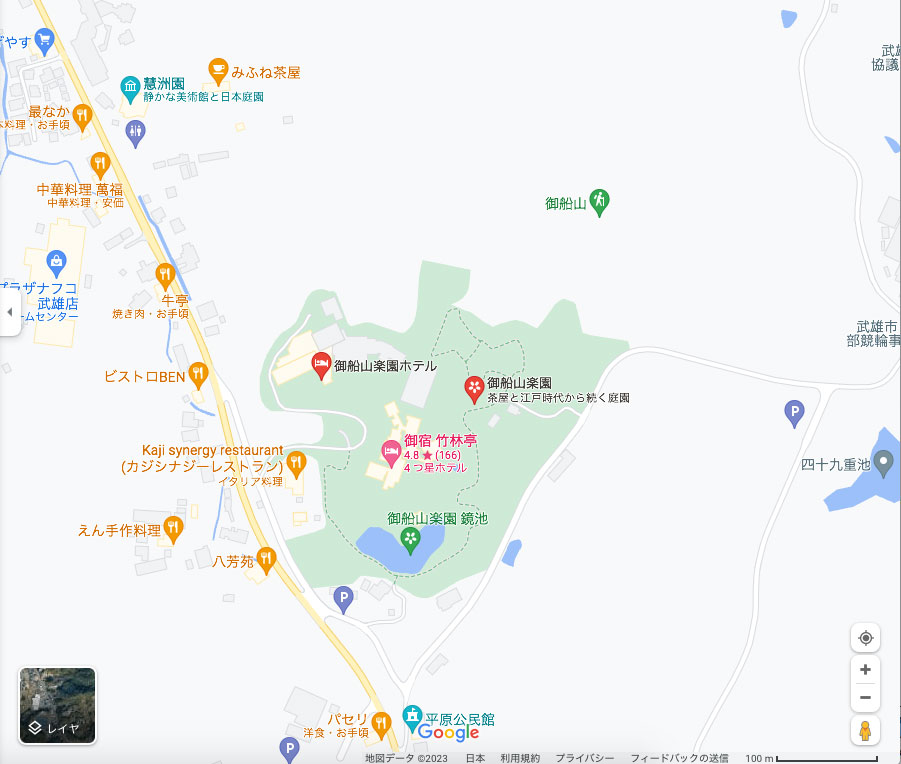 ��D�R�y���i���ꌧ���Y�s�j©google map ��D�R�y���i���ꌧ���Y�s�j©google map |
���ꌧ�̕��Y�̎�E�瓇�`�̕ʓ@�Ձi������1845�N�j�A�w��D�R�y���x��50�����āi15���j�������ł��B���o�^�L�O���Ɏw�肳��Ă����뉀�ł��B���͍s�������Ƃ�����܂��A�E����100m�̃o�[�Ɣ�r����ƂȂ�ƂȂ��C���[�W�ł���ł��傤���B �V�����̎O���ɂ���X�m�[�s�[�N�ƌ�����Ђ̖{�Е~�n���A��5�������15���Ɋg������A�����{�݂�X�g���������镡���^���]�[�g�{�݂Ƃ���2022�N�t�ɊJ�Ƃ��������ł��B����܂��s�������Ƃ��Ȃ��̂ł����A15���̋K�͓I�ɂ͂��̂悤�Ȋ����ł��B ���Ȃ݂Ɂw��n��x�̒�`�́A���͓��{�ƃC�M���X�ł͋K�͂����Ȃ�قȂ�܂��B |
| ��n��̒�` | |
���{ |
50�����i125�G�[�J�[�A50�����āA15���j�ȏ� |
| 1870�N��̉p�� | 1,200�����i3,000�G�[�J�[�A1,200������=12�����q�A360���j�ȏ� |
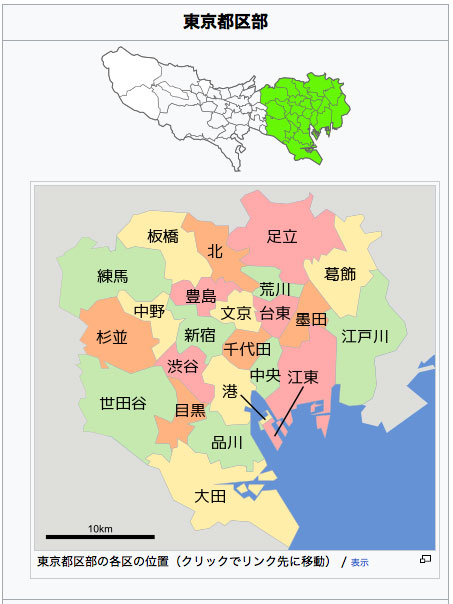 �����s�敔 �����s�敔�y���p�z�w�t���[�S�Ȏ��T�@�E�B�L�y�f�B�A���{��Łx�����s�敔 2023�N3��26��(��) 03:42 UTC |
���{�l���C���[�W�����n���24�{�ȏ�̓y�n�������Ȃ���A1870�N��̃C�M���X�ł͑�n��Ƃ݂͂��܂���ł����B �C�M���X�̑�n��̍Œ�����ƂȂ�12�����q�́A3�`4�L���l���̍L���ɑ������܂��B���⒬�ł͂Ȃ��A��ʓI�Ȏs��̍L���ɂ�����܂��B ���c��i11.66�����q�j�A������i11.29�����q�j�A�L����i13.01�����q�j���炢�̍L���ł��B ���Ȃ�̐l�����Z�߂܂��B���{�̑�n��̖ʐςƂ͌��Ⴂ�̍L���ł��B�ƂĂ������Ɉ����郌�x���ł͂���܂���B |
 �T�U�[�����h���݁i1963�N�ɃT�U�[�����h���݂��番���j�̓@��_�����r���� �T�U�[�����h���݁i1963�N�ɃT�U�[�����h���݂��番���j�̓@��_�����r����"Dunrobin Castle -Sutherland -Scotland-26May2008(2)" ©jack_spellingbacon, Snowmanradio(30 November 2009, 15:38)/Adapted/CC BY 2.0 |
���Ȃ݂ɓ����C�M���X�ő�̑�n�傾�����T�U�[�����h���݃��[�\�����S�A�Ƃ̏ꍇ�A��33��6,274�����i135��854�G�[�J�[�j�����L���Ă��܂����B5,467�����q�ɑ������܂��B����͎s�łȂ��A�����x���̍L���ł��B |
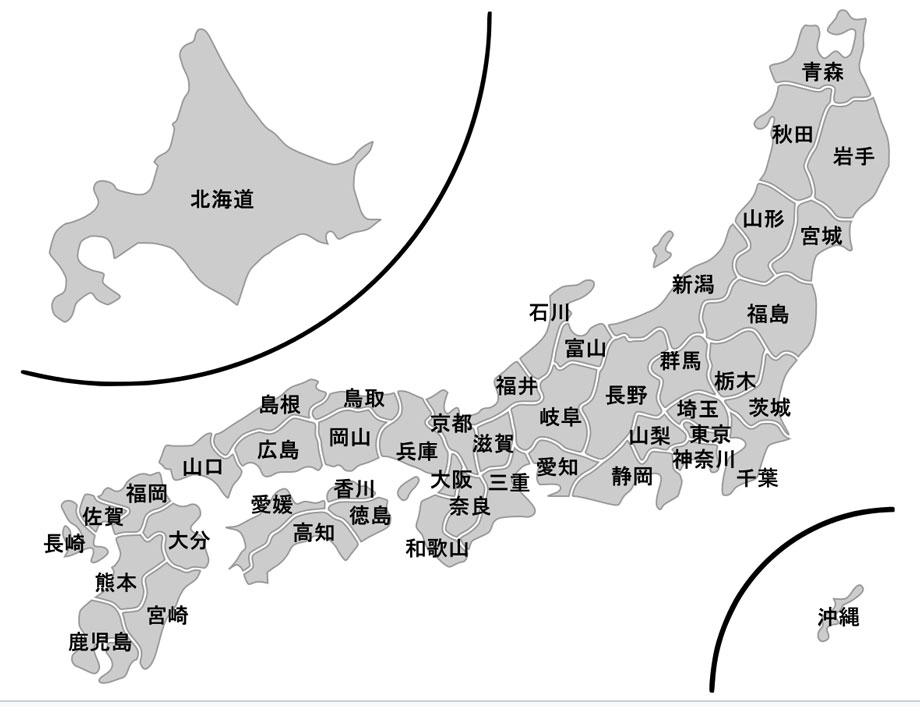 �s���{��
�y���p�z�w�t���[�S�Ȏ��T�@�E�B�L�y�f�B�A���{��Łx�s���{�� 2023�N3��15��(��) 17:18 UTC �s���{��
�y���p�z�w�t���[�S�Ȏ��T�@�E�B�L�y�f�B�A���{��Łx�s���{�� 2023�N3��15��(��) 17:18 UTC |
�T�U�[�����h���݂�5,467�����q�ɋ߂��L���̌��Ƃ��Ă͎O�d���i5,774�����q�j�A���Q���i5,676�����q�j�A���m���i5,172�����q�j�A��t���i5,158�����q�j���������܂��B�����s��1,400���l�قǂ��Z��ł��܂����A2,191�����q�����ʐς͂���܂���B�����s�̔{�ȏ�̖ʐς����L���Ă����Ƃ������Ƃł��B ��n��ƕ����āA��������N���X��z�����Ă͂����܂���B�C�M���X�M���́A�˂̌N�傽��喼�N���X��z�����ׂ��Ȃ̂ł��B |
| �C�M���X�݈̎ʋM���̃R���l�b�g | ||||
���� "Coronet of a British Duke" ©Sodacan(20 July 2010)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |
��� "Coronet of a British MARQUESS" ©Sodacan(20 July 2010)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |
���� "Coronet of a British EARL" ©Sodacan(20 July 2010)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |
�q��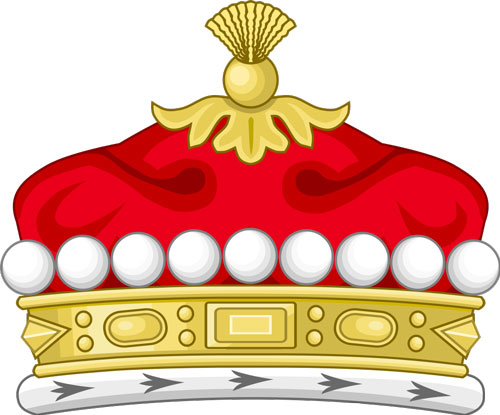 "Coronet of a British Viscount" ©Sodacan(20 July 2010)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |
�j�� "Coronet of a British Baron" ©Sodacan(20 July 2010)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |
�܂��ɃC�M���X�M���͏����̉��ł���A���̏W���̂�UK�iUnited Kingdom�F�A�������j�ƌ�����̂ł��B ���̂̐l�X�̍K�����肢�A���̂��߂ɐs�͂���B�C�M���X�M���̕x�ƌ��͂́A���̖������ʂ������߂Ɏ������ꂽ���̂ɉ߂��܂���B�����炱�����Ȍ����~�������߂Ɏg�����̂ł͂���܂��A���܂�Ȃ���Ɏ����Ă��邪�̂ɁA�����Ă���̂�������O�Ƃ����}�C���h�Ȃ̂ŁA�����������̕x�ƌ��͂��Ђ��炩���Ď��Ȍ����~�������Ƃ������z�ɂ��Ȃ蓾�Ȃ��̂ł��B |
||||
2-1-10. �V�������̎v�l�p�^�[��
�V�������͐���オ��ł��B �ŏ��͎�������҂������l���A���g�̍˔\��^�ɂ���Ė�S��B�����邱�Ƃ�"���Ă��"�ƂȂ�킯�ł��B�}�C���h�Ƃ��ẮA�u�����Ă��Ȃ��̂�������O�v�Ƃ�����Ԃɂ���܂��B�̂ɁA"�����Ă��Ȃ�"�ƌ��F�ɑ��A��X�Ɏ����Ă��邱�Ƃ��Ђ��炩�������Ȃ�̂ł��B |
| �h���肽���C������}�����Ȃ��V������ | |
| ���g�̂Ȃ��h�h��p�[�e�B�[ | �f�U�C���I�Ƀo�����X�̈��������W���G���[ |
 �T���H�C�E�z�e���̃S���h���E�p�[�e�B�i1905�N�j �T���H�C�E�z�e���̃S���h���E�p�[�e�B�i1905�N�j |
 �}�b�P�C�E�G�������h���_�C�������h�E�l�b�N���X�i�J���e�B�G�E�t���[���@1931�N�j �}�b�P�C�E�G�������h���_�C�������h�E�l�b�N���X�i�J���e�B�G�E�t���[���@1931�N�j"Cartier 3526707735 f4583fda9a" ©thisisbossi(12 May 2009)/Adapted/CC BY-SA 2.0 |
�N���̂��߂ɂł͂Ȃ��A���g�̍��𑝂₷�ׂ��w�͂��Ă����l�����ł��B��������l�̂��߂ɐs�͂��悤�Ƃ������z�ɂ͂Ȃ�܂���B�ނ���A��������l����������D������āA�����Ɖ҂��ŕx��~���˂Ƃ���l����\�����炠��܂��B�����ăh�����āA����܂Ŗ������Ȃ��������Ȍ����~�������Ƃ���̂ł��B �J�l�Ȃ�āA�{���͎����Ώۂɂ͂Ȃ�܂���B�����炻�̕��@�Ńh�����Ă��A�S���^�ɖ�������邱�Ƃ͂���܂���B���������@��m��Ȃ����������́A�u�����ƍ����Ȃ��̂���ɓ���Ď�������Ζ�������ɈႢ�Ȃ��B�v�Ǝv�����݁A�ȓw�͂��d�ˑ����܂��B���̂��߂ɂ́A����Ȃ邨�����K�v�ł��B |
|
 ��2��o�b�L���K�����V�����h�X���݃��`���[�h�E�e���v�����j���[�W�F���g���u���b�W�X���V�����h�X���O�������B���i1797-1861�N�j1830�N�A33�� ��2��o�b�L���K�����V�����h�X���݃��`���[�h�E�e���v�����j���[�W�F���g���u���b�W�X���V�����h�X���O�������B���i1797-1861�N�j1830�N�A33�� |
���܂�Ȃ���ɑ���������������ڂ�����܂́A�K�v�ȏ�̂������A�N������ނ������Ăł����悤�Ƃ͂��܂���B �����ƍK���͕K��������v���܂���B �j�Y�͂��߂��ł����i�j |
�����ɂ���O�͂������ł��傤����ǁA��̂͂����ƒ~�����邽�߂ɁA����ɒN������ނ���Ƃ�Ȃ��Ă͂Ɣ��z���܂��B���Ȍ����~�������ƁA�܂�K���̂��߂ɂ͂������K�v�ƐM�����݁A�K�v�ȏ�ɂނ����낤�Ƃ��܂��B ����ȐV�������ł����Ă��A�M�����肵�Č������Ќ��E�̒��Ő�����������A100�N�A200�N�̔N�����o�ĂM���炵����������Ă������̂ł����B �������Ȃ���A6�N��50�Ƒ�����ȂǂƂ����A19���I�������20���I�O���ɂ����Ăُ͈̏�ł����B�����܂ňꋓ�ɐ����R���̐V���M����������ƁA�`���I�ȋM���ɝ��܂�Đ�������Ă����ǂ���ł͂Ȃ��A�V�����������𗘂����Ă������ƂɂȂ�܂��B |
2-1-11. �M���@���V�������̐N�������������ʋN��������
�M���@�́A�C�M���X�̐����o�ς��R���g���[���ł��܂��B �M���@���肵���V�������͂ǂ������ł��傤���B �`���I�ȋM���̂悤�ɁA�̖��̂��߂ɂȂ�悤�ɓ����킯���Ȃ��A�������������x�ƌ��͂���悤���d�p���ɗ�ނ̂͗e�Ղɑz���ł��܂��B �`���I�ȋM���̖͗��̂��߂ɂȂ炸�A�������肪��������悤�Ȑ���ɂ͓��R�����܂��B�V�������̋M���ɂ́A�ז��ȑ��݂ł��B �`���I�ȋM���̗͂��킬�����B�ǂ�������ǂ��ł��傤���H ���̓������A�V�������̋M���𑝂₷���Ƃł����B�`���I�ȋM���̐������点�Ȃ��ꍇ�A�M���@�̋c�Ȃ𑝂₵�A�V�������̋M���̊����𑝂₷���ƂŁA�`���I�ȋM����1�[1�[�̗͂���̉������A�V���������͂̈ӌ���ʂ��₷�����邱�Ƃ��ł��܂��B ��������Ă��܂��A������̂��̂ł��B�V�������ɓs�����ǂ��悤�ɐ��x�������A����ɐV�������̊����𑝂₷�B�����Ă���ɐ����ɓs�����ǂ���������Ă����B���̌`�ɂȂ��Ă��܂��܂����B |
2-2. 20���I�̋M���̏�
�@20���I�ɓ���Ɣ�ێ�}�n�̎������M���@�̕ێ琨�́A���Ȃ킿�`���I�ȋM�������̗͂��킮�ׂ��A�X�Ɏ݈ʂ𗐔����܂����B�������ď]���̒n��M���ł͂Ȃ��A�V�����͂ƂȂ鐬���M�����M���@�Ő��͂𑝂��Ă����܂����B�ЂƂ��ѐN���������A��͓{���̂悤�ɐ���ꍞ�ނ݂̂ł��B |
2-2-1.�`���I�ȋM����ׂ�����ł���������C�h�E�W���[�W
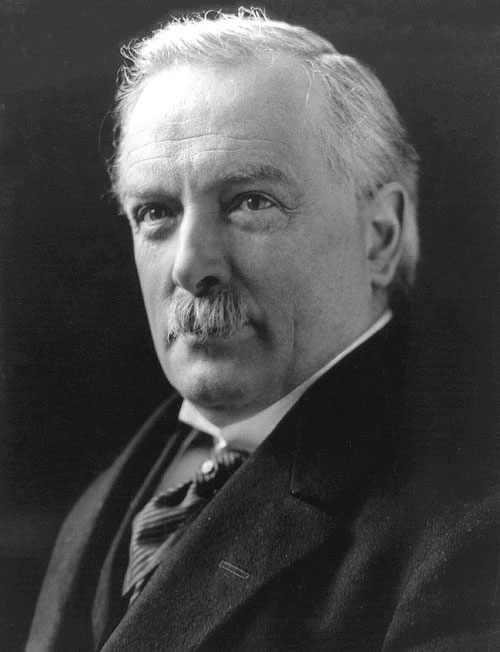 ����h���C�t�H�[�̃��C�h���W���[�W���݃f���B�b�h�E���C�h�E�W���[�W�i1863-1945�N�j1919�N�A56�� ����h���C�t�H�[�̃��C�h���W���[�W���݃f���B�b�h�E���C�h�E�W���[�W�i1863-1945�N�j1919�N�A56�� |
����E������݈ʂ̗����͍s���Ă��܂����A����M���̎�����I�킳����ׂ���O�Ɍ���ł�A�������Ƃ��āA���R�}�̃f���B�b�h�E���C�h�E�W���[�W�����܂��B �݈ʂ̗����ł��m���Ă���A�߂�1916�N����1922�N�܂ł�91���݈̎ʐV�݂���t���܂����B �h���C�t�H�[�̃��C�h���W���[�W���݂����݂��Ă��܂����A�����1945�N3��26����82�ŖS���Ȃ钼�O�A2��12���ɏ��݂������̂ł��B |
 ����h���C�g�t�H�[�̃��C�h���W���[�W���݃f���B�b�h�E���C�h�E�W���[�W�i1863-1945�N�j1890�N�A27�� ����h���C�g�t�H�[�̃��C�h���W���[�W���݃f���B�b�h�E���C�h�E�W���[�W�i1863-1945�N�j1890�N�A27�� |
���E�����1890�N�A27�̎��ł��B���R�}�����@�c���Ƃ��Ċ������n�߂܂����B �ƂȂ�����ꎟ���E���̍��́A�u�n�R�l����ɂ܂ŏ��l�߂��j�v�ƓO��I�ɔ�������Ă��������ł��B�܂��A�u���߂Ĉʐl�b���ɂ߂����q�̎q�v�Ƃ��Ă�܂����B |
 �W���[�t�E�`�F���o�����i1836-1914�N�j �W���[�t�E�`�F���o�����i1836-1914�N�j |
�����o�g�ō�������Ŋ��������ƂƂ��ẮA�����C�h�E�W���[�W���27�ΔN��̃W���[�t�E�`�F���o�����Ȃǂ��L���ł��B �o�[�~���K���s�����̑���v�Ŗ����グ�A�����ɐi�o���Ēʏ���b�A������b�A�A���n��b�Ȃǂ����߂܂����B �����A�`�F���o�����͕��ʂ̏����Ƃ����킯�ł�����܂���ł����B ���ƉƂ̑��q�Ƃ��Đ��܂�A��w���ƌ�͕����o�c����H��œ����A�o�����Ă�����ЂŌo�c�ɎQ�悷��Ȃǂ��A����ƉƂƂ��Đ������Ă����l���ł��B |
�M���ł͂Ȃ����̂́A���܂�Ȃ���ɂ��ėT����"���Ă��"�̗��ꂾ�����ƌ��邱�Ƃ��ł��܂��B �C�M���X�̏ꍇ�A�M�����ǂ���{�Ƃ��ċ@�\���Ă��܂����B�m�u���X�I�u���[�W���̐��_�������ɂ܂ŐZ�����Ă���A��������҂��w�͂���"���Ă��"�ƂȂ���~�������������P�����ƂɂȂ邱�Ƃ͓�����O�ɂ���܂������A�T���ȉƂɐ��܂�ė���Α�����"���Ă��"�̐ӔC�Ƃ��Ď��P����������Ƃ������Ƃ�����܂����B�u�������Ȃ��̂͒p�B�v�ƌ������炢�̊��o���������悤�ł��B |
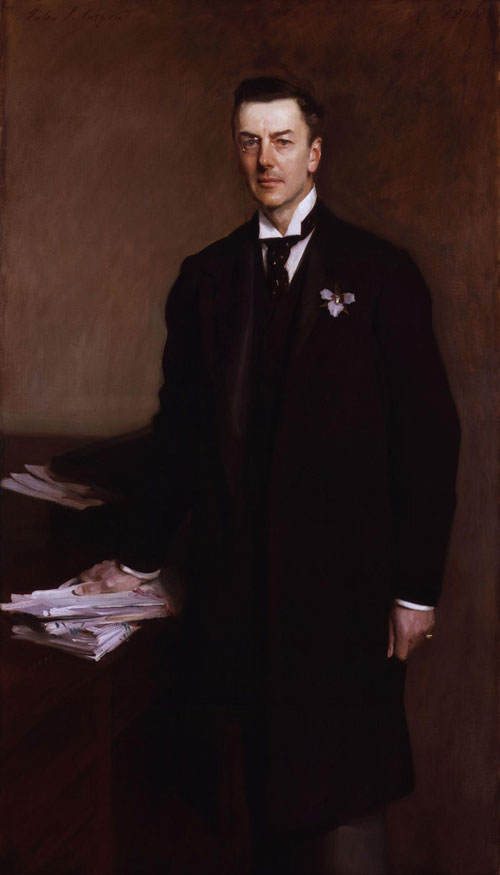 �W���[�t�E�`�F���o�����i1836-1914�N�j �W���[�t�E�`�F���o�����i1836-1914�N�j |
�̂Ƀ`�F���o�����������o�c�҂Ƃ��ĂӂԂ�悤�ȏX���s���͂����A�J���҂����̍K�����肢�A��ɓw�͂��Ă��܂����B ����ɘJ���҂����Ɠ��_����J������A�J�Ђ⎾�a�̕ۏ�g���n�݂��哱���܂����B ����ɂ͘J���҂����̂��߂̖�Ԋw�Z���J�Â��A���當�w�E���j�E�t�����X��E���w�̋��ڂ��Ƃ�܂����B �J�����𐮂���݂̂Ȃ炸�A�������T���Ōb�܂�Ă������炱������ꂽ���{���F�ɕ����^����A�F���瑸�h����x�����W�߂�̂����R�ł��傤�B |
| ���������n�m����Z���X���Q�̃W���[�t�E�`�F���o���� | |
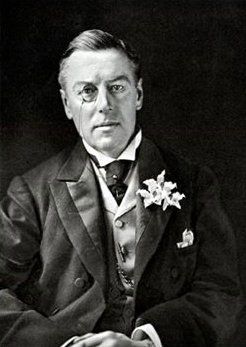 �W���[�t�E�`�F���o�����i1836-1914�N�j�A���n������ �W���[�t�E�`�F���o�����i1836-1914�N�j�A���n������ |
 �W���[�t�E�`�F���o�����i1836-1914�N�j1909�N�A73�� �W���[�t�E�`�F���o�����i1836-1914�N�j1909�N�A73�� |
�t�@�b�V�����E�Z���X���炵�Ă��A���炩�ɂ����̈�ʏ����ł͂���܂���B�㗬�K�����W���Ќ��E�ɉ����Ă���ڒu����A�l�ڂ��䂭�ł��낤���Q�̃Z���X�ł��B |
|
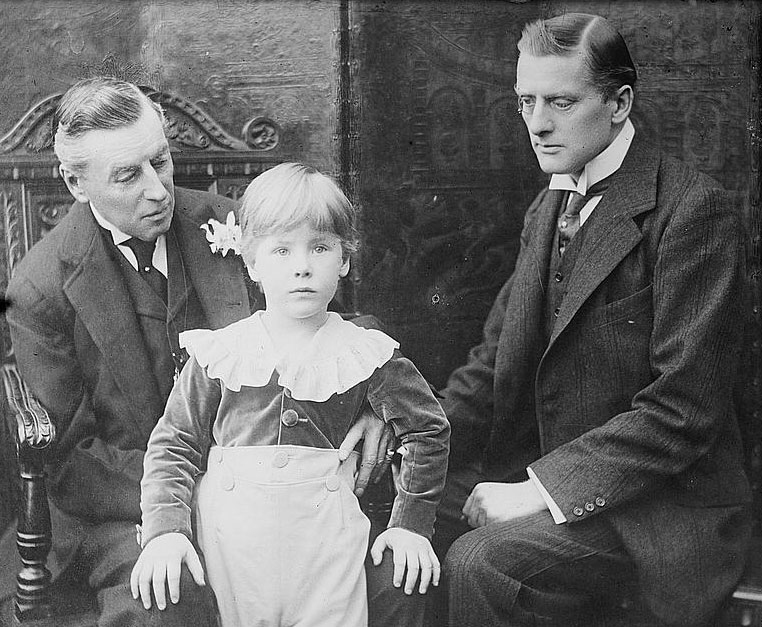 3����̎ʐ^�i���F�W���[�t�E�`�F���o�����A���F���W���[�t�A�E�F���j�I�[�X�e�B���j 3����̎ʐ^�i���F�W���[�t�E�`�F���o�����A���F���W���[�t�A�E�F���j�I�[�X�e�B���j |
�Ƒ��ʐ^�����Ă��A���炩�Ȉ炿�̗ǂ����`����Ă��܂��ˁB |
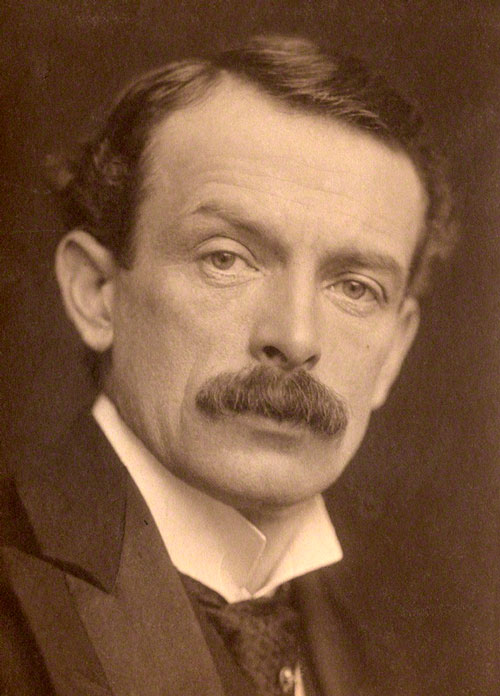 ����h���C�g�t�H�[�̃��C�h���W���[�W���݃f���B�b�h�E���C�h�E�W���[�W�i1863-1945�N�j1902�N�A39�� ����h���C�g�t�H�[�̃��C�h���W���[�W���݃f���B�b�h�E���C�h�E�W���[�W�i1863-1945�N�j1902�N�A39�� |
���C�h�E�W���[�W�̏ꍇ�A���t�̕��̌��ɐ��܂�܂����B �����A���C�h�E�W���[�W��1�̎��ɕ��͋��E��ނ��A���K�͂Ȕ_����w�����Ĉ�ƂňڏZ���܂����B ���̔N�̓��ɕ��͔x���ŖS���Ȃ��Ă��܂��A���Z��Ƌ��ɘH���ɖ����H�ڂɂȂ�܂����B���ǁA�C�����c�ޔ������`���[�h�E���C�h�̉Ƃɐg���������ł��B �{�l�H���A�q������ɒn��̍����U�镑�������Ēn�匙���ɂȂ��������ł��B �܂��A�n�����ƒ�ň�������̂悤�Ɍ���Ă��������ł����A���ۂɂ͊����Ɍb�܂ꂽ���Y�K���������Ƃ������Ă��܂��B |
�����܂ł����l�̈�ۂł����A����܂őO�Ⴊ�Ȃ������̂ɂ����̈�ʐl���ɂ܂ŏ��l�߂����ƁA�������e�ɋ��������邱�ƂȂǁA������ƌӎU�L����������l���ł��B�{�l�̈ӎv�ƌ������A�C�M���X�M�����I��点�邽�߂ɁA�N������Ӑ}���đ��荞�܂ꂽ�l���Ƃ��犴���܂��B �I���œ��I����ɂ͖{�l�̐����ƂƂ��Ă̍˔\�݂̂Ȃ炸�A�R�l�N�V�����⎑���͂Ȃǂ��K�v�ł����ˁB�����͂����̈�ʐl���ʏ�͎����̂ł͂���܂���B �c�����I���炢�܂ł͂��蓾�Ă��A�ɂ܂ŏ��l�߂�͕̂��ʂł͂���܂���B�f�B�Y���[���̂悤�Ƀ��B�N�g���A�����𗸂ɂ��ăG�R�ۛ����ꂽ�Ȃǂ���Δ[�����₷���ł����A���������܂���B |
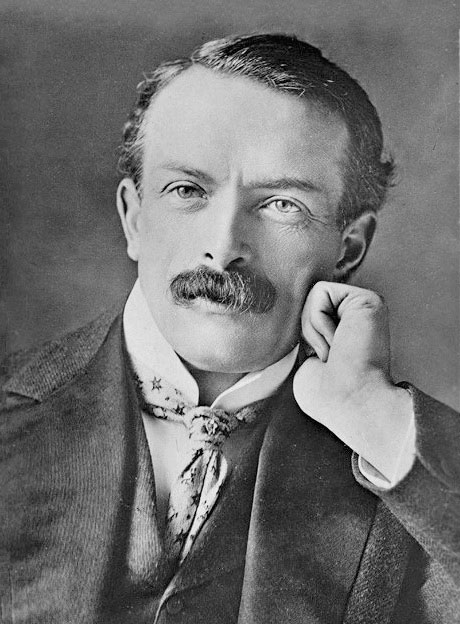 �呠��b����̏���h���C�g�t�H�[�̃��C�h���W���[�W���݃f���B�b�h�E���C�h�E�W���[�W�i1863-1945�N�j1911�N�A48�� �呠��b����̏���h���C�g�t�H�[�̃��C�h���W���[�W���݃f���B�b�h�E���C�h�E�W���[�W�i1863-1945�N�j1911�N�A48�� |
���āA���_�̏o���悤���Ȃ����Ƃ͂��Ă����B ���C�h�E�W���[�W�̓A�X�L�X���t�ɂđ呠��b�ɏA�C���܂����B���Ԃ�1908�`1915�N�ł��B�鍑��`���Q�����A���[���b�p�̏I���ƃA�����J�̑䓪�������炵����ꎟ���E���ɓ˓��������Ԃł��ˁB �呠��b���C�h�E�W���[�W��1909�N4���A"�푈�̐��"�𖼖ڂɁw�l���\�Z�x���c��ɒ�o���܂����B ���Ȃ݂ɐ푈�̖��ڂ�"�n���ƔߎS�̍���"�ł������A��ꎟ���E���̌��ʂ�����ƁA�ǂ��l���Ă����O�ɉ߂��Ȃ������悤�ɂ��������܂���B |
�w�l���\�Z�x�ɂ͏����ŗ��̈����グ�Ɨݐi�ېŐ��̋����A�����ł̈����グ�A�y�n�ېŐ��x���������荞�܂�Ă��܂����B ���ꂾ�����Ă��A��������ɂ͖��炩�ɋM�����^�[�Q�b�g�Ƃ��A�M���̗͂��킮���߂̂��̂Ƃ��z������������ł��傤�B �l���\�Z�͐��E�␢�_����܂����B�M���@�́w�Љ��`�\�Z�x�A�w�A�J�̗\�Z�x�Ə̂��A���ɓy�n�ېł͒n��M�����u�y�n�̍��L����_�����́v�Ƃ��Ĕ��܂����B |
| �l���\�Z�ł̑Η� | |
| �����@�c�� | �M���@�c�� |
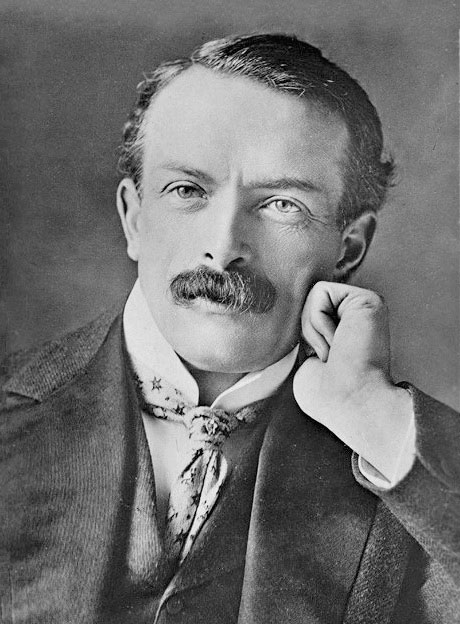 �呠��b����̏���h���C�g�t�H�[�̃��C�h���W���[�W���݃f���B�b�h�E���C�h�E�W���[�W�i1863-1945�N�j1911�N�A48�� �呠��b����̏���h���C�g�t�H�[�̃��C�h���W���[�W���݃f���B�b�h�E���C�h�E�W���[�W�i1863-1945�N�j1911�N�A48�� |
 ���ネ�X�`���C���h�j�݃i�T�j�G���E���X�`���C���h�i1840-1915�N�j ���ネ�X�`���C���h�j�݃i�T�j�G���E���X�`���C���h�i1840-1915�N�j |
���ꂼ��w�\�Z�^�������x�Ɓw�\�Z���Γ����x����������A���_����荞�������킢�ƂȂ�܂����B ���C�h�E�W���[�W�̓��X�`���C���h�j�݂��l���\�Z���Ή^���̍����Ƃ��Č������l�U���������Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂����A�S�̂̍��������X�`���C���h�j�݂�������ۂ�����܂��B�v�����X�����A�ړI�������\�Z�ʉ߂����R�Ɍ�����`�Ő����������悤�Ɍ����܂��B 1909�N11���A�l���\�Z�͏����@��ʉ߂������̂́A�M���@�Ŏ^��75�A����350�Ƃ������|�I�卷�Ŕی�����܂����B ������A�A�X�L�X���t�͋c��̉��U���I���ɑł��ďo�܂����B���I���̘_�_�́w�l���\�Z�x�Ɓw�M���@�����k���x�ɏW������܂����B���������炳�܂ł��ˁB 1910�N1���̉��U���I���͐ڐ�ƂȂ�܂����B���C�h�E�W���[�W��̎��R�}��275�c�ȁA�ێ�}��273�c�ȁA�A�C�������h�����}��82�c�ȁA�J���}��40�c�ȂƂȂ�A���ʂƂ��Ă͎��R�}��104�c�Ȃ��r�����邱�ƂƂȂ�܂����B �������Ȃ��烍�C�h�E�W���[�W��͏�肢���ƍ����A�A�C�������h�����}��J���}�̎x�������t���āA1910�N4��20���ɐl���\�Z���Ē�o���܂����B�����@�ʼn���A�M���@�̌����k���荞�c��@�Ă���o���A�M���@���[�Œʉ߂����邱�Ƃɐ������܂����B�Ȃ����\�I�Ȏ���Ɍ����܂����A�s���̈����@�Ă�ڗ����ʂ悤��������ʂ����肷��̂́A����ł����݂��镁�Ղ̎���ł����ˁB 1910�N4��28���A�����G�h���[�h7���̍ىāw�l���\�Z�x�͐������܂����B �������ċM���̗͖͂ڂɌ����Ď����Ă����܂����B �܂��A�A�X�L�X���t�͊C�R�����H���ɑǂ��A���C�h�E�W���[�W��}�i�h�t�����鍑��`�������߂Ă������ƂɂȂ�܂����B��������1914�N�̑�ꎟ���E���ɓ˓����Ă����܂��B |
|
| ���X�`���C���h�� | ||
| �� -�h�C�c�̋�s��- |
�� -5�l�̑��q�̕�- |
�O�j -�C�M���X�S��- |
 �}�C�A�[�E�A���V�F���E���[�g�V���g�i1744-1812�N�j �}�C�A�[�E�A���V�F���E���[�g�V���g�i1744-1812�N�j |
 �O�g���E���X�`���C���h�i1753-1849�N�j1836�N�A83�� �O�g���E���X�`���C���h�i1753-1849�N�j1836�N�A83�� |
 �l�C�T���E���C�A�[�E���X�`���C���h�i1777-1836�N�j �l�C�T���E���C�A�[�E���X�`���C���h�i1777-1836�N�j |
�u���̑��q�������]�܂Ȃ���A�푈���N���邱�Ƃ͂���܂���B�v �푈���_�@�ɁA���X�`���C���h�Ƃ͖����̕x�A���Ȃ킿�p���[��ςݑ����Ă��܂��B�V�˓I�Ɍ�������A����푈�̃`�����X�����������Ă���悤�ɂ������܂��B��ʐl�͈Ӑ}���ċ��ׂ��̂��߂ɈӐ}���Đ푈���N�����Ȃ�Ĕ��z�����܂��A�O�g���̂��̌��t�͌y�����Ȃ������ǂ��̂�������܂���E�E�B�@
��ꎟ���E���ł͑����̋M�����펀���܂����B�M���͏��Z�߂܂��B���S�n�т���w�����o���X�^�C���ł͂Ȃ��A�댯�ȑO���ɏo�Ďw�����Ƃ邱�Ƃ�������O���������߁A�����Ō����Ώ������y���ɑ����̋M�������������܂����B�{�l�݂̂Ȃ炸�Վ��܂Ő펀���A�����݈̎ʌp���҂����Ȃ��Ȃ������Ƃ����ƂȂ��������ł��B |
||
2-2-2. ����E������������w�M���x�Ƃ��������̔j��
2-2-2-1. �A�g���[�����ɂ�鑊���ŗ��̈����グ
 ����A�g���[���݃N�������g�E���`���[�h�E�A�g���[�i1883-1945�N�j1950�N�A67�� ����A�g���[���݃N�������g�E���`���[�h�E�A�g���[�i1883-1945�N�j1950�N�A67�� |
���ɕs�t�I�ȂقǁA��łւ̓���i�ނ����Ȃ��Ȃ����悤�Ɍ�����]����"�C�M���X�M��"�ł����A����ɒǂ��ł����������̂�����E����̃A�g���[�����ł��B �A�g���[�̍ݔC���Ԃ�1945�N7��26������1951�N10��26���ł��B ����6�N���x�ŁA98���݈̎ʂ̐V�݂���t���Ă��܂��B 1946�N�ɂ͑����ł̍ō��ŗ�90%�Ƃ����Œ��ꒃ�Ȉ����グ�����{���܂����B |
| �����G���U�x�X2�� �݈ʁF1952-2022�N |
2022�N9��8���ɏ����G���U�x�X2�������䂵�܂����B ���̔���ȍ��Y�̑����ɂ��āA�b������ɂ��ꂽ��������������Ǝv���܂��B �����̌l���Y�����Ŗ�3��7�疜�|���h�i��620���~�j�ƌ����܂����A�܂Ƃ��ɕ����ƂƂ�ł��Ȃ����ƂɂȂ�܂��B ���̓��{�̐��x�ł���A3��������Β~���͖����Ȃ�ƌ�����قǂł��B �������Ȃ���C�M���X�̌N�傩��N��ւ̑����ł́A�K���ȗ��R�����ė�O�I�ɖƏ��Ƃ���Ă��܂��B���̂��߁A���ł�����Ȏ��Y��ۗL���Ă��܂��B �M���͗�O�K���͂Ȃ���܂���ł����B�ƌ��������A���X�]���̋M������ł����邽�߂̂��̂������ƌ����܂��B |
 �Պ����̃G���U�x�X2���i1926-2022�N�j27�� " H.M. Queen Elizabeth II wearing her Coronation robes and regalia - S.M. la Reine Elizabeth II portant sa robe de couronnement et les insignes royaux " ©BiblioArchives / LibraryArchives from Canada(14 May 2012, 09:32)/Adapted/CC BY 2.0 �Պ����̃G���U�x�X2���i1926-2022�N�j27�� " H.M. Queen Elizabeth II wearing her Coronation robes and regalia - S.M. la Reine Elizabeth II portant sa robe de couronnement et les insignes royaux " ©BiblioArchives / LibraryArchives from Canada(14 May 2012, 09:32)/Adapted/CC BY 2.0 |
 ����f�{���V���[���݃E�B���A���E�L�����F���f�B�b�V���i1640-1707�N�j ����f�{���V���[���݃E�B���A���E�L�����F���f�B�b�V���i1640-1707�N�j |
�����ň����グ�̈З͂͐��܂����A���̉e�������܂�ɂ��}�����r��ŋM���ւ̍U���������炳�܉߂������Ƃ������Ă��A1954�N�Ɋɘa�̕����։�������܂����B �������Ȃ���1946�N����1954�N�̖�8�N�ԂŁA�����̋M������œI�ȑŌ����܂����B �f���H���V���[���݉Ƃ�x�b�h�t�H�[�h���݉Ƃ͒�������A�{�@�ȊO�̑S�Ă̓y�n�̔��p�𔗂��܂����B �Ⴆ�f���H���V���[���݉Ƃ́A���X��4��f�{���V���[���݂������E�B���A���E�L�����F���f�B�b�V����1694�N�ɏ��݂��Ĉȍ~�A����܂ő�������Ƃł��B |
 �f�{���V���[���݂̃^�E���n�E�X�������f���H���V���[�E�n�E�X���ʌ��ցi1906�N�j �f�{���V���[���݂̃^�E���n�E�X�������f���H���V���[�E�n�E�X���ʌ��ցi1906�N�j |
��n��ł���C�M���X�M���͖{��ƂȂ鏊�̂̃J���g���[�n�E�X�̂ق��A�Ќ��V�[�Y����d���Ȃǂ̗p���Ŏg�p���邽�߂̃^�E���n�E�X�������h���ɏ��L���܂��B �f�{���V���[���݂̓����h���Ɂw�f�{���V���[�E�n�E�X�x�����L���Ă��܂����B |
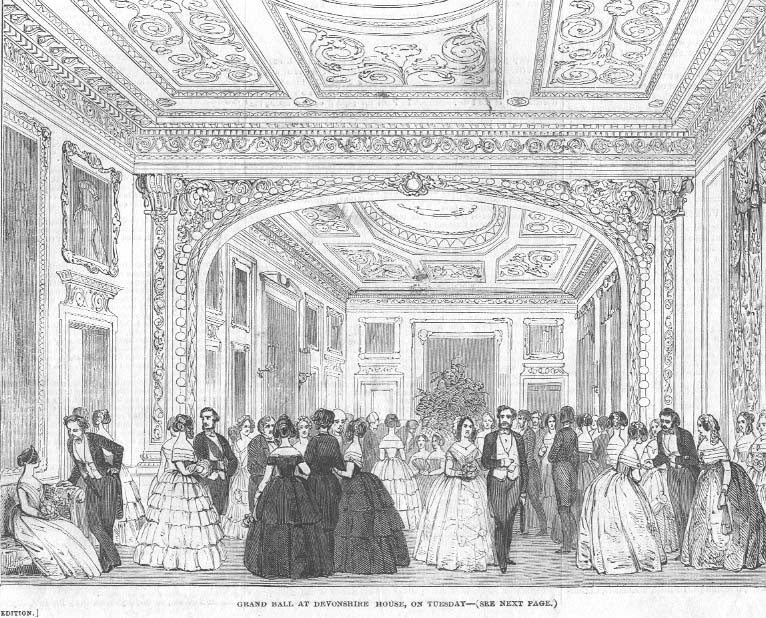 �f���H���V���[�E�n�E�X�̕������i�C���X�g���C�e�h�E�����h���E�j���[�X�@1850�N�j �f���H���V���[�E�n�E�X�̕������i�C���X�g���C�e�h�E�����h���E�j���[�X�@1850�N�j |
1740�N���Ɋ��������f�{���V���[�E�n�E�X�́A���S�l���̏㗬�K�����W�߂ĕ�������Â����Ƃ��ł���قǍ��ȃ^�E���n�E�X�ł����B |
| �_�C�������h�E�W���r���[���j���f���H���V���[�E�n�E�X�ł̑剼��������̎Q���ҁi1897�N�j | |
 |
 |
���B�N�g���A�����̑���60�N�ƂȂ�_�C�������h�E�W���r���[���j���A1897�N�ɊJ�Â��ꂽ�f�{���V���[�E�n�E�X�ł̑剼��������͑傫�Șb����Ăт܂����B �o�[�e�B���A���N�T���h�������q�v�Ȃ��n�߁A���S�l�̏㗬�K���̃Q�X�g���������j�I�ȏё���ɐ������h�������̂悤�Ȉߑ���g�ɓZ�����A�ƂĂ����т₩�ȕ�������������ł��B ���͌�Ƀm���E�F�[���z�[�R��7���ƂȂ�f���}�[�N�̃J�[�����q�A�����Ă��̍Ȃł���C�M���X�����G�h���[�h7���̖����[�h�����ƁA�o�̃��B�N�g���A�����ł��B�E�̓N���I�p�g���ɕ������A�[�T�[�E�p�Q�b�g�v�l�ł��B �����ɂ͒m��ꂴ��Ќ��E�̒��g�ł����A���̎��̏㗬�K�������̉����p�͎ʐ^�W�Ƃ��ďo�ł���Ă��܂��B������̂��̂ɁA���Ă̏㗬�K�������͂����܂ł����ƒm���A��Ԃ������Ă����Ƃ������Ƃ�������A�M�d�Ȏ����ƂȂ��Ă��܂��B |
|
 �wEros�x �wEros�x�����A�[���f�R�@�_�C�������h�@�u���[�` �C�M���X�@1920�N�� ¥5,500,000-�i�ō�10%�j |
����̏����̊��o�ł́A�z����y���ɒ����鐢�E�ł��B �ł��A�{���͂��̂悤�Ȑ��E���������Ƃ�������ƁA���̂悤�ȑf���炵�������݂��Ă��邱�Ƃ����R���D�ɗ����Ă����܂��B |
|
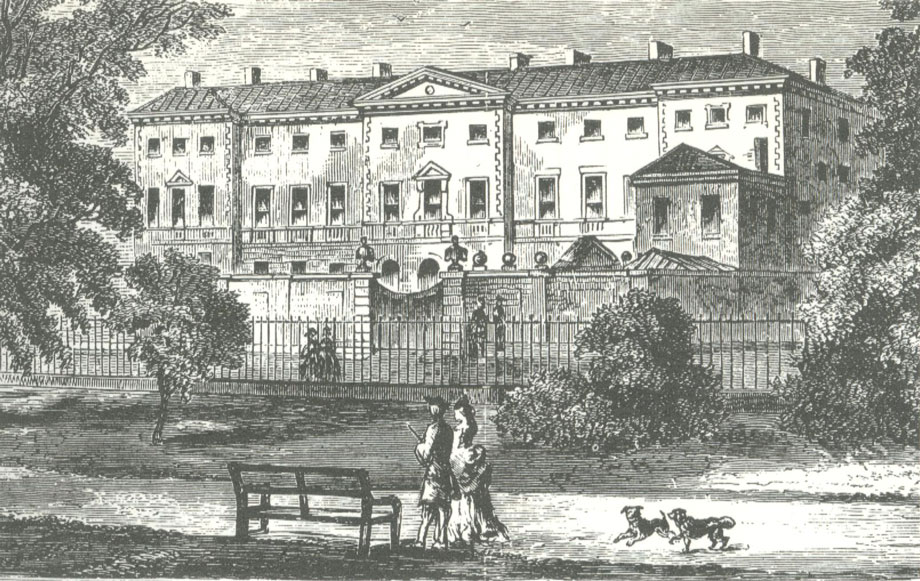 �f���H���V���[�E�n�E�X�i1800�N���j �f���H���V���[�E�n�E�X�i1800�N���j |
�M���̗��j�����݁A������n��o���Ă����f�{���V���[�E�n�E�X�ł����A1919�N�Ɏ������܂����B1910�N�Ƀ��C�h�E�W���[�W���l���\�Z��ʂ������Ƃ����Љ�܂����B ��ꎟ���E���i1914-1918�N�j�̌�A�����̋M���������h���̃^�E���n�E�X��������܂����B�����̑�9��f�{�{���V���[���݂́A�ꑰ�ŏ��߂đ����ł��x����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ȃ�܂����B���l���鏑���A�����h���̉��l����3�G�[�J�[�̒뉀�Ƌ��ɁA�f���H���V���[�E�n�E�X�͔��p����A1924�N�Ɏ���܂����B |
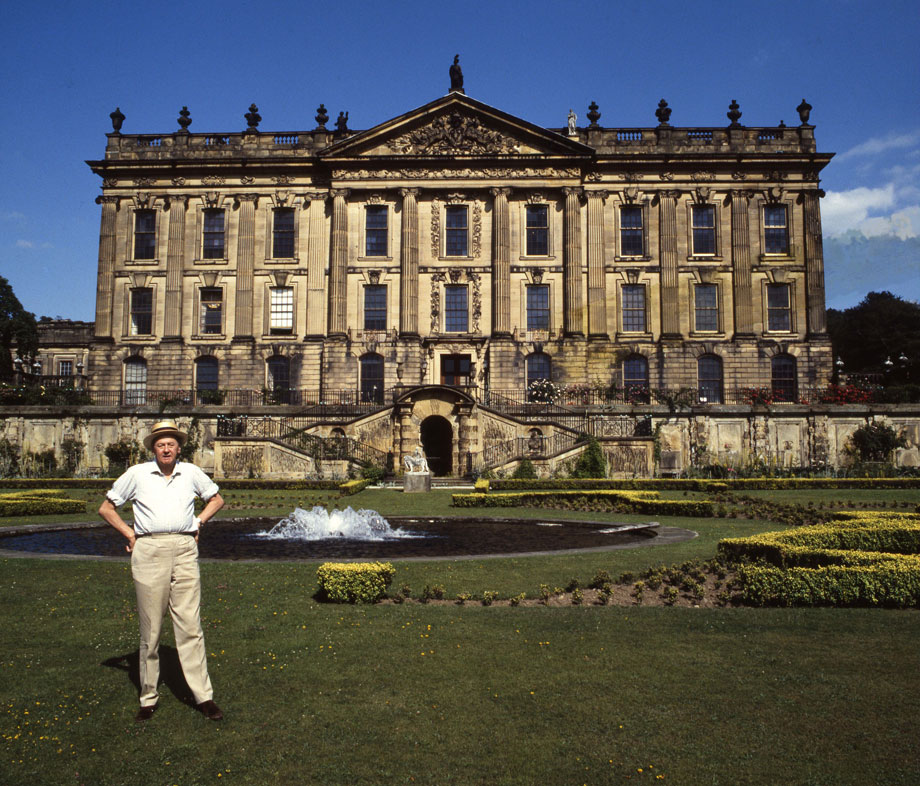 �`���b�c���[�X�E�n�E�X�Ƒ�11��f�{���V���[���݃A���h���[�E�L�����F���f�B�b�V���i1985�N�j �`���b�c���[�X�E�n�E�X�Ƒ�11��f�{���V���[���݃A���h���[�E�L�����F���f�B�b�V���i1985�N�j"The Duke of Devonshire at Chatsworth" ©Allan warren(1985)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |
���̌�A1950�N�ɑ�10��f���H���V���[���݂��S���Ȃ�A�A�g���[�����ɂ����ٓI�ȑ����ł̒������Ă��܂��܂����B ��11��f�{���V���[���݃A���h���[�E�L�����F���f�B�b�V���́A�ꑰ��400�N�ɓn���ďW�߂Ă����������p�i�̖w�ǂɉ����A�{�@�ł���`���b�c���[�X�E�n�E�X�ȊO�̑S�Ă̓y�n�p���邱�ƂɂȂ�܂����B �����Ƃł����Ă��A���̃C�M���X�M���͍��Ɍ�����@������L���Ă��Ă��ێ������Ő���t�B�ƂĂ��₩�ȃW���G���[��V�����A�V�������s�╶�������o���悤�ȗ]�T�Ȃ�ĂȂ��̂ł��B |
| �{�@���玸���Ē��ݕ�炵�ƂȂ������݉� | |
| �Z���g�E�I�[���o���Y���� | �����X�^�[���� |
 ����Z���g�E�I�[���o���Y���݃`���[���Y�E�{�[�N���[�N�i1670-1726�N�j1690�N�A20�� ����Z���g�E�I�[���o���Y���݃`���[���Y�E�{�[�N���[�N�i1670-1726�N�j1690�N�A20�� |
 ���ナ���X�^�[���݃W�F�[���Y�E�t�B�b�c�W�F�����h�i1722-1773�N�j1753�N�A31�� ���ナ���X�^�[���݃W�F�[���Y�E�t�B�b�c�W�F�����h�i1722-1773�N�j1753�N�A31�� |
�ʓ@�ǂ��납�{�@���܂߂��S�y�n�������A���ݏZ��ɕ�炷���݂��獡�ł͑��݂��܂��B�Z���g�E�I�[���o���Y���݂���X�^�[���݁A�ǂ�����R������M���ł����A�y�n�����L���Ă��܂���B �Z���g�E�I�[���o���Y���݂͑���E���O������ɍ������Ă���A1940�N�ɂ̓x�X�g�E�E�b�h�̓@��p���A�y�n�������Ȃ��M���ƂȂ�܂����B�݈ʎ��̂͏��L���Ă�����̂́A�`�F���V�[�̎؉ƏZ�܂��ŃT�����[�}���Ƃ��Đ��������Ă���A�w���Y�K���̌��݁x�ƌĂ��H�ڂɂȂ��Ă��܂��B �v�����ƂȂ鑊���ł�������邽�߁A�C�M���X�M���͐��O���^�Ȃǂő�悤�ɂȂ�܂����B�������Ȃ��炻�̔�����������ׂ��ׂ��A1975�N�ȍ~�͑��^�ł��������ꂽ�悤�ł��B |
|
2-2-2-2. ���M���̓����ɂ�鐬�����͂̊g��
 ����A�g���[���݃N�������g�E���`���[�h�E�A�g���[�i1883-1945�N�j1950�N�A67�� ����A�g���[���݃N�������g�E���`���[�h�E�A�g���[�i1883-1945�N�j1950�N�A67�� |
1945�`1951�N�̖�6�N�Ԃ̃A�g���[������98���݈̎ʂ̐V�݂���t����A�C�M���X�M���������鐬�����͂��v�X�͂����܂����B ����ŁA1946�`1954�N�̖�8�N�Ԃ̑����ł̍ō��ŗ�90%�Ƃ����ېłɂ��`���I�ȋM���͑�������œI�ȏւƊׂ�܂����B �������Ȃ���A����ɓO�ꂵ�ċM���̔j��͐i�߂��܂����B |
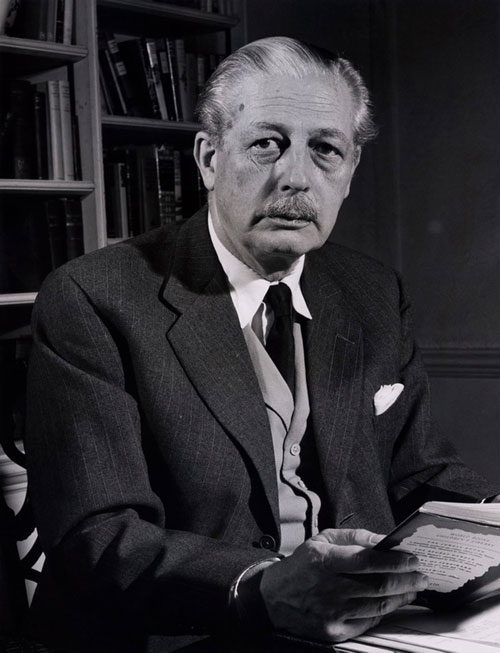 ����X�g�b�N�g�����݃n�����h�E�}�N�~�����i1894-1986�N�j1959�N�A65�� ����X�g�b�N�g�����݃n�����h�E�}�N�~�����i1894-1986�N�j1959�N�A65�� |
1957�`1963�N�̃n�����h�E�}�N�~���������ɂāA���M���Ɋւ���@�������肳��܂����B �w1958�N���M���@�x�ƌĂ�܂��B �ȑO������M���Ɋւ��Ă͋c�_���Ȃ���Ă��܂������A���̎��̖@���ɂ���Ĉ��M�̑n�݂��\�ƂȂ�܂����B ���P�M���̑n�ƂɕK�v�ȍ����������Ƃ͔��ɓ�����A���̖@���ɂ���Ď݈ʐV�݂̃n�[�h����������܂����B ���z���ʂ�A������O�̂悤�Ɏ݈ʂ̗������������܂����B |
| 1958�N���M���@�ɂ����M���C���� | ���M���͎̏����Ɋ�Â��A�����̒�����ɂ���ď��݂���܂��B "����"�͎ɂ��Ǝ����f�̏ꍇ������A���{����Ɨ������w�M���@�C���ψ���x�̐��E�Ɋ�Â����Ƃ�����܂��B ���h�ȐU�镑����v���ɂ���ď��݂����l�����ۂɂ���Ƃ͎v���܂����A�_���s�ܓI�ȏ��݂��Ȃ���邱�Ƃ͑z���ɓ����܂���B ���{�ɉ�����t������Ȃǂł̓|�X�g�������܂����A�M���̐��͐���������܂���B"�펯�͈͓̔�"�Ƃ����A����ӂ�Ȑ����ƂȂ�܂��B �ɂȂ�ɂ́A�J�l��R�l�͕K�{�ł��B�����Ǝ���������B�w�M���x�Ƃ����u�����h�~�����ɐ����͎x�����A�ƂȂ����łɂ͂��̖J���Ƃ��Ď݈ʂ�n���B |
|||
| �� | ���� | �C���� | �N���� | |
| �}�N�~���� | 1957-1963 | 46 | 9.2 | |
| �_�O���X���q���[�� | 1963-1964 | 16 | 16.0 | |
| �E�B���\�� | 1964-1970 | 122 | 20.3 | |
| �q�[�X | 1970-1974 | 58 | 14.5 | |
| �E�B���\�� | 1974-1976 | 80 | 40.0 | |
| �L�����n�� | 1976-1979 | 58 | 19.3 | |
| �T�b�`���[ | 1-79-1990 | 201 | 18.2 | |
| ���[�W���[ | 1990-1997 | 160 | 20.1 | |
| �u���A | 1997-2007 | 357 | 35.7 | |
| �u���E�� | 2007-2010 | 34 | 11.3 | |
| �L�������� | 2010-2016 | 243 | 40.5 | |
| ���C | 2016-2019 | 43 | 14.3 | |
| �W�����\�� | 2019-2022 | 87 | 29.0 | |
| �g���X | 2022 | 3 | 3.0 | |
| �X�i�N | 2022- | 26 | 26.0 | |
| ���v | 1,534�l | ����23.6 | ||
���͊�Ղ��s����ȎقǁA���݈ʂ𗐔������ł��傤���B �u���^�X���g���X�ɏ����v�Ȃǝ��������قǒ��Z���ɏI��������Y�E�g���X�ł����A���C����܂ł̋͂�45���̊Ԃ�3�l���̈��M����C�����Ă��܂��B ���̐��x�͂��������Ȃ���ۂł��B�˔@���������ɂȂ��������ł��A���h�ȍs���ɓw�߂悤�Ƃ���l�͂��܂��B���������l�����݂���ꍇ�͗ǂ��ł����A���̂������Ə��ݑΏۂ͖�S�������A�݈ʁi�u�����h�E���Ёj�~�����ɎɎC����^�C�v�̐��������ł��B ���������킯�ŁA����̃C�M���X�M���̒��g�͂��̑�����"��S���炯�̐���"�ƌ��邱�Ƃ��ł��܂��B |
2-2-2-3. ���M���̓����ɂ���Ăقڕs�\�ƂȂ��������̏���
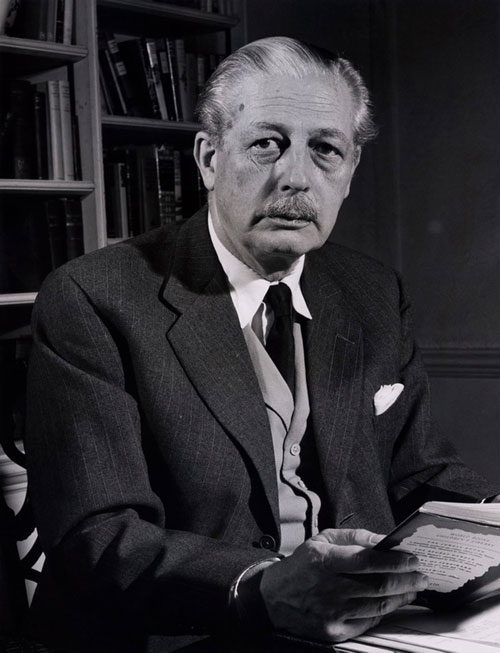 ����X�g�b�N�g�����݃n�����h�E�}�N�~�����i1894-1986�N�j1959�N�A65�� ����X�g�b�N�g�����݃n�����h�E�}�N�~�����i1894-1986�N�j1959�N�A65�� |
�w1958�N���M���@�x�𐧒肵���n�����h�E�}�N�~������1984�N�A90�̎��ɃX�g�b�N�g�����݂����݂��܂����B �b���ɗ^����ꂽ���P�M���݈ʂƂ��ẮA�Ō�݈̎ʂƂȂ�܂��i2023�N3��30�����݁j�B �ȍ~�̐V�݂͈��M���݂̂ł��B |
 �w4 FACES�x �w4 FACES�x�t�H�[�E�F�C �E�H�b�`�L�B�E�y���_���g �C�M���X�@1830�`1840�N�� ¥255,000-�i�ō�10%�j |
�C�M���X�M���ɂ͓Ɠ���"�C�M���X�M��"�炵��������܂����B ����͍��������ŊȒP�ɐg�ɂ�����̂ł͂���܂���B�����N���������ď������ꂽ���̂ł��B �ŏ��͐����������Ƃ��Ă�����d�ˁA100�N�A200�N�ƌo�����ɐ�������M���炵���Ȃ��Ă����ƌ����܂��B �܂��A�����������Ă��K�������~�������̂���ɓ���Ƃ͌���܂���B |
|
 �wMIRACLE�x �wMIRACLE�x�G�h���[�f�B�A���@�u���b�N�I�p�[���@�y���_���g �C�M���X�@1905�`1915�N�� ¥10,000,000-�i�ō�10%�j |
�H�����������A�B�ꖳ��̔��p�i�Ȃǂ̏ꍇ�A��ɓ������`�����X�������܂��B �����炱����X�A�x�ƌ��͂��ێ����ė����Ƃ��������l����������p�i�����L���邱�Ƃ��ł���̂ł��B |
���P�M���͂܂Ƃ��ɍ��Y���ێ��ł��Ȃ��Ȃ�E�E�B ����d�˂�ΐ�������Ă����\��������ƌn�ł��A��サ���݈ʂ������ł��Ȃ���ΐ����̂܂܁B �M���Ȃ�ł͂̋M���炵�����������B�ł�����́A�����Ƃ����̐̂Ɏ����Ă���̂ł��B |
2-2-2-4. ���S�ɏ�����ꂽ�M���@
�N���̎��ł��A�ĂыM���̎�ɗ͂����߂���\���͂���ł��傤���B ��������͖��������ł��B 1885�N�ȍ~�A���P�M���͉����������Ĉ�ؑn�݂���Ă��܂���B�b�����������͎̂�����A���M���݂̂ƂȂ��Ă��܂��B |
���P�M���͑����邱�ƂȂ����R���̓���˂��i�ނ݂̂ł������A���M���͖҃X�s�[�h�Ő��𑝂₵�Ă����܂����B2022�N�ɂ͈��M����1,504�l�ɒB���܂����B2023�N3�����_�ł̐��P�M���̐���807�Ƃł��B���͂␔�ł����|���Ă��܂��B ���ꂾ���ł͂���܂���B���P�M���͂���ɋM���@�ł̗͂��D���Ă��܂��B |
 �g�j�[�E�u���A�i1953�N-�j2002�N�A49�� �g�j�[�E�u���A�i1953�N-�j2002�N�A49�� |
�u���A�̐��ʂƂ��ẮA���̂悤�Ɍ����Ă��܂��B �u�����O�ߑ�I�E�����I�Ȋ��K��x���c�����Ă����M���@�̐��P�M���c�Ȑ��̐����ƍō��ٔ����̌����Ɨ��Ƃ��������v�𐬂������A�ߑ�I�Ȍ��͕������̊m����B�������B�v ���͌����悤�B�����̉��v�͎��_�ɂ���ĉ��߂��ς���Ă���Ƃ������܂��B 1999�N�Ɂw�M���@�@�x�����肳��܂����B |
 18���I�����̃C�M���X�M���@�i�s�[�^�[�E�e�B���}���X�@1708-1714�N���j���C�����E�R���N�V���� 18���I�����̃C�M���X�M���@�i�s�[�^�[�E�e�B���}���X�@1708-1714�N���j���C�����E�R���N�V���� |
�]���A���P�M���͑S�����M���@�̋c�Ȃ錠��������܂����B �܂��A���M���������I�ɋM���@�̋c�Ȃ��^�����܂��B 1999�N�̋M���@�@�ɂ��A�M���@�c���̐��P�M���g��92�c�Ȃɐ������܂����B |
 �p���c��c���� "British Houses of Parliament" ©Maurice from Aoetermeer, Netherlands(27 July 2008, 40:47)/Adapted/CC BY 2.0 �p���c��c���� "British Houses of Parliament" ©Maurice from Aoetermeer, Netherlands(27 July 2008, 40:47)/Adapted/CC BY 2.0 |
||||
| �����@ | �M���@ | |||
| �M�� | ���M�� | ���P�M�� | ||
| 1999�N10�� | 650�c�� | 1330�c�� | 577�c�� | 753�c���i�M���@��57%�j |
| 2000�N6�� | 650�c�� | 669�c�� | 577�c�� | 92�c���i�M���@��14%�j |
���̌��ʁA�M���@�ʼnߔ������߂Ă������P�M���̗͍͂킪��A14%��̔��������������Ȃ��Ȃ�܂����B���M����86%�̔������������A���͂┼�X�ŋc�_���킹��悤�Ȃ��Ƃ͕s�\�ƂȂ�܂����B���̏�Ԃŕ������Ƃ́A�����s�\�ł��B �����ƌ����ǂ��A�c���ƂȂ��̂̓C�M���X�����{���l��"���ʂ̐l"�ł͂Ȃ��A"�㋉����"�̂悤�Ȑl�����ł��傤�B�J�l��R�l����������p���[�E�G���[�g�w�ƌ����܂��B���M���������悤�Ȃ��̂ŁA������p���[�E�G���[�g��"�M��"�u�����h��t���������ƌ��邱�Ƃ��ł��܂��B �����ʂɉ����Ă��A�]���̋M���͂�������͂��������ƌ����܂��B 1999�N�ɐ��肳�ꂽ�w�M���@�@�x�̌�����Ƃ��ẮA�u�����ς��c�̊���ƒn�ʂɊ�Â������̐��P�M�����A�����M���̉ƌn�ɐ��܂ꂽ�Ƃ��������œ����ĉ��v��j�Q����͖̂��ł���B���̌o���Ǝ��тɂ��M���ɏ����ꂽ���M�����哱�ł���M���@�ɂ���B�v�Ƃ���Ă��܂��B �ꌩ����ƕ������͗ǂ��̂ł����A�悭�悭�l����Ɨl�X�Ȗ����z���ł��܂��B �����Ă��������Ő���t�̏�Ԃł��鐢�P�M�������Ȃ����Ȃ�����A�m�u���X�I�u���[�W���̐��_���ǂ��܂ŕۂĂĂ��邩�͕�����܂���B�����A���܂�Ȃ���ɒn�ʂ����҂ł���A����オ�邽�߂Ɍ��d�p���菄�炵�A���C�o����@�����Ƃ��ĂĂł����������̂��߂ɓ����Ƃ������Ƃ͂��܂���B ���M���͒N�̂��߂ɓ����ł��傤���B��x���݂���ΏI�g�ł����A�q���Ɏ݈ʂ͌p���͂ł��܂���B����オ��ł�����M���́A���̌���m�ł���n�ʂ�z���~�����A�ꑰ�̗͂��m�ł�����̂ɂ��邽�߂ɓ����ł��낤���Ƃ͗e�Ղɑz���ł��܂��B 2000�N��ɓ���A�C�M���X�͏����ɂƂ��čK���ȍ��ƂȂ����ł��傤���B�m�荇���̃C�M���X�l�������A�̂̊y�����v���o�Ƌ��ɁA���̕�炵�ɂ�����s��ɋ�s���܂����B�u���{�͂ʂ邭�ėǂ���ˁA�V��͓��{�ɈڏZ���悤���ȁB�v�Ƃ̂��Ƃł����B ���{�̕����ŗ��������Ȃ��ł����A����Ə��q�������Ȃ荓���A��S���c�����Ă��Ȃ���Ԃł̃R�����g��������܂���B�����A���ꂾ���ǂ��Ȃ��̂悤�ł��B �����ɂƂ��āA�����čK���ȍ��ɂ͂Ȃ��Ă��܂���B"���ʂ̏���"��A�����̂��Ƃ�z����M���ł͂Ȃ��A���������ǂ���Ηǂ�"��������"�������J�l�ƌ��͂����������ʂ����Ƃ������Ƃł��傤�B |
||||
2-3. 20���I�����̃n�C�W���G���[�s��
�����̐��̒��ɂȂ��Ă���́A�W���G���[�͕ω��ɖR�����ł��B���͓I�ȐV�����f�ނ����s�邱�Ƃ��Ȃ��A�f�U�C�����A�C�f�A���o�s�����A�R�X�g�J�b�g�����`�ɂ����Ȃ���f�U�C�����g����A�����Ȃ����̈��z�ł��B �{���A�n�C�W���G���[�͎��ゲ�Ƃɕω����Ă��܂����B�����炱���N��̐�����\�ł��B |
 |
���́̕A20���I�����̃G�h���[�f�B�A���ɐ��삳�ꂽ���̂ł��B |
2-3-1. ���s����ɂ��f�U�C���I�ɍł��p���t���Ȏ���
| ���[���b�p�̃n�C�W���G���[�E�f�U�C���̐i�� | |||||||
| ����M���̎��� | ��O�i�����j�̎��� | ||||||
| �A�[�c�� �N���t�c |
���_���X�^�C�� | �G�h���[�f�B�A�� | �A�[���f�R | �C���^�[�i�V���i���E�f�U�C�� | |||
| �O�� | ��� | ||||||
 1880�N�� 1880�N�� |
 1900-1910�N�� 1900-1910�N�� |
 1910�N�� 1910�N�� |
 1920�N�� 1920�N�� |
 1930�N�� 1930�N�� |
 1930�N�� 1930�N�� |
 1940�N�� 1940�N�� |
 2019�N 2019�N�y���p�zBOUCHERON HP / WOLF BROOCH |
���{�̊J���́A���m���p�ɋ}�����傫�ȕω��������炵�܂����B���ɉe�������̂��w��ȋ{�앶���x�ł͂Ȃ��A���[���b�p�ɂ͗ގ��̂��̂����݂��Ȃ������w�V���v���E�C�Y�E�x�X�g�̕��ƕ����x�ł����B �ŏ��̓A�[�c&�N���t�c�̂悤�ɁA���{���p�̎��"�v�f"������������銴���ł����B����ɃX�^�C�����̂��̂��e������悤�ɂȂ�A20���I�ɓ���ƈ�C�ɗZ���E�����i�݁A�ŏI�I�ɂ͖����Ђ́w�C���^�[�i�V���i���E�f�U�C���x�Ɏ���܂��B ����M���̎��ォ���O�̎���ֈڍs����ƁA���X�Ƀ`�[�v���ƁA�Ȏ��Ȍ����~�������Y�������f�U�C���F�����߂Ă����܂��B |
|||||||
| ����M���̂��߂̃n�C�W���G���[�E�f�U�C���̐i�� | |||||
| �A�[�c�� �N���t�c |
���_���X�^�C�� | �G�h���[�f�B�A�� | �A�[���f�R | �C���^�[�i�V���i�� �f�U�C�� |
|
| �O�� | ��� | ||||
 1880�N�� 1880�N�� |
 1900-1910�N�� 1900-1910�N�� |
 1910�N�� 1910�N�� |
 1920�N�� 1920�N�� |
 1930�N�� 1930�N�� |
 1930�N�� 1930�N�� |
19���I�������20���I�����ɂ����ẮA�n�C�W���G���[�̃f�U�C���̕ω��͋}���ł����B�ŏI�I�ɂ̓A�[���f�R�E�f�U�C���ւƎ������܂��B����f�U�C���̓A�[���f�R�ȍ~�i�����Ă��炸�A���_���f�U�C���Ƃ��Ē蒅���Ă���Ƃ������Ă��܂��B ����̃f�U�C���́w�V���v���E�C�Y�E�x�X�g�x�ł͂Ȃ��A���ۂ̏��̓R�X�g�J�b�g�����`�ɂ���ĕK�v�ȕ����܂ō킬���Ƃ��Ă��܂����A�ȑf���n���ȃf�U�C���ł��B�`�[�v����������̂͂��̂����ł��B �A�[���f�R����ȍ~�̃f�U�C���́A����l�����Ă���a�����Ȃ��Ǝv���܂��B�Â��������Ȃ��ǂ��납�A���܌��Ă������I�ɂ��犴����̂́A�f�U�C����K�v�ȗv�f�͍킬���Ƃ��ꂸ�ɂ�����Ƒ��݂��邩��ł��B |
|||||
| 20���I�����̃��[���b�p�̃f�U�C���̋}���ȕω� | |||
| 20���I�����i�G�h���[�f�B�A���j | �A�[���f�R | ||
| �v���`�i�o�꒼�O | �v���`�i�o��� | �O�� | ��� |
 1900�`1905�N�� 1900�`1905�N�� |
 1910�N�� 1910�N�� |
 1920�N�� 1920�N�� |
 1930�N�� 1930�N�� |
���_���f�U�C���ւƒʂ���A�[���f�R�܂ŁA�����Ƃ����Ԃł����B���̋͂��Ȋ��ԁA�f�U�C���̖ʂł����[���b�p�e���ŗl�X�Ȏ��s���낪�s���܂����B���Ƀp���t���Ȏ��ゾ�����ƌ����A�G�h���[�f�B�A������A�[���f�R�����ɂ����Ă͋����悤�Ȗ��͓I�ȃf�U�C�������������ݏo����Ă��܂��B |
|||
2-3-2. �G�h���[�f�B�A���̐�i�I�f�U�C��
 |
���͕̕���V�R�^��ƃg�����W�V�����J�b�g�E�_�C�������h�����ꂼ��1�����́A�ꌩ����ƂƂĂ��V���v���ȃf�U�C���Ɍ����܂��B �������Ȃ���A���ۂ͂ƂĂ������I�ŃI�V�����ł��B ���̎���Ȃ�ł͂̃f�U�C���ƌ����܂����A���̂悤�ȓ������������f�U�C���̓G�h���[�f�B�A���E�W���G���[�̒��ł��ƂĂ��������ł��B �s�A�X�ł͏��߂Č��܂����B |
 �wShining White�x �wShining White�x�G�h���[�f�B�A���@�_�C�������h�@�l�b�N���X �C�M���X or �I�[�X�g���A�@1910�N�� SOLD |
�G�h���[�f�B�A���̃f�U�C���ƕ����āA�ǂ̂悤�ȃf�U�C����z�������ł��傤���B ���̎���̃n�C�W���G���[�ɂ�"�v���`�i�ɃS�[���h�o�b�N"�Ƃ��������I�ȍ�肪���邽�߁A�f�U�C���l�����̎�ށA�J�b�g�Ȃǂ������邱�ƂȂ��w�G�h���[�f�B�A���E�W���G���[�x�ł��锻�f���邱�Ƃ��\�ł��B ����̂ɁA���x�Ȑ��m���⊴�o�������Ȃ��Ă��G�h���[�f�B�A���E�W���G���[�Ɣ��ʂł��܂����i��������t��ɂƂ����t�F�C�N�E�W���G���[�����ɑ��݂��܂��j�B ���̂悤�ȗ��R�ɂ��A����܂ŃG�h���[�f�B�A���̃f�U�C���ɂ��ĐG���l���w�ǂ��Ȃ������悤�ɂ��v���܂��B |
�܂��A���ꂾ���ł͂���܂���B����̍Ő�[�f�U�C�������f�����̂́A�㗬�K���̂��߂ɍ��ꂽ����ꂽ�n�C�E�W���G���[�݂̂ł��B��������40�N���邨��舵�����т����邩�炱���AHERITAGE�ɂ̓J�e�S���C�Y����ɑ���f�[�^������Ƃ������܂��BGen�������ǂ�����ł��܂����AGen�͓��Ƀf�[�^���W�A���͕��͂����ӂƌ����邩������܂���B |
| ���l���ɕx�ރG�h���[�f�B�A���̃W���G���[�E�f�U�C�� | |||
| �A�[�c&�N���t�c�̌n�� | ���[���b�p�� �`���X�^�C���̌n�� |
�A���O���E�W���p�j�[�Y�E�X�^�C���̌n�� | |
| �A�[���k�[���H�[�n | �K�[�����h�X�^�C���n | ���_���X�^�C���` ���[�Q���g�V���e�B�[���n |
�A�[���f�R�ɂȂ���n |
 �wMIRACLE�x �C�M���X�@1905�`1915�N�� ¥10,000,000-�i�ō�10%�j |
 �w�i���̈��x �w�i���̈��x�_�C�������h �y���_���g���u���[�` �t�����X�H�@1910�N�� ��1,220,000-(�ō�10%) |
 �wREBIRTH�x �wREBIRTH�x�Z�Z�b�V�����i�E�B�[�������h�j�@�l�b�N���X �I�[�X�g���A�@1905�`1910�N�� SOLD |
 �V�R�^�쁕�_�C�������h �u���[�` �V�R�^�쁕�_�C�������h �u���[�`���[���b�p�@1910�N�� SOLD |
�S�Ă�ԗ����Ă���킯�ł͂���܂��A�G�h���[�f�B�A���̃f�U�C���ɂ͂��̂悤�ȃJ�e�S���[������܂��B�f�U�C���͐V�����v�f��������Ȃ���i�����܂��B �ŏI�I�ɂ��A���O���E�W���p�j�[�Y�E�X�^�C���̌n����g�ރV���v���E�C�Y�E�x�X�g�n�̃f�U�C�����A�A�[���f�R�ւƂȂ����Ă����܂��B ��������Ď������Ă����O�ł���G�h���[�f�B�A���́A�{���ɗl�X�ȃf�U�C�������s����Ő��ݏo����܂����B����͂̕��̒��ł��A���_���X�^�C�����烆�[�Q���g�V���e�B�[���n�ɑ�����f�U�C���ƌ����܂��B4�̃J�e�S���[�̒��ł́A�ł��s��Ō��鐔�����Ȃ��n���ł��B |
|||
3. �M���̃v���C�h����������ӎ��̍s���͂������
3-1. �����I�ȍŐ�[�f�U�C��
 |
����z�����A�s�v�c�Ȃقǖ����I�ȃf�U�C���́A���_���X�^�C����Z�Z�b�V�����n�̃W���G���[�̓����ł���ő�̖��͂Ƃ������܂��B |
3-1-1. �A���O���E�W���p�j�[�Y�E�X�^�C�����甭�W�������[���b�p�E�f�U�C��
| �C�M���X�Ŕ��B�����A���O���E�W���p�j�[�Y�E�X�^�C���̃f�U�C�� | ||
 �N���X�g�t�@�[�E�h���b�T�[�i1834-1904�N�j �N���X�g�t�@�[�E�h���b�T�[�i1834-1904�N�j |
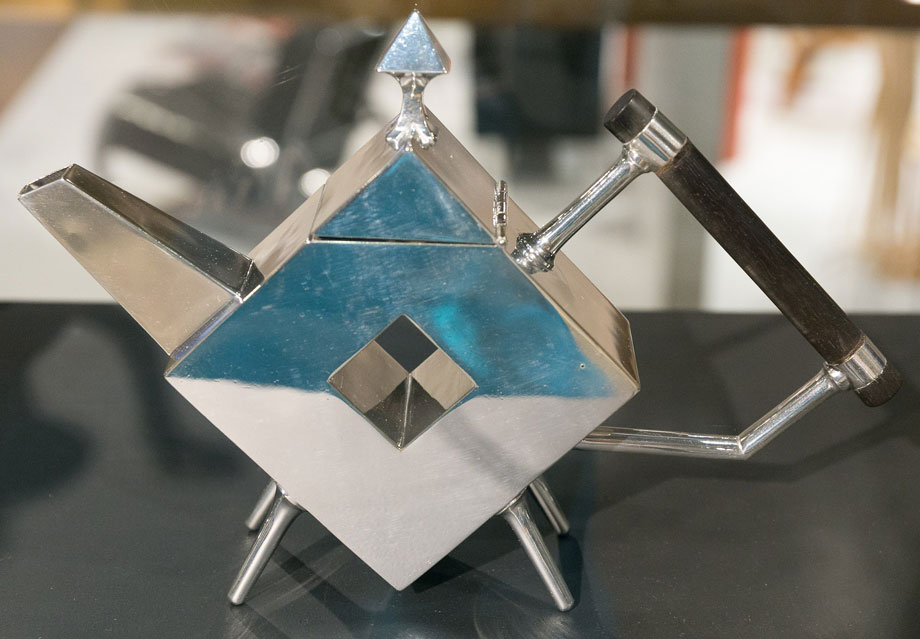 �wThéière�x�i�N���X�g�t�@�[�E�h���b�T�[�@1879�N�j�����g���I�[�����p�� �wThéière�x�i�N���X�g�t�@�[�E�h���b�T�[�@1879�N�j�����g���I�[�����p�� |
 �w�p���M���̓���x �w�p���M���̓���x�V�R�^�쁕�g���R�@�����O �o�[�~���K���@1876�`1877�N SOLD |
�C�M���X�̓����h�������Z�̒��S���������Ƃ�����A���p�����������p������i�j�̃t�����X�̂悤�Ƀt�@�b�V������|�p�Ȃǂ�PR�ɂ��܂�͂����Ă��炸�A�|�p�ʂŐ�s���Ă�����ۂ����܂�Ȃ���������܂���B �������Ȃ���C�M���X�͊J���������{�̔��p�l������������������A�f�U�C���̐i�����N����܂����B�����ׂ����ƂɁA1870�N��ɂ͊��ɃA�[���f�R�̂悤�ȃf�U�C�������ݏo����Ă��܂��B���̍��̃t�����X���c��i�|���I��3����p�ʂɂ��ċ��a���Ɉڍs������A�����푈�ŕ��������ŃS�^�S�^���Ă������ł��ˁB ���ƂȂ�l���������o��������N���X�g�t�@�[�E�h���b�T�[�Ƃ����f�U�C�i�[�ŁA�C�M���X�Ŕ��W�����A���O���E�W���p�j�[�Y�E�X�^�C���̎�v�l���Ƃ���Ă��܂��B |
||
3-1-1-1. �C�M���X�����ł̃��_���X�^�C���ւ̐i��
 �w���H�̖����x�i�`���[���Y�E���j�[�E�}�b�L���g�b�V���@1892�N�j �w���H�̖����x�i�`���[���Y�E���j�[�E�}�b�L���g�b�V���@1892�N�j |
�A���O���E�W���p�j�[�Y�E�X�^�C��������Ƀ��_���X�^�C���i���������̂��A�O���X�S�[�h�̃}�b�L���g�b�V���v�Ȃ������ƌ����܂��B �V�������̂ݏo���ɂ͎��s���낪�K�v�ł��B �}�b�L���g�b�V���̍�i�������́A�����̃��}���ɓ��ꂽ�E�B���A���E�����X�̃A�[�c���N���t�c�̉e�����A�̋��X�R�b�g�����h�̓`���ł���Ñ�P���g���p�̑��`���Ȃǂ������ꂽ���z�I�ȋȐ�����������Ƃ��܂����B |
| �}�b�L���g�b�V���v�Ȃ̓����I�ȍ�i | |
 �y�Q�l�z�`���[���Y�E���j�[�E�}�b�L���g�b�V���̃f�U�C���̃`�F�A �y�Q�l�z�`���[���Y�E���j�[�E�}�b�L���g�b�V���̃f�U�C���̃`�F�A |
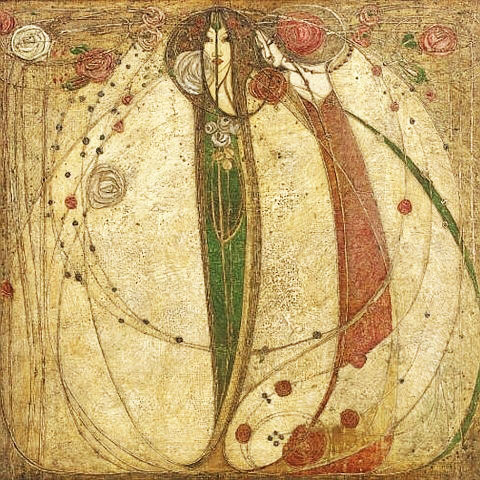 �w�����o���ƐԂ��o���x�i�}�[�K���b�g�E�}�N�h�i���h�E�}�b�L���g�b�V���@1902�N�j2008�N�̃I�[�N�V�����Ŗ�3.6���~ �w�����o���ƐԂ��o���x�i�}�[�K���b�g�E�}�N�h�i���h�E�}�b�L���g�b�V���@1902�N�j2008�N�̃I�[�N�V�����Ŗ�3.6���~ |
�������獑���Ŕ��B���������A���O���E�W���p�j�[�Y�E�X�^�C����������A�j���I�Œ����I�ȕv�`���[���Y�̃X�^�C���ƁA�ȃ}�[�K���b�g�̋Ȑ��I�ȃ��C����o���Ȃǂ̏����I�ȗv�f���g�ݍ��킳�邱�ƂŁA�A���O���E�W���p�j�[�Y�E�X�^�C���Ƃ͈قȂ�Ǝ��̃f�U�C���ɐi�����܂����B |
|
 �E�B���A���E���b�g�̂��߂̃T�C�h�{�[�h�i�G�h���[�h�E�E�B���A���E�S�h�E�B���@1876-1877�N�j �E�B���A���E���b�g�̂��߂̃T�C�h�{�[�h�i�G�h���[�h�E�E�B���A���E�S�h�E�B���@1876-1877�N�j"Godwinsideboard" ©VAwebteam at English Wikipedia(26 OAugust 2008)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |
���ƕ����̃V���v���E�C�Y�E�x�X�g�������ꂽ�A���O���E�W���p�j�[�Y�E�X�^�C����A�[���f�R�́A�j���I�Ȉ�ۂ������ł��B�܂��A�w���Ƒ��x�Ƃ��Ă��A���@���̋����e���������{�Ɖ��Ɋ���e����ł������{�l�́A�����̗l�������Ă���a���Ȃ�����邱�Ƃ��ł��܂��B ���̈���ŁA"�V���ȋ����⊴��"�Ƃ����̂͂��܂芴�����Ȃ���������܂���B |
 �E�B���[�E�e�B�[���[���Y�́w�����̊ԁx�Č��i�}�b�L���g�b�V���̃f�U�C�� 1903�N�j �E�B���[�E�e�B�[���[���Y�́w�����̊ԁx�Č��i�}�b�L���g�b�V���̃f�U�C�� 1903�N�j"Room de Luxe" ©Dave souza(10 March 2006)/Adapted/CC BY-SA 2.5 |
������̌|�p�Ƃ�������w�V�ˁx�Ə̂��ꂽ�A�}�[�K���b�g�E�}�N�h�i���h�E�}�b�L���g�b�V���Ɠ��̏����I�Ȋ�������荞�ނ��ƂŁA�f�U�C���͋����ׂ��i���𐋂��܂����B �ꌩ����ƃA���O���E�W���p�j�[�Y�E�X�^�C����A�[���f�R�Ƒ傫���ς��Ȃ��悤�Ɍ����܂����A�s�v�c�Ȃقǖ����I�ŁA�������D�����S�n�悳����������̂ł��B |
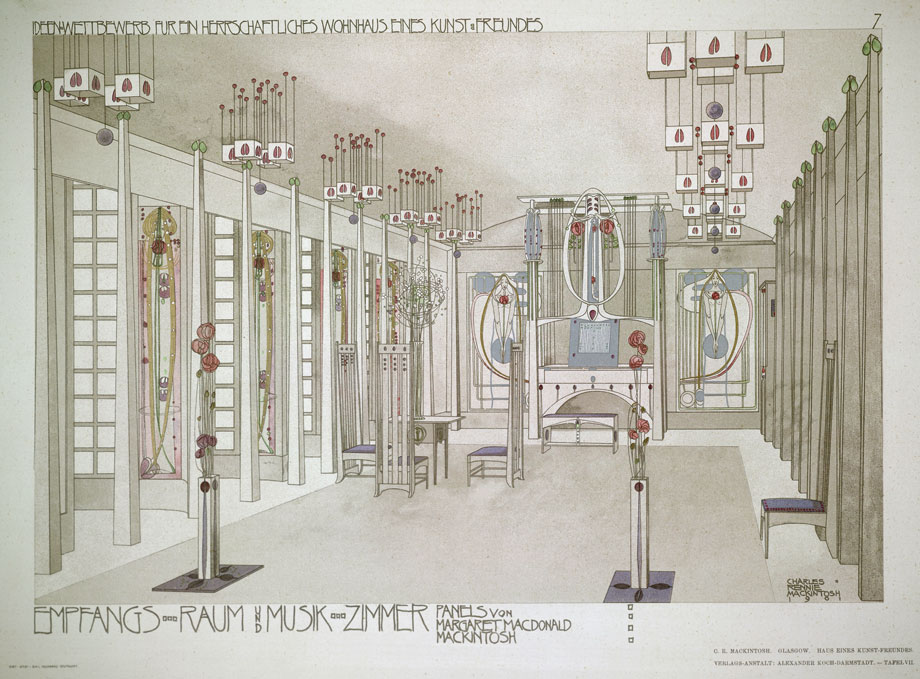 �w�|�p���D�Ƃ̂��߂̉��y���x�̃f�U�C���i�}�b�L���g�b�V���v�ȁ@1901�N�j �w�|�p���D�Ƃ̂��߂̉��y���x�̃f�U�C���i�}�b�L���g�b�V���v�ȁ@1901�N�j |
�`�ł�������A�F�g���ł�������B �܂����B�N�g���A���̏d���Ȓ��x�i�ň��Ă�������B1900�N���̍�i���Ȃ�ĉ₩�ɂ͐M����قǁA���܌��Ă������I�Ȉ�ۂł��B |
| ���_���X�^�C���̃n�C�W���G���[ | ||
 �wMODERN STYLE�x �wMODERN STYLE�x�_�C�������h �S�[���h �u���[�` �C�M���X�@1890�N�� SOLD |
 �wWILDLIFES�x �wWILDLIFES�x�V�R�^�� �S�[���h �y���_���g �C�M���X�@1900�N�� SOLD |
 �wSTYLISH PINK�x �wSTYLISH PINK�x�s���N�g���}���� �y���_���g �C�M���X�@1900�N�� SOLD |
�������̔��A�Ɠ��̊Ԃ̎����i��Ԏg���j�A���E��Ώ̂Ȃǂ̃o�����X�B������w�B �V���v���E�C�Y�E�x�X�g�Ƃ������{�Ɠ��̔��p�l���͍݂���A�Ǝ��̊�������������A��������ƗZ���E�������w���_���X�^�C���x�͋������͂�����܂��B Gen�Ɂu�A���e�B�[�N�W���G���[�͂��ꂼ��̎���Ɍ��o�����f�U�C�������邯�ǁA�ǂ̗l������ԍD�����ƕ����ꂽ��A���̓}�b�L���g�b�V���̃��_���X�^�C������ԍD�݁B�v�ƌ�������AGen���l���ƌ����A�u���������A�J�삳����}�b�L���g�b�V�����D���ƌ����Ă����Ȃ��B�v�Ǝv���o���Ă��܂����B �J�삳���Gen�̖��F�ɂ��āA���{���̃O���X�A�[�e�B�X�g�Ȃ̂������ł��B�x���r�[�ԍ�ɂ��X���o���������Ȃ��ł�����������l�ŁA�s�^�ɂ�2�l���Ă������炩��ɂȂ��Ă��܂����n�R����ɂ͈ꏏ�Ƀo�^�[�ݖ����т�H�ׂāA���ꂪ�ƂĂ������������������ł��i�j |
||
| 1900�N�O��Ɍ݂��ɉe�������������C�s�̃f�U�C�i�[���� | |||
| �C�M���X�̃��_���X�^�C�� | ���I���E�B�[���̃Z�Z�b�V���� | ||
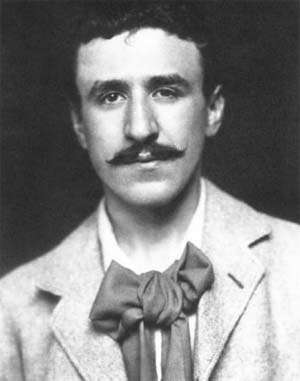 �`���[���Y�E���j�[�E�}�b�L���g�b�V���i1868-1928�N�j �`���[���Y�E���j�[�E�}�b�L���g�b�V���i1868-1928�N�j |
 �}�[�K���b�g�E�}�N�h�i���h�E�}�b�L���g�b�V���i1864-1933�N�j �}�[�K���b�g�E�}�N�h�i���h�E�}�b�L���g�b�V���i1864-1933�N�j |
 ���[�[�t�E�z�t�}���i1870-1956�N�j1902�N�A32�� ���[�[�t�E�z�t�}���i1870-1956�N�j1902�N�A32�� |
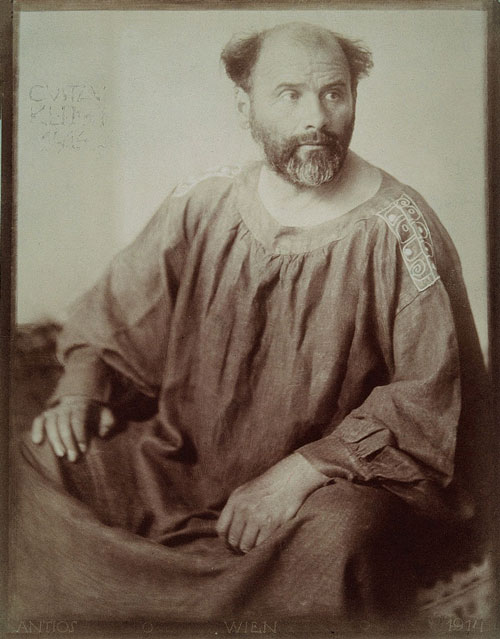 �O�X�^�t�E�N�����g�i1862-1918�N�j1914�N�A52�� �O�X�^�t�E�N�����g�i1862-1918�N�j1914�N�A52�� |
����͂��Ă����B100�N�ȏ�̎����Ď������𖣗����郂�_���X�^�C���̓V�˃f�U�C�i�[�v�Ȃ́A������Ɋ����A�[�e�B�X�g�����ɂ�����ȉe����^���܂����B �����Ƃ��Ă͐�i�I�߂��āA�C�M���X�����ł͖w�Ǘ�������Ȃ��������_���X�^�C���ł������A���p�H�|���wTHE STUDIO�x��ʂ��Ă��̑��݂�m�����Z�Z�b�V������1900�N�̃Z�Z�b�V�����W�ɕv�Ȃ�����҂��܂����B |
|||
3-1-1-2. �I�[�X�g���A�ɉ�����f�U�C���̐i��
 �wREBIRTH�x �wREBIRTH�x�Z�Z�b�V�����i�E�B�[�������h�j�@�l�b�N���X �I�[�X�g���A�@1905�`1910�N�� SOLD |
�Z�Z�b�V�����i�E�B�[�������h�j�ɂ��Ă͈ȑO���������܂����B �Z�Z�b�V�����͏]���̃I�[�\�h�b�N�X�ȃ��C���X�g���[������͗��E�i�����j�����A�����Ƃ��Ă͐�i�I�ňْ[�̑��݂������ƌ����܂��B |
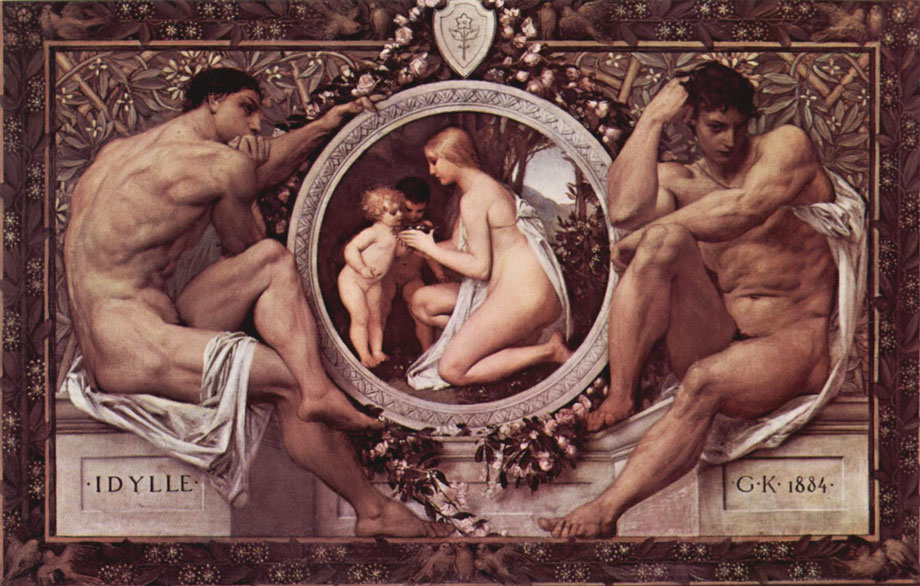 �wIdylle�i�C�f�B�[���F���j�x�i�O�X�^�t�E�N�����g�@1884�N�j �wIdylle�i�C�f�B�[���F���j�x�i�O�X�^�t�E�N�����g�@1884�N�j |
�N�����g�������A22���̍�i�͂���Ȋ����ł��B�ƂĂ����ł͂�����̂́A��������̗D�ꂽ�|�p�Ƃ����̒��ł����g�ɏO�ڂ��W�߂�قǂ̓��������邩�ƌ����A�����܂ł͊����܂���B |
 �Z�Z�b�V�����فi�����h��فj�i1897-1898�N�j �Z�Z�b�V�����فi�����h��فj�i1897-1898�N�j"Secession Vienna June 2006 005" ©Gryffindor(June 2006)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |
1898�N����A�Z�Z�b�V�����W���J�Â���܂����B |
| ��6��i1900�N�j�Z�Z�b�V�����W�w���{���p�x��S���������[�U�[ | |
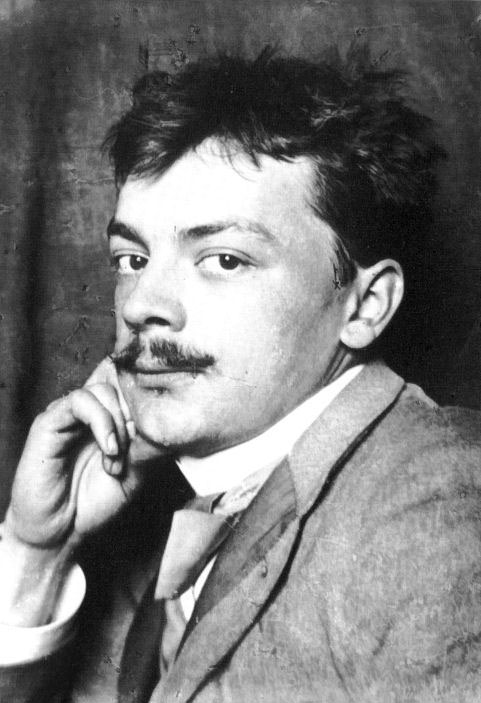 �R���}���E���[�U�[�i1868-1918�N�j �R���}���E���[�U�[�i1868-1918�N�j |
 ��؍H�̃A�[���`�F�A�i�R���}���E���[�U�[�@1900�N�j���T���[���X�E�J�E���e�B���p�� ��؍H�̃A�[���`�F�A�i�R���}���E���[�U�[�@1900�N�j���T���[���X�E�J�E���e�B���p�� |
�R���}���E���[�U�[���S��������6��i1900�N�j�́A���{���p���e�[�}�ł����B�A�h���t�E�t�B�b�V���[���N�W�����A�����G��H�|�i�Ȃǂ̓��{���p���o�W����܂����B �I�[�X�g���A��1873�N�̃E�B�[�������ɂ���ē��{���p�u�[�����N���A�c���q�ƂȂ����t�����c�E�t�F���f�B�i���g�����E�������s��1893�N�ɓ��{��K��A���r�ɗ��̎h�����肷��Ȃǂ��Ă���A���߂ď㗬�K����m�I�K��������{���p�͒��ڂ��W�߂Ă��܂����B 1������2���܂ŊJ�Â��ꂽ�Z�Z�b�V�����W��700�_�߂���i���o�W����A�E�B�[���|�p�E�ő�]���ƂȂ��������ł��B�R���}���E���[�U�[�̃A�[���`�F�A�́A���{�̊�؍H����g���ăf�U�C������Ă��܂��B���{���}���ɐ��m������܂������A���[���b�p�̎��_�Ō���A���m���p�ւ̓��{���p�̉e���������������������ł��傤�ˁB |
|
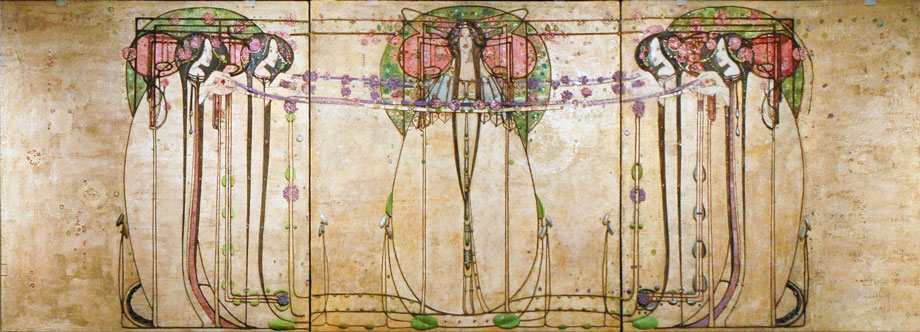 �wThe Wassail�x 5���̏����i�}�[�K���b�g�E�}�N�h�i���h�E�}�b�L���g�b�V���@1900�N�j �wThe Wassail�x 5���̏����i�}�[�K���b�g�E�}�N�h�i���h�E�}�b�L���g�b�V���@1900�N�j |
���N��11������12���ɂ����ẮA��8��Z�Z�b�V�����W�̃e�[�}�́w�O���̍H�|���p�x�ł����B ���̂悤�ȗ���ŁA���{���p�̉e�����Ȃ���i���𐋂������_���X�^�C���̃}�b�L���g�b�V���v�Ȃ����҂��ꂽ�̂́A�������R�Ȃ��Ƃƌ�����ł��傤�B |
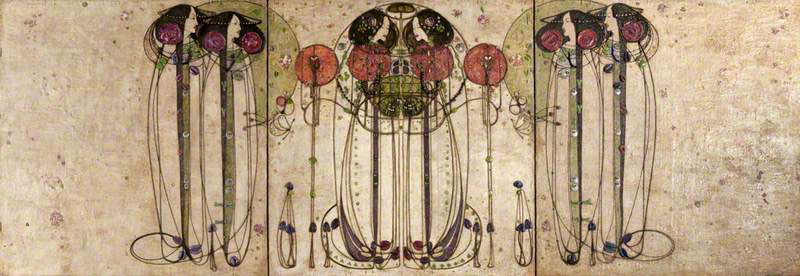 �wThe Wassail�x(�}�[�K���b�g�E�}�N�h�i���h�E�}�b�L���g�b�V���@1900�N) �wThe Wassail�x(�}�[�K���b�g�E�}�N�h�i���h�E�}�b�L���g�b�V���@1900�N) |
���ɒj���A�[�e�B�X�g�����ɂƂ��ẮA�v�`���[���Y���w�V�ˁx�Ə^����}�[�K���b�g�Ɠ��̊����ɑ傫���h�����ꂽ��������܂���B ���ɃN�����g�͕�����₷���ł��B |
 |
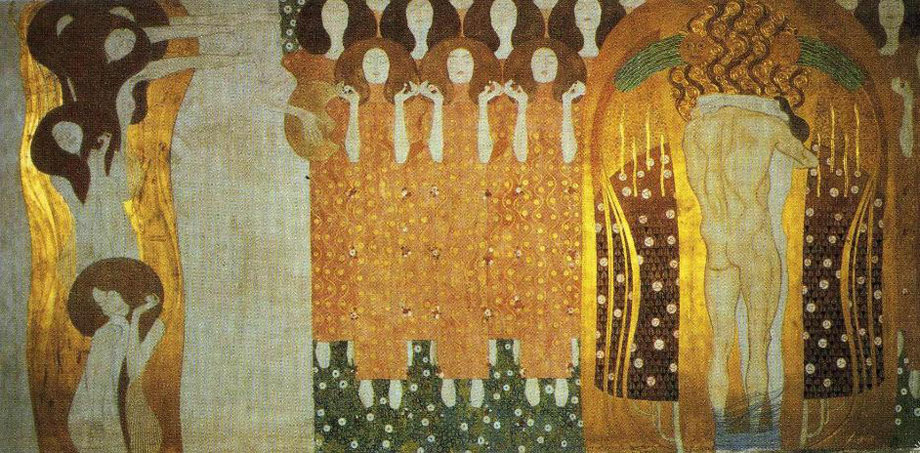 �w�x�[�g�[�x���E�t���[�Y�x�i�O�X�^�t�E�N�����g�@1901-1902�N�j �w�x�[�g�[�x���E�t���[�Y�x�i�O�X�^�t�E�N�����g�@1901-1902�N�j |
"�������Ȑl"�Ƃ�����ۂ����������N�����g�ł����A���̌�̍앗�͑傫�Ȑi���𐋂��܂����B�Z�Z�b�V�����W�̒���ɕ`���ꂽ�̂��A���́w�x�[�g�[�x���E�t���[�Y�x�ł��B |
| ���_���X�^�C�� -�V�˃}�[�K���b�g�̑�\��- |
�Z�Z�b�V���� -�N�����g��������̑�\��- |
 �w���̃I�y���x�i�}�[�K���b�g�E�}�N�h�i���h�E�}�b�L���g�b�V���@1903�N�j �w���̃I�y���x�i�}�[�K���b�g�E�}�N�h�i���h�E�}�b�L���g�b�V���@1903�N�j |
 �w�ڕ��x�i�O�X�^�t�E�N�����g�@1907-08�N�j �w�ڕ��x�i�O�X�^�t�E�N�����g�@1907-08�N�j |
�N�����g��������̑�\��w�ڕ��x���A�}�[�K���b�g�̑�\��w���̃I�y���x�ɃC���X�s���[�V�������ĕ`���ꂽ�Ƃ�����i�ł��B�Ɠ��̍\�}�͊ԈႢ�Ȃ��ł��傤�B �P���ȃ��m�}�l�ł͂Ȃ��A������ƃN�����g�̒��œƎ��̍�i�Ɏd�オ���Ă��܂��B�����炱���̍����]���Ƃ�������ł��傤�B |
|
 �Z�Z�b�V���� �g���}���� �l�b�N���X �Z�Z�b�V���� �g���}���� �l�b�N���X�I�[�X�g���A�@1900�`1910�N�� SOLD |
�W���G���[�̃f�U�C�������l�ł��B �A���O���E�W���p�j�[�Y�E�X�^�C������i���������_���X�^�C���ɉe�����A�I�[�X�g���A�œƎ��̐i���𐋂��܂����B �������Ȃ���A�J�e�S���C�Y�͕s�\�ł��B ��������ƓƎ��̖��͂�����A1�̃W�������Ƃ��Ċm���ł���قǁA�����͐������闬��ƂȂ����悤�ł��ˁ� |
3-1-1-3. �e�n�ɉ����郈�[���b�p�E�f�U�C���̐i��
 ���X�N���̃j���[�E�X�^�C���W�̏o�W��i�i�}�b�L���g�b�V���v�ȁ@1902�N�j ���X�N���̃j���[�E�X�^�C���W�̏o�W��i�i�}�b�L���g�b�V���v�ȁ@1902�N�j |
���_���X�^�C���̃}�b�L���g�b�V���v�Ȃ�́A���E�����ڂ���Z�Z�b�V�����W�ŕ]���ƂȂ�A�傫�Ȓ��ڂ��W�߂܂����B ���̌��ʁA�e�n�̓W����ɏ��ق���A�u�_�y�X�g�A�~�����w���A�h���X�f���A�x�l�`�A�A���X�N���ȂǑ����̍������܂����B�������āA�A���O���E�W���p�j�[�Y�E�X�^�C������i���������_���X�^�C�����A�e�n�̃f�U�C���ɉe����^���A���[���b�p�̃f�U�C���̐i�����N�����܂����B |
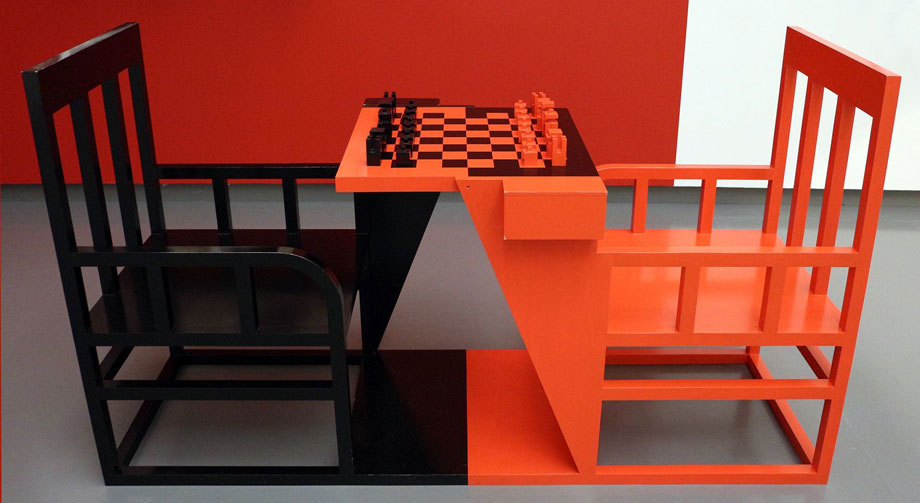 �w�Ώ̐��A�[�g�x�i�A���L�T���_�[�E���h�`�F���R�ɂ��`�F�X�e�[�u���E�f�U�C���@1925�N�j �w�Ώ̐��A�[�g�x�i�A���L�T���_�[�E���h�`�F���R�ɂ��`�F�X�e�[�u���E�f�U�C���@1925�N�j" Alexandr rodchenko, scacchi da dopolavoro, progettaz. 1925, ricostruito nel 2007, 01 " ©Sailko(12 March 2016, 12:17:466)/Adapted/CC BY-3.0 |
�ŏI�I�ɂ͑S�̂Ƃ��ăA�[���f�R�Ɏ������Ă����܂����A1900�N�ォ��1910�N�キ�炢�܂ł͊e���̓Ǝ��F�������āA���ꂼ��̖��̂ŌĂ�Ă��܂��B���V�A�̏ꍇ���w���V�A���E�A���@���M�����h�x�ł��B |
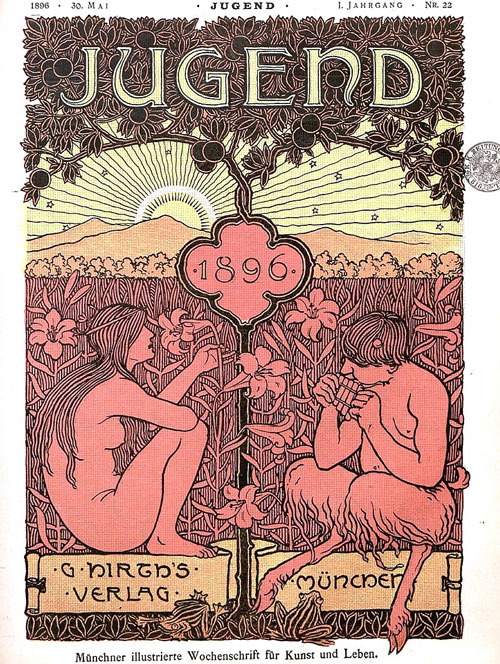 �G���w���[�Q���g�x�̕\���i1896�N�j �G���w���[�Q���g�x�̕\���i1896�N�j |
�I�[�X�g���A��h�C�c�Ȃǂ̃h�C�c�ꌗ�ł́A���I�����p�̌X�����w���[�Q���g�E�V���e�B�[���x�ƌĂ�Ă��܂��B �ێ�������A����܂łɂȂ��V�����X�^�C���ݏo�������|�p�Ƃ����ɂ���ă~�����w���ŕ����h�����܂�܂����B ���ꂪ�x��������I�[�X�g���A�ɂ��g�y���A1899�N�Ƀx�����������h�A1897�N�ɃE�B�[�������h���a�����܂����B �Z�Z�b�V�����ƌĂ��E�B�[�������h���A���[�Q���g�E�V���e�B�[���̈�h�ƌ����܂��B |
 ���[�Q���g�V���e�B�[���@�v���J�W���[���E�G�i�����@�y���_���g ���[�Q���g�V���e�B�[���@�v���J�W���[���E�G�i�����@�y���_���g�h�C�c�@1900�N�� SOLD |
���[���b�p�̏]���̃X�^�C�����o���A�V�����X�^�C���ݏo�����Ƃ����C�s�̃f�U�C�i�[�����B ���[���b�p���p�Ƃ͑S���قȂ�l���������{���p�ɉ\�������o���A���s���낵�Ă������ŁA�}�b�L���g�b�V���v�Ȃ�̃��_���X�^�C���͂��̐������1�Ƃ��đ傢�ɎQ�l�ɂȂ������Ƃł��傤�B �������ă��[���b�p�e�n�Ńf�U�C���̐i�����N���A�Ɠ��̐V�����f�U�C�������ݏo����Ă����܂����B |
3-1-2. �H���ȃ��_���X�^�C���`���[�Q���g�V���e�B�[���̃n�C�W���G���[
 |
Gen�������u�h�����ōD�݁I�I��v�ƌ����郂�_���X�^�C���̃W���G���[�ł����A����܂ł�46�N�Ԃł��Љ�����͋ɂ߂ď��Ȃ��ł��B ���ɃG�h���[�f�B�A�����̃v���`�i���g�������̂͐��_�ŁA�����m�����ł́A�s�A�X�͏��߂Ă̂��Љ�ɂȂ�܂��B ����ɂ͂�����Ɨ��R������܂��B |
 �G���̃|�X�^�[�i�`���[���Y�E���j�[�E�}�b�L���g�b�V���@1896�N�j �G���̃|�X�^�[�i�`���[���Y�E���j�[�E�}�b�L���g�b�V���@1896�N�j�y���p�zMoMA ©Acquired by exchange from the University of Grasgow / The Museum of Modern Art |
���ł����^�������̗����Ă��郂�_���X�^�C����[�Q���g�V���e�B�[���̃f�U�C���ł����A�����͂ǂ�����ْ[�̑��݂ł����B �C�M���X�ł̃}�b�L���g�b�V���v�Ȃ�̕]�����U�X�Ȃ��̂ŁA����1896�N�̃A�[�c���N���t�c�W�ł͎�Î҂���u��ȑ����̕a�v�Ɣ���A�Ȍ�̏o�i���֎~����Ă��܂��������ł��B �������ْ[�̑��݂������E�B�[�������h�����ڂ������ƂŁA���[���b�p�e�n�̃f�U�C���̐i���ɍv�����邱�ƂƂȂ�܂����B �������Ȃ��玞��ɍ���Ȃ������悤�ŁA�唼�̃��[���b�p�l�ɂ͉��l���������ꂸ�A��N�͌��z�̎d�����Ȃ��Ȃ�A�`���[���Y�͐��ʉ�Ƃɓ]�����Ă��܂��������ł��B |
 �}�x�p�[���E�V���o�[�E�l�b�N���X�i���[�[�t�E�z�t�}���@1909�N�j �}�x�p�[���E�V���o�[�E�l�b�N���X�i���[�[�t�E�z�t�}���@1909�N�j�y���p�zMASTERART / JOSEF HOFFMANN / WIENER WERKSTATTE / Necklace ©MASTERART |
�Z�Z�b�V���������ł����������m������Ă��܂����A�����͂����܂ł����C���X�g���[�����痣�E�����ْ[�̑��݂ł����B�����烈�[�[�t�E�z�t�}�����f�U�C�������W���G���[�����Ă݂Ă��AHERITAGE�ł��Љ�ł��郌�x���̍����i�͂���܂���B �W���G���[�̃f�U�C�������ł͂Ȃ��������Ƃ����邩������܂��A�w�A�N�Z�T���[�x�ƃJ�e�S���C�Y�����������������Ɗ����邭�炢�����ۂ��ł����A�ޗ��������p�ł��B |
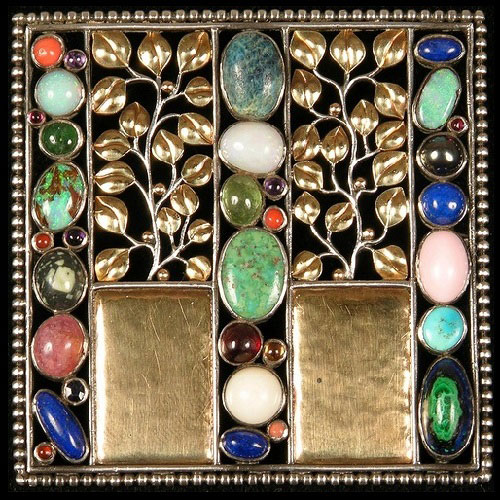 ���M�̃V���o�[�E�u���[�`�i���[�[�t�E�z�t�}���@1908�N�f�U�C���A1914�N����j ���M�̃V���o�[�E�u���[�`�i���[�[�t�E�z�t�}���@1908�N�f�U�C���A1914�N����j�y���p�zMASTERART / JOSEF HOFFMANN / Brooch ©MASTERART |
����̓~���[�W�A���E�s�[�X�Ȃ̂ŁA���[�[�t�E�z�t�}���̃f�U�C�������W���G���[�Ƃ��Ă͂��Ȃ�}�V�Ȃ��̂ł��B �V���o�[�f�ނɈ����ۂ����r�b�V���ŁA"�L���f�U�C�i�[�̃T�C���h�s�[�X"�ł����Ă����̓v���C�h�ɂ����āA��ɂ���舵���ł��Ȃ��㕨�ł��B �L���f�U�C�i�[�ł����Ă��W���G���[�Ɋւ��Ă͓��ӕs���ӂ���������A����Ȃ��̂������Ƃ������Ƃ����z������������Ǝv���܂��B |
�A�[�c���N���t�c�̐A�����`�[�t����荞��ł���悤�ł����A�f�U�C�����S�`�����悤�����{�l�̊��o�ɂ͍����܂���B �V���v���E�C�Y�E�x�X�g�͕��ƕ����Ŕ��W���܂����B���[���b�p�͌��X�A���ԂȂ������Ŗ��ߐs�����̂����O�W���A���[�Ƃ��������ł����B�V���v���E�C�Y�E�x�X�g�̓��[���b�p�̒j���ɂ͂�����x����₷���Ă��A�����͗����ł���l�����Ȃ��������ʂ�������܂���ˁB �f�U�C�i�[�͓��y�ł͂���܂���B�����Ă����l�����Ȃ���A�����͌p���͕s�\�ł��B�������Ɍ�������́A�܂�̂Ȃ���̃S�`���S�`���������̂��D�ސl���܂����������̂ł��傤�B�v���悤�Ƀf�U�C���ł����A�z�t�}���͐����������Ă��������Ƃ��m���Ă��܂��B �������Ƌ�Ȃǂƈ���ă_�T���f�U�C���ł����A�z�t�}���������̃W���G���[�Ɋւ��Ă͖{�]�ł͂Ȃ�������������܂���E�E�B |
| ���l���ɕx�ރG�h���[�f�B�A���̃W���G���[�E�f�U�C�� | |||
| �A�[�c&�N���t�c�̌n�� | ���[���b�p�� �`���X�^�C���̌n�� |
�A���O���E�W���p�j�[�Y�E�X�^�C���̌n�� | |
| �A�[���k�[���H�[�n | �K�[�����h�X�^�C���n | ���_���X�^�C���` ���[�Q���g�V���e�B�[���n |
�A�[���f�R�ɂȂ���n |
 �wMIRACLE�x �C�M���X�@1905�`1915�N�� ¥10,000,000-�i�ō�10%�j |
 �w�i���̈��x �w�i���̈��x�_�C�������h �y���_���g���u���[�` �t�����X�H�@1910�N�� ��1,220,000-(�ō�10%) |
 �wREBIRTH�x �wREBIRTH�x�Z�Z�b�V�����i�E�B�[�������h�j�@�l�b�N���X �I�[�X�g���A�@1905�`1910�N�� SOLD |
 �V�R�^�쁕�_�C�������h �u���[�` �V�R�^�쁕�_�C�������h �u���[�`���[���b�p�@1910�N�� SOLD |
�n�C�W���G���[�̐���́A�n�C�W���G���[��g�ɂ�����ʃN���X�̃p�g���������˂ł��܂���B �G�h���[�f�B�A���̃W���G���[�s�������ƁA�n�C�W���G���[�͂�͂胁�C���X�g���[���̍�i�������ł��B���ł����������m�����Ă��郂�_���X�^�C����[�Q���g�V���e�B�[���ł����A�����͂܂��������ǂ����Ă��炸�A�ŏI�I�ɂ͋쒀����Ă��܂������C���X�g���[���̕������|�I�����h�������Ƃ������Ƃł��傤�B |
|||
 �}�U�[�E�I�u�E�p�[���̃V���o�[�E�u���[�`�i���[�[�t�E�z�t�}���@1912�N�j �}�U�[�E�I�u�E�p�[���̃V���o�[�E�u���[�`�i���[�[�t�E�z�t�}���@1912�N�j�y���p�zMASTERART / JOSEF HOFFMANN / Brooch ©MASTERART |
���������킯�ŁA���[�[�t�E�z�t�}���قǒm���x�̂���f�U�C�i�[�ł����Ă��A�����f�ނō�����ʎY�p�̈����i�ꉞ�n���h���C�h�j����Ȃ̂ł��B |
 |
���̂��߁A���_���X�^�C����[�Q���g�V���e�B�[���̃n�C�W���G���[�͋ɂ߂Đ������Ȃ��ł��B ���̈���ŁA�������肵�߂�����i�I�ȃX�^�C���𗝉��ł���قǂ̐l�����I�[�_�[���������Ȃ̂ŁA�������ꍇ�͕K���f�U�C�����������Q�ɗD��Ă���ƌ�����قǁA�f���炵���ꍇ�������ł��B |
3-1-3. �����I�ȕ��͋C�����͂̋H���ȃW���G���[
 |
���_���X�^�C����[�Q���g�V���e�B�[���̃n�C�W���G���[�ɋ��ʂ���̂��A���܌��Ă������I�Ɗ�������A�s�v�c�Ȃقǂ̖����I�ȕ��͋C�ł��B |
���_���X�^�C��
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
���[�Q���g�V���e�B�[��
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
3-1-4. ���Ƀ��A�ȃv���`�i��̂̃��_���X�^�C���E�W���G���[
 |
���_���X�^�C����[�Q���g�V���e�B�[���̃n�C�W���G���[����ׂĂ݂܂����B���Ƀ��_���X�^�C���͑f�ނƂ��āA�S�[���h��̂̊�����������ۂł��B 1900�N�̃Z�Z�b�V�����W�ȍ~�A���[���b�p�嗤�e�n�Ƀ��_���X�^�C�������e����^����悤�ɂȂ��Ă����܂����B �v���`�i������I�V�f�ނƂ��ăW���G���[�̈�ʎs��ɏo�n�߂�̂́A�Z�p�I�ۑ�ƎY�o�ʓI�ȉۑ�̑o�����������ꂽ���1905�N������ł��B |
�v���`�i��1914�N�u��������ꎟ���E���ɂ���āA�\���ȗʂ��g���Ȃ�����������܂����B�܂��A�v���`�i�o��̏����͋����ʂ̖�肪����A�g�p�ł���ʂɐ�����܂����B�ǂ���̗��R���A�����������Ă��K�����������ł��Ȃ����̂ł��B ����2��ނ̗��R�ɂ��A�G�h���[�f�B�A���̓v���`�i�ɃS�[���h�o�b�N�̍��̃n�C�W���G���[�����݂��܂��B |
| �I�[���E�S�[���h | �ꕔ�v���`�i���g�p |
 �wMODERN STYLE�x
�wMODERN STYLE�x���_���X�^�C�� �_�C�������h �S�[���h �u���[�` �C�M���X�@1890�N�� SOLD |
 �Z�Z�b�V�����i�E�B�[�������h�j�u���[�` �Z�Z�b�V�����i�E�B�[�������h�j�u���[�`�I�[�X�g���A�i�E�B�[���j1900�`1910�N�� SOLD |
���_���X�^�C����[�Q���g�V���e�B�[�������ɒ��ڂ��ꂽ�̂́A1900�N�O��ł��B���傤�ǃW���G���[�̈�ʎs��ɁA�v���`�i���o�ꂷ��O�㍠�ƂȂ�܂��B���̂��߁A�v���`�i�o��ȑO�͍ō����̋����Ƃ��ăS�[���h���ґ�Ɏg�p�������̕����݂��܂��B �܂��A�o�n�ߍ��͏\���ȗʂ��m�ۂł��Ȃ����Ƃ�����A�_�C�������h�����݂̂Ƀv���`�i���g���Ȃǂ̍��̂��̂�����܂��B |
|
 �w�X�g���C�v�x �w�X�g���C�v�x�V�R�^�쁕�_�C�������h �y���_���g �C�M���X�@1910�N�� SOLD |
 �wThe Great Wave�x �wThe Great Wave�x�T�t�@�C�A���_�C�������h �u���[�` �C�M���X�@1910�N�� SOLD |
�^�C�~���O�I�ɁA�v���`�i����̂Ƃ��ă��_���X�^�C���̃W���G���[�͊����I�ɏ��Ȃ��̂ł��B �����f�U�C���ł����Ă��A�S�[���h���v���`�i�̕�����薢���I�Ȉ�ۂ���ł��傤�B |
| 1900�`1920�N���̃n�C�N���X�̃s�A�X | |||
| ���_���X�^�C�� | �g�����W�V�����E�W���G���[ | ||
 |
 |
 |
 |
1900�N����1920�N���ɂ����Ẵs�A�X����ׂĂ݂܂����B��ԉE�̓v���`�i�ɃS�[���h�o�b�N�̃G�h���[�f�B�A���̍��ŁA���_���X�^�C���I�ȓ���������܂����A�f�U�C���I�ɂ̓A�[���f�R�ƌĂԕ����������肭��̂��g�����W�V�����E�W���G���[�ƃJ�e�S���C�Y����̂��K�ł��傤�B ���ʂ̂Ȃ����痈��X�^�C���b�V�������������ŁA���肰�Ȃ��f�U�C�����ґ�ɋZ�p�Ǝ�Ԃ������Ĕ�������ǂ����߂�"�B�ꖳ��̓���"������Ă����̂����_���X�^�C���̍ő�̓����ł��薣�͂ł��B �����g�����Ƀ��_���X�^�C���D���Ȃ̂ŁA��������K�������t���Ă��܂����A5�N�ԂŃs�A�X��3�_�ڂł��B�v���`�i���Ɍ����2�_�ڂł��B����̃f�U�C���ɂȂ���A�[���f�R�E�f�U�C���Ȃ�A���͋C�����������̂͂܂����݂��܂����A���_���X�^�C���͓����ł�����Ԃ��������ґ�Ȃ��̂������̂ŁA���R�Ȃ���ގ��̂��̂͂���܂���B |
|||
 |
�ꌩ����ƂƂĂ��V���v���Ȉ�ۂȂ̂ɁA�ƂĂ������I�ȃf�U�C���̃s�A�X�ł��B �ɏ�̓V�R�^��ƃN���A�ȃ_�C�������h���g�p���Ă��܂����A����f�U�C���ɖڂ��s���܂��B������D�ꂽ�f�U�C���Ȃ�ł͂̓����ł��B �������肵�߂������_���X�^�C���𗝉����A���ꂾ���̃W���G���[����ʃI�[�_�[�ł����l���Ƃ����̂́A�M���̖v�����������������������͂��܂���B���Ȃ���ʂŁA�H�����̍����Ȃ̂ł��B |
3-1-5. �ґ�ȍ��ɗR�����関���I�ȕ��͋C
3-1-5-1. ���G�ɐv���ꂽ�▭�̎��^�t�H����
 |
���܂�Ɉ�a���̂Ȃ��������t�H�����Ȃ̂ŁA���G�Ȑv�ɂȂ��Ă��邱�ƂɋC�Â��ɂ����̂ł����A���̃p�[�c�ɂ͋����قǍ��x�ȃf�U�C���v�ƋZ�p���l�ߍ��܂�Ă��܂��B �܂��O���ɒ��ڂ���ƁA�������͑��݂����A�Ȑ����I�݂Ƀf�U�C�����Ċ��炩����V���[�v����\�����Ă��邱�Ƃ�������܂��B�����̐�����▭�ł��B�����Ȃ�f�U�C������̂��A���̂��P���ŊȒP�������͂��ł����A����ł͂��̕��͋C�͏o�܂���B �������̃f�U�C���ɂ��āA�����̓o�����X�̗ǂ������c���̎��^�ɂȂ��Ă���̂��Z���X���ǂ��ł��B |
 |
���̃p�[�c�̓t���b�g�ł͂Ȃ��A���̕����ɂ����G�Ƀf�U�C������Ă��܂��B�ӂ�����Ƃ����t�H�����ƁA���S�ɐ��������悤�A���E�ňقȂ�ʂ̕����ɂȂ��Ă��܂��B |
 |
���ƂȂ����͋C�͂������肢��������ł��傤���B |
 |
�P���ȃt���b�g�`��ł͂Ȃ��A�ǂ̕��������G�ȗ��̂Ƀf�U�C������Ă��܂��B |
 |
 |
���̂��߁A���̓�����p�x�ɂ���ĕ��G�ɕ\��ω����܂��B�h���\�������炱���A���̕\��̖L��������������A���ۂɃs�A�X�Ƃ��Ē��p���Ă��鎞���ł����͓I�Ɍ����܂���� |
|
3-1-5-2. ����ɂ����ʂȍ��
 |
���̃s�A�X�́A�v���`�i�ɃS�[���h�E�o�b�N�̃G�h���[�f�B�A���̍��ł��B |
 |
 |
�Ƃ���ŏ㕔�̓V�R�^��̃p�[�c�ƁA�����̎��^�̃p�[�c������ׂ�ƁA�v���`�i�̕��ʂ��S���قȂ邱�Ƃɂ��C�Â�����������ł��傤���B�㕔�̃p�[�c�͒ʏ�̃S�[���h�o�b�N�Ƃ�����ۂł����A���^�̃p�[�c�͌������Ȃ���I�[���E�v���`�i�̂悤�ɂ������܂��B |
|
 |
���͂��̃p�[�c�͒���ɂȂ��Ă���A�����ɏ����Ȍ�������܂��B �����ɂ�钆��̍��ɂ���ہA�ł������̂ł��B |
 �A���t�H���^�@�^�[�R�C�Y���S�[���h�@�s�A�X
�A���t�H���^�@�^�[�R�C�Y���S�[���h�@�s�A�X�C�M���X�@1860�`1870�N�� �g���R�A15ct �S�[���h SOLD |
 |
| ����̍����w�Ñ�̃A���t�H���x�̃s�A�X�ł����邱�Ƃ��ł��܂����B |
����W���G���[�͗ʎY�ɓK�����w�����i���イ�����j�x�Ŗw�ǂ�����܂��B�����A�C���������̂��u�����C�R�[�����v�Ƃ����킯�ł͂Ȃ����Ƃł��B ������@���Ēb����w�b���i�����j�x�́A������n�����ė�₵�ł߂������̒�����苭�x�����߂邱�Ƃ��ł��܂��B��菭�Ȃ��ʂŁA���x���o�����Ƃ��ł��܂��B �P�ɒ��߂邾���̔��p�i�ƈقȂ�A�g�ɂ��Ďg���W���G���[�ɂ͑ϋv�����K�v�ł��B�K�v�ȑϋv�����o�����Ƃ���ƁA�����ł͂��Ȃ�̕��ʂ̋������K�v�ƂȂ�܂��B������{�e�b�Ƃ����f�U�C���ɂȂ��Ă��܂��܂��B������ƊE�́u�S�[���h�i�����̓v���`�i�Ȃǁj���ґ�Ɏg�������O�W���A���[�ȍ��v�ƕ\������킯�ł��B�P�ɑ@�ׂȃf�U�C�������Ȃ��̂��떂�������߂ł���A�{�e�b�Ƃ����_�T���W���G���[�����������i�Ɗ��Ⴂ�����č��l�Ŕ̔����邽�߂̐�`����ł�������܂���B �A���e�B�[�N�̃n�C�W���G���[�͑ϋv�����K�v�ȏꍇ�A��ԁi�܂肨���j���������Ă��b���ō��܂��B��ɗ͂�����������A�ǂ����ɂԂ����肵�₷�������O�ł�������A���E�̍ۂɗ͂�������u���[�`�Ȃǂ́A���ɑϋv�����K�v�ł��B |
 �A���t�H���^�@�^�[�R�C�Y���S�[���h�@�s�A�X �A���t�H���^�@�^�[�R�C�Y���S�[���h�@�s�A�X�C�M���X�@1860�`1870�N�� �g���R�A15ct �S�[���h SOLD |
�s�A�X�͑��̃A�C�e���ƈقȂ�܂��B���E�̍ۂ��A�͖͂w�lj����܂���B�̂ɒ������I���ł��܂��B �M�����ł���S�[���h��v���`�i�͏d�����ł��B���������x����ׂĂ݂܂��B �����ŕς����̂́A�S�[���h��v���`�i�͒ʏ�̋����̔{���炢�d��������܂��B |
���̂悤�ȁA�����Ղ�̐ς�����f�U�C���̏ꍇ�A���̂܂܋���ō��Ƃ��Ȃ�̏d�ʂƂȂ�܂��B�h���\�����ƁA���ɏd�����s�A�X�͎��ւ̕��S���傫���ł��B���������Ή����������A���̃s�A�X�����ό`���Ă��܂��܂��B�����Ȃ�ł͂̒���̍��́A�y���ł��郁���b�g������̂ł��B |
 |
�܂��A�^���g���̂ŕ��G�Ȍ`�ł��S�������`�ɂ��邱�Ƃ��\�ł��B�����ł��o�����X�������ƁA���͋C���ς���Ă��܂��f�U�C���ɂ͒����͍œK�ƌ����܂��B |
 |
�܂��A�܂�����ꂽ�ʂ����g���Ȃ���������ɁA�܂�Ńv���`�i�����ō��ꂽ���̂悤�Ɍ����܂��B ���ɂ��̂悤�Ȓ����̃v���`�i�ɂ��A���e�B�[�N�W���G���[�͌������Ƃ��Ȃ��A�Z�p�I�ɂ����ʂɊJ�����ꂽ���̂��Ƒz���ł��܂��B �S�[���h�ƃv���`�i�ł͗Z�_���S���قȂ��Ă���A�����炱���v���`�i����ʂ̃W���G���[�s��ɓo�ꂷ��̂�20���I�ɓ����Ă���ł����B����܂ł̃S�[���h�p�̓����Z�p�����̂܂g�����킯�ł͂Ȃ��͂��ł��B |
�܂��A�C�����Ă��������̂�"�����C�R�[������"�Ƃ����킯�ł͂Ȃ����Ƃł��B �^���g�������́A�ʎY�ł��郁���b�g������܂��B1�^�����A�������̂�100�A1,000�ƗʎY�ł��܂��B���̃X�P�[�������b�g�ɂ���āA�����ɐ��i��ł���悤�ɂȂ�܂��B �ǂ�ȏꍇ�ł��A�}�X�^�[�ƂȂ�^�𐧍삷��ɂ͂����ƋZ�p�Ǝ�Ԃ�������܂��B100���ꍇ�́A���̔�p��1/100���ϓ��ɕ��S���܂��B1,000���Ȃ�Δ�p���S��1/1,000�ōς݂܂��B���ꂪ�X�P�[�������b�g�ɂ��R�X�g�_�E���ł��B |
 |
���̃��_���X�^�C���̍Ő�[������ȃf�U�C���́̕A�������ʎY�ł͂���܂���B �ʎY�i��100�{�A1,000�{�̃R�X�g�������āA���̗B��̕�����Ă���̂ł��B ����ɂ���ĉ���M���̍ō����i�炵���C�i�A�������h��A�y�₩�ȕt���S�n�����������ƌ�����ł��傤�B�����܂ł�����͖̂ő��ɂȂ����炱���A�������Ƃ��Ȃ��悤�ȕƌ�����̂ł��B |
3-1-5-2. "���̔�"���ӎ��������_���X�^�C���炵���f�U�C��
 |
�����̎��^�̃p�[�c���f���炵���ł����A�㕔�̓V�R�^��̊O���̃v���`�i�̗ւ��ƂĂ����͂�����܂��B �����"��"�Ƃ��ċP������悤�t���b�g���C���ō���Ă��܂��B �����w���̔��x���Ӑ}�����t���b�g���C���̃f�U�C���́A���_���X�^�C���̃W���G���[�ɂقڋ��ʂ�������ł��B |
 �wSTYLISH PINK�x �wSTYLISH PINK�x�s���N�g���}���� �y���_���g �C�M���X�@1900�N�� SOLD |
�w���̔��x�A�w�������̔��x�A�w��Ԃ̔��x�Ȃǂ�\�����邽�߂́w�t���b�g���C���x�́A���_���X�^�C���ȑO�̃A���e�B�[�N�W���G���[�ł͌��Ȃ��Z�@�ł��B �w���̔��x�A�w�������̔��x�A�w��Ԃ̔��x���ӎ��������{���p�̉e�����Đ��ݏo���ꂽ�\�����ɂ߂č����A���{�l�Ɠ��̔��ӎ������[���b�p�̈ꕔ�̐l�������������n�߂�����ƍl�����܂��B �ȑO�̃��[���b�p�ł́A�Ӑ}���ăt���b�g�Ȑ��ŕ\���������̂͂���܂���ł����B |
 �wSamurai Art�x �wSamurai Art�x���_���X�^�C�� �A�N�A�}����&�V�R�^�� �l�b�N���X �C�M���X�@1900�`1910�N�� SOLD |
"��"�͂��̑��݊����ɗ͔������邽�߂ɁA����Ȃ��ʐς̂Ȃ�2������"��"�Ƃ��ĕ\�����邱�Ƃ��ǂ����߂��܂����B �̂ɁwSamurai Art�x�̉����ɂ���悤�ȁA�i�C�t�G�b�W�̋Z�@�ŕ\������̂��n�C�W���G���[�̊�{�ł����B �i�C�t�G�b�W�ƃt���b�g���C���̗������g���ăf�U�C�������͂���ȊO�Ɍ������Ƃ��Ȃ��قǒ������ł����A���ӎ��̍�������M���̂��߂ɍ��ꂽ�A���e�B�[�N�̃n�C�W���G���[���A"���̕\��"���ӎ����ċZ�@���g�������Ă������Ƃ�������M�d�ȏƂȂ��Ă��܂��B |
 �w�X�g���C�v�x
�w�X�g���C�v�x�V�R�^�쁕�_�C�������h �y���_���g �C�M���X�@1910�N�� SOLD |
 |
�i�C�t�G�b�W��Ȗʂŕ\�����ꂽ"��"�Ƃ͖��炩�ɈقȂ鐫���������܂��B�����̒ʂ�A�t���b�g���C���͂���u�Ԃɋ���ȑ��݊�������܂��B |
| ������ۓI�ȋP������t���b�g���C�� | |||
 |
 |
 �w���Ԃ̃����f�B�x �w���Ԃ̃����f�B�x�C�M���X�@1900�N�� SOLD |
 �wSamurai Art�x �wSamurai Art�x�C�M���X�@1900�`1910�N�� SOLD |
| �w�����ɋP���A���t�H���x �C�M���X�@1900�N�� SOLD |
|||
���݊����Ɍ��܂Ŗ��������߂̃i�C�t�G�b�W��"���e��"�̗v�f�ƂȂ�܂����A�t���b�g���C���͎����1�Ƃ�������قNj������͂�����܂��B �_�C�������h��~���O���C���Ȃǂ̋P�����l�A���̖��͂͐Î~��ł͕�����ɂ�����������܂���B��ɂ����ڂ��s���Ȃ������n�D�ƈقȂ�A��z�����f�U�C���͂ƍ��x�ȋZ�p�������Ă����̔������ł��B�����ɂ������������邱�Ƃ����A���ӎ��̍�������M���̂��߂ɍ��ꂽ�n�C�W���G���[�̏ł�����̂ł��B |
|||
 �wALL WHITE�x �wALL WHITE�x�I�[���h���[���s�A���J�b�g�E�_�C�������h�@�s�A�X �C�M���X�@1910�N�� SOLD |
�v���`�i�̔����d���ȋP���́A�S�[���h�̃t���b�g���C����肳��ɋ���Ȉ�ۂ�^���܂��B |
 |
 |
�L���ʐςł͂Ȃ��A���悢�ʐς�"��"�Ƃ��ċP�����炱����i�����������ƂȂ��A�Z���X�̗ǂ��Ɩ��������������������Ă���܂���� �������̔��A��Ԃ̔��A�����Đ��̔��B�����ȕɂ́A�������̃f�U�C���v�f�����߂��Ă���A���ꂪ�������Ɩ����I���͋C�ɂȂ��Ă���킯�ł��B |
 |
���Ȃ݂ɂ���͍ɊǗ��̂��߂ɁA�������ƃX�}�[�g�t�H���ŎB�����摜�ł��B �{���A������������̂ł͂���܂��A���܂��ܕЕ��̃t���b�g���C�������������˂��Ă��܂����B���̈�u�́A�_�C�������h�̋P���ȏ�ɋ�����ۂ�^�������Ƃ��������肢��������Ǝv���܂���� |
3-2. ���������o�����߂̌����ȍ\���f�U�C��
 �_�C�������h�E�s�A�X�i�e�B�t�@�j�[�@2023�N�j �_�C�������h�E�s�A�X�i�e�B�t�@�j�[�@2023�N�j¥2,365,000- �y���p�zTIFFANY & CO / �e�B�t�@�j�[ �n�[�h�E�F�A �����N �s�A�X©T&CO |
�W���G���[�Ƃ��Ďg�p���邽�߂̑ϋv�����o�����߂ɁA����W���G���[�͊y�����悤�Ƃ��āi���Ȃ킿�����R�X�g�̐ߖ�j�A�����Ղ�Ƌ������g���܂��B �����p�Ȃ̂ɁA�����Y�W���G���[�̂悤�Ȗ����Ń{�e�b�Ƃ�����ۂ̂��̂������̂͂��̂����ł��B ������A�Ȃ��Ȃ��ł��ˁB �_�C�������h�͍��v1.18�J���b�g�������ł��B�����ȃ����_�C���̓T�C�Y�⎿�ɂ��˂�܂����A�ʔ̂Ő��S�~�Ŕ����邭�炢�����ł��B��胁�[�J�[�̈ꊇ�d����Ȃ�Α������������Ă�͂��ł��B 236��5��~�͍����u�����h�Ƃ��āA���Ȃ�L����`���`���z���オ����Ă������ł��ˁB |
 |
���x�ȋZ�p�����E�l�̎�d���ō��ꂽ�A���e�B�[�N�̃n�C�W���G���[�����ɋZ�p�Ǝ�ԁi�܂肨���j�������邱�ƂŁA�@�ׂȔ������Ƒϋv���𗼗������܂��B ������̏d�ʊ�����f�U�C�����嗬�s�����~�b�h���B�N�g���A���E�W���G���[�ƈقȂ�A���͂̕Ƃɂ����y�₩���������܂��B �ւ�����܌^�̃p�[�c�́A�܂�Œ��ɕ����Ă��邩�̂悤�Ɋ����܂��B |
 |
 |
�������ɕ����Ă��邩�̂悤�ȕs�v�c�Ȋ��o�������A"�����I"�Ɗ��������邽�߂Ɍv�Z���ꂽ�t���[�`���[�E�f�U�C���̂Ȃ���Z�ł��B��������A��Ԃ��������I�݂ȋZ�����邱�Ƃ��ł��܂��B �㕔�̓�d�~�̃p�[�c�́A�V�R�^��ƃv���`�i�̗ւ�A������c�̓y����i�C�t�G�b�W�Ɏd�グ�Ă��܂��B������V�R�^����v���`�i�̗ւ����ɕ����Ă���悤�Ɍ��������ŁA�ϋv���Ƃ��Ă�100�N�ȏ�̎g�p�ɂ��r�N�Ƃ����Ȃ����x��ێ����Ă��܂��B �����̗܌^�̃p�[�c���A���ʂ��炾�Ƌ��x�͑��v�Ȃ̂��s���Ɏv���قǂ̌����ڂł��B�㉺��������2�ӏ����A�����͂��Ȑڒn�ʐς����ŘA�����Ă���悤�Ɍ����܂��B�������Ȃ��痠��������ƁA�S�[���h�̐c�_�ł�������Ǝx�����Ă��邱�Ƃ�������܂��B |
|
 |
�����Ȃ��H�v��A���̂��߂̋Z�p�����ɂ͋������܂��I�I�� ���ꂼ�A���ӎ��̍�������M���̂��߂ɍ��ꂽ�ō����i�ɑ�����������ł��B �A���e�B�[�N�̃n�C�W���G���[�ł������܂ŋC�������Ă��āA�Z�p�I�ɂ����x�ȋZ����g����Ă�����͖̂ő��ɂȂ��A�܂��ɍō����i�Ə̂���ɑ��������ł��B |
 |
�V�R�^���܌^�̃p�[�c�����ɕ����Ă���悤�Ɍ�����̂́A���ɂ��H�v������܂��B �T�C�h���炲�����������ƁA���ꂼ�ꏭ����яo���悤�ɍ\���f�U�C������Ă��邱�Ƃ�������܂��B�͂��Ȃ��ƂɌ����܂����A���ꂪ�傫�Ȏ��o���ʂƂ��Č����Ă��܂��B |
 |
�V���v���Ɍ�����f�U�C���̒��ɁA�ǂ�قǂ̃A�C�f�A�ƃZ���X�����߂��Ă���̂��E�E�E�B ���������̂ɂ́A�K�����R������̂ł��E�E�E���� |
3-3. ���Ԃ�Ȃ�������ɂ�����������
 |
�f�U�C�����D��Ă���قǁA��̓f�U�C���̈ꕔ�Ƃ��Ē��a���Ă���A��Ύ��̂����܂萦�����Ɍ����܂���B �������Ȃ���A����M���̓���p�̍ō����W���G���[�ɑ��������A�ƂĂ��㎿�ȕ���g���Ă��܂��B ���ꂱ�����A�ȑf�Ȉ����Ƃ͖��炩�ɈقȂ�|�C���g�Ƃ������܂��B |
3-3-1. �Ő�[�̃g�����W�V�����J�b�g�E�_�C�������h
 |
�_�C�������h��2���݂̂ł����A���ʂȐ��Z�b�g����Ă��܂��B �]���̃I�[���h���[���s�A���J�b�g�ł͂Ȃ��A�����̍Ő�[�ƌ�����g�����W�V�����J�b�g�̃_�C�������h�ł��B |
 |
�ƂĂ��N���A�ȃ_�C�������h�ŁA�J�b�g�̎d�グ���ǂ����Ƃ���A�P���������ł��B���̂��߁A�J�b�g�̏ڍׂ͕�����ɂ�����������܂���B����́w�g�����W�V�����E�J�b�g�x�ɂȂ��Ă��܂��B |
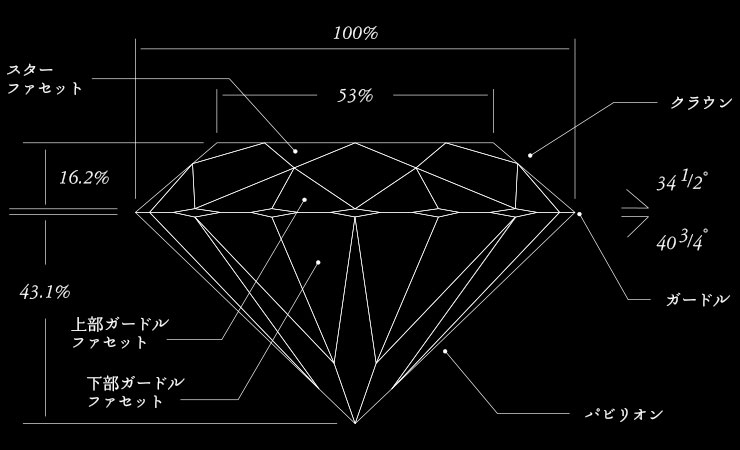 |
 �w�~���[�E�_�C�������h�x �w�~���[�E�_�C�������h�x�A�[���[�E���B�N�g���A���@�I�[���h���[���s�A���J�b�g�E�_�C�������h �����O �C�M���X�@1840�N�� ¥3,700,000-�i�ō�10%�j |
�����ԁA�n�C�W���G���[�̃_�C�������h�̃J�b�g�̓I�[���h���[���s�A���J�b�g���嗬�ł����B�����̃L���[���b�g���J�b�g����Ă��邱�Ƃ�������1�ł��B �J�b�g���ߑ㉻�����ȑO�A�d���_�C�������h�̃J�b�g�͂ƂĂ���ςł����B�����炱�������y���ɍ����i�������킯�ł����A�L���[���b�g���J�b�g����Ă������R�͉��ł��傤�B |
 �w�K���̃����f�B�x �w�K���̃����f�B�x�_�C�������h�@�u���[�` �C�M���X�@1880�N�� SOLD |
�Z�p�I�ɂ��J�͓I�ɂ��A�ߑ㉻�ȑO�̓J�b�g���邾���ō�����ɂ߂܂����B �Ώ̐��̍������k�ȃJ�b�g�́A���ꂱ���s�\�ƌ�����قǂł����B �̂ɑ����ȍ����i�ł��A19���I�ȑO�̃_�C�������h�̓��t�ȃJ�b�g�ł��邱�Ƃ������ł��B ���ꂱ�����A���x�ȋZ�p�����E�l�̃n���h���C�h�����炱���o�Ă��閡�킢�ł���A�l�H�I�ȋ@�B�H�Ɛ��i�ł͂Ȃ��|�p���������闝�R�ł�����܂��B ������Gen���u�Â��_�C�������h�̕������͂������čD����v�ƌ����킯�ł����A�Ώ̐������̂�������炱���A�����̃L���[���b�g��1�_�ɐ��m�ɃJ�b�g������������̂�����ł����B |
|
| �I�[���h���[���s�A���J�b�g | �g�����W�V�����J�b�g |
 1910�N���̃W���G���[��� 1910�N���̃W���G���[��� |
 1930�N��̃W���G���[��� 1930�N��̃W���G���[��� |
���̂��߃L���[���b�g����蕔���A������Ă����悤�ł��B�d�������@�ƃ_�C�������h�\�E����������A�Ώ̐��̍����J�b�g���ȒP�ɂł���ɘA��āA�L���[���b�g���J�b�g����K�v���Ȃ��Ȃ��Ă����܂����B ����嗬�̃u�����A���E�J�b�g�̓L���[���b�g���J�b�g����Ă��܂��A�Â��I�[���h���[���s�A���J�b�g���猻��̃J�b�g�Ɍq����܂ł̉ߓn���̃J�b�g�Ƃ��āA�w�g�����W�V�����J�b�g�x������܂��B |
|
 �A�[���f�R �g�����W�V�����J�b�g�E�_�C�������h �����O �A�[���f�R �g�����W�V�����J�b�g�E�_�C�������h �����O�C�M���X�@1930�N�� SOLD |
����̔����炢�u�����A���J�b�g�Ƃ��قȂ�A�������ƋP���𗼗������J�b�g�ł��B �J�b�g������ɋ߂��̂ŁA�Â��������Ȃ��ł��ˁB �����1930�N���̕ł��B ����M���̎��オ���S�ɏI�����}�������́A���Ǝ�`�ɂ���Ĕ��������R�X�g�J�b�g���D�悳��A��C�ɖ��͂̂Ȃ�����̃J�b�g�Ɉڂ�ς���Ă��܂��܂��B |
 |
�w�X�p�C�_�[�x �I�[���h���[���s�A���J�b�g�i�g�����W�V�����J�b�g�j�E�_�C�������h�A���[�Y�J�b�g�_�C�������h�A�G�������h�A���r�[�A�v���`�i�A�V���o�[�A18ct�S�[���h |
�ŏ����̃g�����W�V�����J�b�g���̕Ō��邱�Ƃ��ł��܂��B1900�N���́A�R���e�X�g�E�W���G���[�̉\����������i�ł��B �f�U�C��/���/�f�ނ��O���q�����Ă���̂��R���e�X�g�E�W���G���[�̓����ł��B���C���X�g�[���̃_�C�������h��1ct�ȏ�̑傫���ƁA�����Ȃ܂ł̃N���[���������˔������ł��B������g�����W�V�����J�b�g���{�������ʂȕ�����炱���A�R���e�X�g�ɏo�W���邽�߂̓��ʂȍ�i�̃��C���X�g�[���Ƃ��Đ��������킯�ł��B |
 |
 |
|
||
���̕��R���e�X�g�E�W���G���[�ɕC�G�������������Ă��܂��B ����R���e�X�g�o�i�̂��߂ɁA���ꂾ�������ȑf�ނ��g�p���ăW���G���[�𐧍�ł��郂�_���X�^�C���̃f�U�C�i�[�͂��炸�A����͉���M���̃I�[�_�[�i���낤�ƍl���Ă��܂��B �����A�����Ɏ��ڂ����������삳���Ă����I�[�_�[��̂��߂ɁA�A�[�e�B�X�g���E�l���v���C�h�ƍ������߂Đ��삵���̂��낤�Ƒz�����܂��B �Ő�[�̃J�b�g���{���ꂽ�A�������Ȃ�����ɏ�̃_�C�������h�B |
||||
 |
�L���[���b�g�̐�[������ƁA�ƂĂ����x�ǂ��J�b�g����Ă��邱�Ƃ�������܂��B �]���̃I�[���h���[���s�A���J�b�g���قȂ�B����̃`���`���Ƃ����ア�P���������ĂȂ��A�C�f�A���J�b�g�Ƃ��قȂ�A���ʂȖ��͂�����Ă܂��B �܂��Ƀ��_���X�^�C���̍ō����i�ɑ��������_�C�������h�ł���� |
 |
���̔������������́A�N����������S�Ĕ��˂���悤�v���ꂽ����̃A�C�f�A���J�b�g�ł͏o���Ȃ����̂ł��B�{���A�������̓_�C�������h�̑傫�Ȗ��͂�1�Ȃ̂ł��I�I |
 |
�����āA�����x�̍����N���A�Ȑ����炱���������t�@�C�A������Ƃ��ł��܂��B ���̃^�C�~���O�ł́A���M�Ȉ�ۂ̃u���[�̃t�@�C�A���o�Ă��܂��� |
 |
�_�C�i�~�b�N�ȃV���`���[�V�����ɁA�S�[�W���X�ȃt�@�C�A�B�I�[���h���[���s�A���J�b�g�̎����͂�ێ����Ȃ�����A�L���[���b�g���J�b�g����Ă��炸���m���̍����g�����W�V�����J�b�g�E�_�C�������h�ɂ́A�����I�Ŗ��邳�ɖ������P��������܂��B ������1�����ɍ��߂�ꂽ�Z�p�Ɣ������ւ̋����z���́A�����ڈȏ�ɑ傫���̂ł��I��� |
3-3-2. �㎿�ȓV�R�^��
 |
���͓̕V�R�^����g���Ă��邱�Ƃ��A�|�C���g��1�ł��B �������ł����A�傫���A�F�A�Ƃ艐�Ȃǂ̎������������㎿�ȓV�R�^����g�p���Ă��܂��B �{�B�^��̂悤��"���w��i�ŒE�F���Đ��F����"���F��������O�A�L�k������č����"�T�C�Y�̑������j"�ɔ����^��w�����b�L���������̐l�H���ƈႢ�A�O�ς������悤�ȓV�R�^��𑵂��邱�Ƃ����ł����ɑ�ςł��B |
 |
���̕����ꂽ����́A�j��ł��V�R�^�삪�����]������Ă�������ł����B |
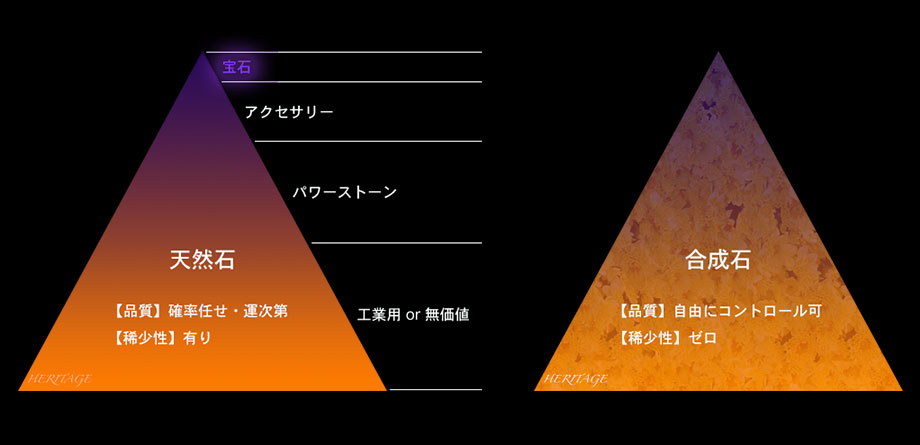 |
�~�����������Y���ċ������\�Ȑl�H���i�H�Ɛ��i�j�ł���{�B�^��́A�H�����l�������܂���B���Еt�����Ă������l������悤�Ɍ����A�����l�i�Ŕ����Ă��܂����A�{����"���"�𖼏��Ȃ��㕨�ł��B ���邪�܂܂��g���V�R�^��̏ꍇ�A�S�Ă��n�C�W���G���[�̕�Ƃ��Ďg����킯�ł͂���܂���B�F�A�`�A�����ȂǑS�Ă������O�ς����������̂́A�ق�̈ꈬ��ł��B |
 |
�j�̌`�f�������`����̗{�B�^��ƈقȂ�A�V�R�^��͂��̌`����l�X�ł��B���`�̏ꍇ�͓V�R�^��l�b�N���X�A�{�^���p�[���͍������o�߂��Ȃ������ǂ������O�A��������n�[�t�p�[���ɂ��Ęe���Ƃ��Ďg���ȂǁA�S�Ă̓V�R�^��͌��ɍ��킹�ēK�ޓK���ł��B ���̓̕V�R�^��̓X���C���̂悤�ȏ����ׂꂽ�`�����I�ł��B�ǂ������Ƀf�U�C���ɓ����ł��܂��B |
 |
�V�R�^��̎��͋ɏ�ŁA�܂��ɍō����W���G���[�ɑ��������ł��B�v���`�i�ɉf����z���C�g�J���[�A�������������鐐�X�������A���܊���������F�̊����B |
 |
 |
 ←↑���{ |
���Ƃ���ɔ����������Ɉӎ����s�����A�����傫���������h���鐬���W���G���[�Ƃ͂���������I�ɈقȂ�̂ł��B�������Ă����ɂ���������������V�R�^��́A�܂��ɔ��ӎ��̍�������M���̂��߂ɍ��ꂽ�ō����i�ł���ƌ�����ł��傤�B |
 |
���F�̊������яオ�点��V�R�^��ɁA�F�Ƃ�ǂ�̃t�@�C�A����_�C�������h�B �v���̊O�A�F�Ƃ�ǂ�̕ƌ����邩������܂����� |
3-4. �����Z�p��������������O���C�����[�N
 |
 |
|
||
���̕��ō����i�Ƃ��č���Ă���Ǝ����ł���|�C���g�Ƃ��āA���x�̍����~���O���C��������܂��B ����ɁA���肰�Ȃ������x�̍����O���C�����[�N���f�U�C�����Ă��邱�ƂŁA���ӎ��̍�������M���̍ō����i�ł���Ɗm�M�ł��܂��B |
||||
3-4-1. �������O���C�����[�N�̑��݉��l
| �y�L��z �A���e�B�[�N�̍ō����i |
�y�����z ����̍����ʎY�W���G���[ |
 �w�����x �w�����x�A�[���f�R�@�W���|�j�Y���@�y���_���g �C�M���X�@1920�N�� SOLD |
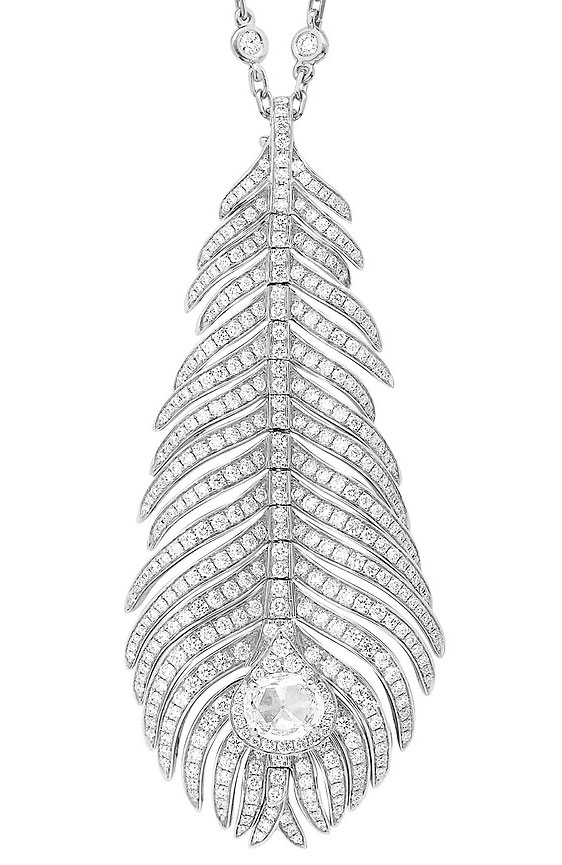 �y�Q�l�z�u�V������ �_�C�������h�E�l�b�N���X
¥7,920,000-�i�ō��j2023.2.2���� �y�Q�l�z�u�V������ �_�C�������h�E�l�b�N���X
¥7,920,000-�i�ō��j2023.2.2�����y���p�zBOUCHERON / �v������ �h�D�@�p�I���@�y���_���g�@���[�W ©BOUCHERON |
�O���C�����[�N�͈ꌩ����ƒn���ȍH�ł����A�������f�U�C���ƕ��͋C�ɂ͕K�v�s���ł��B��������ӎ��̍�������M���̂��߂ɍ��ꂽ�A���e�B�[�N�̃n�C�W���G���[�ł́A������O�̂悤�Ɍ��邱�Ƃ��ł��܂��B �E�̌���W���G���[��800���~�߂�������u�����h�i�ł����A�f�U�C���I�ɖ��͂������܂����H�_�C�������h���V�������Ⴏ�Ă����Ƀm�b�y��������ۂŁA���ɂ̓`���`�ȃA�N�Z�T���[�̂悤�ɂ��������܂���B800���~�ǂ��납8��~�ł�����Ȃ��ƌ������A���������^�_�ł��v��Ȃ��ł��B���Ƀm�b�y���Ƃ��Č�����̂́A�H���̐�[�܂Ń_�C�������h�Ŗ��ߐs������Ă��邩��ł��B ��[�ɃO���C�����[�N������A���̃O���f�[�V�����ɂ���ē�����@�ׂ���������ꂽ�͂��ł��B ����W���G���[�́A�����i�Ƃ��č����l�i�Ŕ̔�����Ă�����̂ł��ʎY�̒����i�ł��B���������ŁA�A���e�B�[�N�̃n�C�W���G���[�̂悤�ɕi���������킯�ł͂���܂���B�����̍��Ȃ̂ŁA���̂悤�ȃm�b�y���Ƃ������ƃf�U�C���ɂ����ł��܂���B���i�̑唼�̓u�����f�B���O�̂��߂̃v�����[�V������p��`���z����ł���A�����R�X�g�������Ă��܂���A���m�Ƃ��Ă͂���Ȃ��̂ł��傤�B |
|
3-4-2. �O���C�����[�N�̓�Փx���猩���Ă���ō����i�̏�
Gen�������v���C�h�ɂ����āA�ō��i���̕������Љ�܂���B������A�A���e�B�[�N�W���G���[�Ȃ�ǂ�ł���肪�ǂ��Ɗ��Ⴂ�����������������邩������܂���B �������͔��t���ŗl�X�ȕi���̃A���e�B�[�N�W���G���[�����܂��B���̖w�ǂ͂��Љ�ł��Ȃ��N�I���e�B�ł��B |
 |
�Ⴆ���ꂾ�ƁA���X�Ȃ�����i�Ƃ��Ă��Љ��Ǝv���܂��B ���ہA�A���e�B�[�N�W���G���[�̒��ł͈ꉞ�����ȕ��ނɓ���܂����A�������̊�͑S���������܂���B �~���O���C����O���C�����[�N�̍�������Έ�ڗđR�ł��B |
| �y�Q�l�zHERITAGE�ł͈���Ȃ����x���̃G�h���[�f�B�A���E�u���[�` |
 �y�Q�l�zHERITAGE�ł͈���Ȃ����x���̃G�h���[�f�B�A���E�u���[�` �y�Q�l�zHERITAGE�ł͈���Ȃ����x���̃G�h���[�f�B�A���E�u���[�` |
�g�傷��ƁA�O�`�����ƒׂꂽ�悤�ȋC�����������Ƃ�������܂��B���ɍ�����E��Ɉʒu����O���C�����[�N���������������ƕ�����₷���ł��傤���B���̂悤�ɁA��肪�����n���h���C�h�E�W���G���[�͊g��ɑς����܂���BHERITAGE���g��摜���f�ڂ������ŁA���X�͂��ꂪ�ł��Ȃ����R��1�ł��B |
 HERITAGE�i���̍̕�� HERITAGE�i���̍̕�� |
 �y�Q�l�zHERITAGE�̊�ɖ����Ȃ���� �y�Q�l�zHERITAGE�̊�ɖ����Ȃ���� |
HERITAGE�i���̕��ƁA�O���C�����[�N�͂܂�ŗ�����X�t�������̂悤�ɍۗ����Ă��܂��B�r�̗ǂ��Ȃ��E�l�ɂ��t�قȍ�肾�ƁA�O�`���b�Ƃ��������悤�ɂȉ����O�ςł��B����ł��O���C�����[�N�����邾���܂��}�V�ŁA�{���̈������Ƃ��������O���C�����[�N���{�����Ƃ��炵�܂���B ���̊ϓ_�ł́A�O���C�����[�N������Ƃ��������ł�"������x�̍����i"�ƌ����܂��B�O���C�����[�N�͋Z�p�I�ɓ�����炱���A�E�l�̘r�ɂ���ē��Ɏd�オ��ɑ傫�ȍ����o�܂��B�A���e�B�[�N�W���G���[�̗ǂ����������ɂ߂��ł́A�������Ȃ��Z�@�ƌ�����̂ł��B |
|
3-4-3. �ō����i�̏ƂȂ�������O���C�����[�N
 |
 |
|
||
���̃̕O���C�����[�N�͎��Ɍ����ł��B�����ɖ����グ���Ă��邩�炱���A����̋P�����ƂĂ��������ł��B ���ۂ̃T�C�Y�����z�����������ƁA�l�Ԃ�������Ƃ͎v���Ȃ��悤�Ȑ_�Z�̍H�ł��邱�Ƃ��������肢��������Ǝv���܂��B �������A�����̑�ꋉ�̘r�����E�l�ɂ���i�ł��B |
||||
 |
�O���p�[�c�͒����ɂ�钆��̍��ł����A�����̃p�[�c�͒b���ł��B���݂̂���b���̓y���[�����o���āA���̃p�[�c������Ă��܂��B���o���ۂɁA���ɃO���C�����[�N�ƂȂ镔����c���Ă��邱�Ƃ�������܂��B�L�����Ƃ������������ۗ��A�����Ȏd���Ԃ�ł��� |
 |
 |
 ←↑���{ |
�ƂĂ������ȃX�y�[�X�ɁA�ɂ߂č��x�ȋZ�p���l�܂��Ă��܂��B |
����
 |
�����������Ŕ��������ł��B �s�A�X������ɁA15ct�S�[���h������585�̍�����܂��B |
 |
 |
�y���ėh���\���ł����A�����\���̃s�A�X����Ȃ̂ŁA���Ƃ��ɂ����̂��ǂ��ł��ˁ� ������͕����������̂��A����̕��������ł��B ����̕��͖�1cm�ŁA�����Ԃ����߂̕��ł��g���₷�����ł��B �����Ԃ������ăs�A�X���X���Ă��܂����́A�V���R���L���b�`���T�[�r�X�ł��t�����܂��̂ŁA��둤�ł���������������Ǝv���܂��B |
���p�C���[�W
 |
���I�ȃf�U�C���ł����A���Ԃ�Ȃ̂ň��ڗ������邱�ƂȂ��A�l�X�ȃR�[�f�B�l�[�g�ɍ��킹�₷���Ǝv���܂��B �_�C�������h��V�R�^�삾���łȂ��A�����͉���I�ȐV�f�ނƂ��čł����ڂ��W�߁A�X�e�[�^�X�̏ے��Ƃ��ăf�U�C���̃|�C���g�ƂȂ��Ă���v���`�i���悭�P���܂��B ���Ԃ�Ȃ̂ɑ��݊�������A������`��P���ł�������ƌ���҂𖣗����邱�Ƃ��ł���A�B�ꖳ��̖��f�̕ł��I�� |
 |
��芪�����̕ω���A�����I�ȈӐ}�ɂ��C�M���X�M�����͂������Ă���������B ��ꎟ���E�����_�@�ɁA����ɑ傫���͂𗎂ƎЌ��E�S�̂̎��ƕ��͋C���ς���Ă��܂��O�����炱���n�邱�Ƃ̂ł����A�ɂ߂��ґ�ȕB �������肵�߂������_���X�^�C���̖��͂������ł����A�����Ȃ�����M���̋M�w�l�E�E�B |
�]���ł���A���̂悤�ȋM���������p�g�����ƂȂ�A���s���Ȃ��甭�W�𐋂��Ă����͂��ł����B���ꂪ�I�ɕs�\�ƂȂ��Ă��܂����A"�f�U�C���i���̃s�[�N"�Ƃ�������̂��w���_���X�^�C���x�Ȃ̂ł��B ���̔w�i������A���_���X�^�C���̔������̓A���e�B�[�N�̃n�C�W���G���[�̒��ł����ɋ߂����݂ƂȂ��Ă��܂��܂����B�ō����������S�[���h����v���`�i�ֈڂ�ߓn�����������Ƃ�����A�v���`�i��̂̃��_���X�^�C���͂���ɒ������A�g���₷���s�A�X�Ƃ��Ȃ�A�s��ł��܂����ڂɂ����邱�Ƃ͂���܂���B �܂��Ɋ�Ղƌ�����A�����Ȕ������ł��E�E�B |









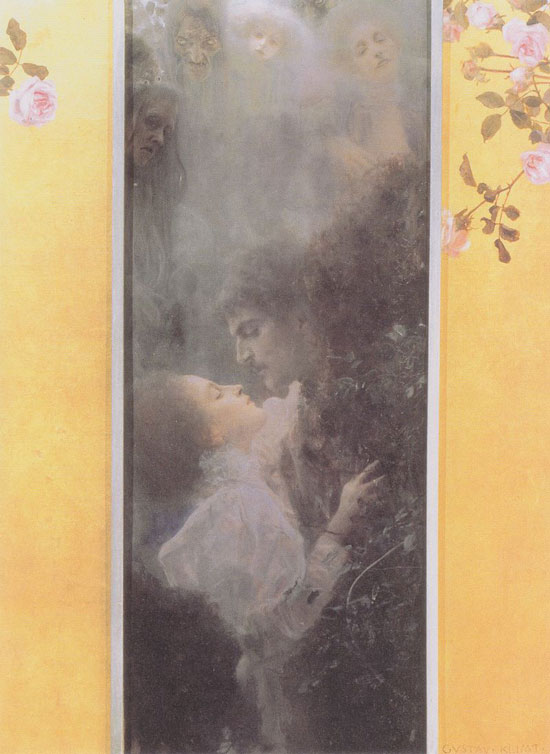 �wLiebe�i���[�x�F���j�x�i�O�X�^�t�E�N�����g�@1895�N�j���B�G���i���p��
�wLiebe�i���[�x�F���j�x�i�O�X�^�t�E�N�����g�@1895�N�j���B�G���i���p��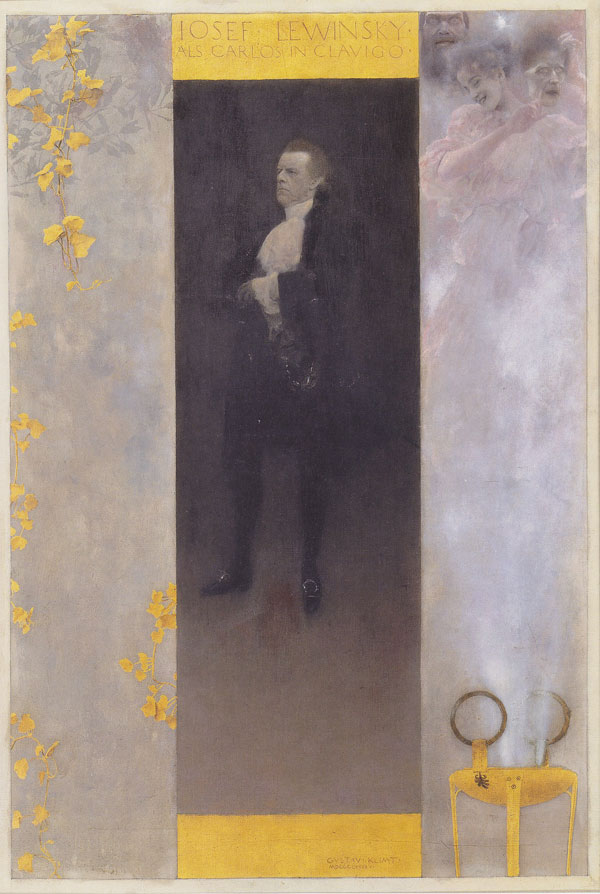 �w�Y��"�N�����B�[�S"�ŃJ�����X��������{����҃��[�[�t�E���C���X�L�[�x�i�O�X�^�t�E�N�����g�@1895�N�j
�w�Y��"�N�����B�[�S"�ŃJ�����X��������{����҃��[�[�t�E���C���X�L�[�x�i�O�X�^�t�E�N�����g�@1895�N�j
 �y�Q�l�z����W���G���[
�y�Q�l�z����W���G���[